
Z世代が重視する「タイパ」とは?採用選考プロセスに取り入れるべき3つの改善点
記事公開日 : 2026/02/13
最終更新日 : 2026/01/15
記事公開日 : 2025/08/12
最終更新日 : 2026/01/15
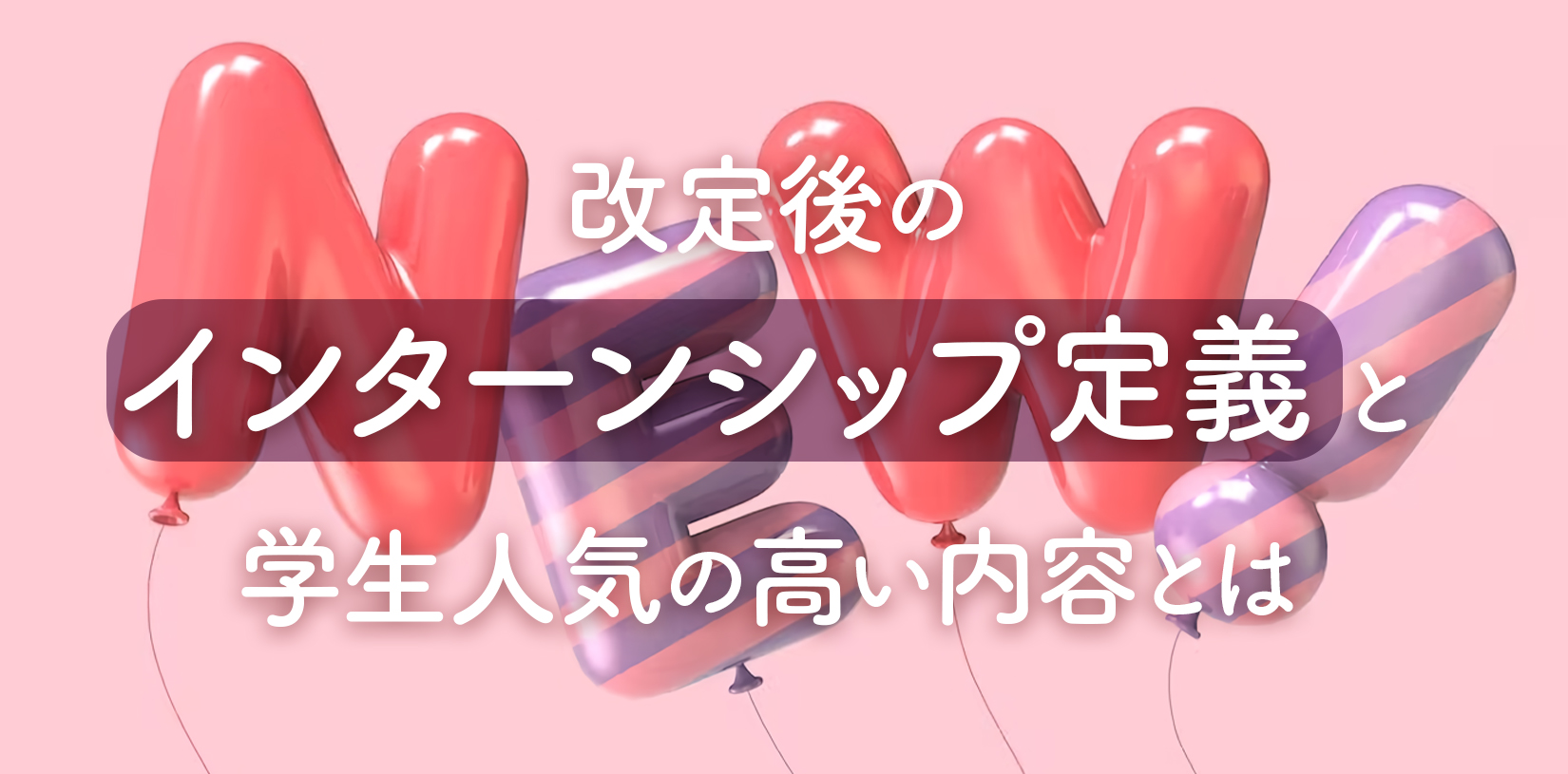
2025年卒以降のインターンシップ制度は、政府による「三省合意」の改正により、その定義と位置づけが大きく変化しました。この改定は、学生のキャリア形成支援をより強化し、企業の新卒採用活動に新たな影響を与えるものです。本記事では、インターンシップの新たな定義、そして学生から特に人気の高いプログラムの内容について詳しく解説し、それらが採用活動にどう影響するかを探ります。

インターンシップは、学生が在学中に自身の専攻や将来のキャリアに関連する仕事の経験を積む活動として広く認識されています。従来、インターンシップで得られた学生の情報は、採用活動に利用できないとされていましたが、2022年6月に経済産業省・文部科学省・厚生労働省による「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方(通称:三省合意)」が改正されたことにより、2025年卒以降は一定の条件を満たせば採用活動への活用が可能となりました。
この背景には、新卒採用市場の売り手市場化と、従来の採用活動だけでは企業が十分な母集団形成を行うことが難しくなった現状があります。特にベンチャー企業やスタートアップ企業では、認知度の低さから、従来の採用スケジュールでは求める学生の確保が困難でした。新しいルールでは、企業側が学生の能力や適性を見極め、ミスマッチを防ぎながら早期に優秀な人材を確保できるような仕組みが整えられています。これにより、学生はより実践的な知識や経験を積む機会を得られる一方で、企業はインターンシップを通じて学生のリアルな姿を把握し、採用に繋げることが期待されています。
2025年卒以降のインターンシップにおける新ルールでは、学生の参加期間、開催時期、就業体験の有無、実施場所、企業側による指導とフィードバックが重要な要件として定められています。まず、学生の参加期間については、汎用的能力活用型インターンシップの場合は5日間以上、専門性が高い業務の場合は2週間以上と明確化されました。また、就業体験は必須となり、参加期間の半数を超える日数を職場で実際に業務を体験することが求められます。原則として実施場所は職場ですが、リモートワークが常態化している企業の場合はリモートでの実施も認められます。
さらに、職場社員による学生への指導とフィードバックが義務付けられ、学生の学びを深める機会を提供する必要があります。これらの要件を満たすインターンシップで取得した学生情報は、採用活動開始以降に限り、企業側が採用選考に活用できるようになりました。これにより、従来のインターンシップが単なる会社説明会の延長と捉えられる実態から、より実践的な就業体験の場へとその位置づけが変化し、新卒学生の就職活動においてインターンシップが採用に直結する重要な機会となっています。
インターンシップを始めとする学生のキャリア形成支援に係る取り組みは、その内容と目的に応じて以下の4つの類型に分類されました。これらの類型は、学生が学修と社会での経験を結びつけ、自身のキャリアを効果的に形成することを目的としています。各類型は、学生がどのような知識や経験を得られるか、企業がどのような目的でプログラムを提供するかによって特徴が異なります。このうち、インターンシップに分類されるのはタイプ3・タイプ4の2分類になります。
タイプ3の「汎用的能力・専門活用型インターンシップ」は、学生が自身の能力や専門性がその仕事で通用するかを見極めることを目的に、企業での就業体験を行う活動を指します。このタイプのインターンシップは、従来の就業体験型インターンシップに近く、特定の専門性を重視したプログラムが提供されます。参加期間は5日間以上とされ、専門性が高い内容を含む場合は2週間以上の実施が求められます。実施期間の半分以上は職場での就業体験に充てることが必須であり、学業との両立に配慮して、学部3年生・4年生または修士1年生・2年生の長期休暇期間に実施されます。また、職場の社員が学生を指導し、インターンシップ終了後には個別のフィードバックを行うことが義務付けられています。
企業はインターンシップ募集時に、取得した学生情報を採用活動に活用する旨を明確に開示する必要があります。このタイプは、採用選考に直接活用できる唯一のインターンシップとして位置づけられ、企業にとっては優秀な学生を早期に囲い込む重要な機会となり、学生にとっては実践的な研修を通じて自身の適性や能力を深く理解できる貴重な体験となります。
タイプ4の「高度専門型インターンシップ」は、高度な専門性を要求される実務の職場体験を伴うインターンシップを指します。この類型は、主に自然科学分野の博士課程学生を対象とした「ジョブ型研究インターンシップ」として既に運用が始まっており、2ヶ月以上の長期にわたる実施が想定されています。また、高度な専門性を重視した修士課程学生向けのインターンシップについても検討が進められています。タイプ4のインターンシップは、学生が専門分野における実践力を向上させることを目的とし、企業にとっては専門的な知識やスキルを持つ学生と共同研究を行うことで、新たな発見や革新を生み出す可能性を秘めています。
タイプ3と同様に、このインターンシップで取得した学生情報は採用活動に活用することが可能ですが、産学協議会が定める厳格な要件を満たす必要があります。学生は自身の専攻を活かしたより専門的な仕事に携わることで、将来のキャリアパスを具体的に描くことができ、企業は特定の分野で即戦力となる可能性のある人材を早期に発掘できるメリットがあります。
2025年卒以降のインターンシップ制度の改定により、インターンシップは採用活動と密接に連携するようになりました。特にタイプ3とタイプ4に分類されるインターンシップでは、企業が参加学生の情報を採用選考に活用することが認められ、これにより早期から優秀な人材の囲い込みが可能になります。企業はインターンシップを通じて、学生の実際の働きぶりや、企業文化への適応度を深く評価でき、採用ミスマッチのリスクを低減できる利点があります。学生にとっても、インターンシップは企業や仕事の理解を深める貴重な機会となり、自身の適性を見極め、入社後の具体的なイメージを持つことができます。
多くの学生がインターンシップへの参加を希望しており、特に「就職活動に有利だと考えたため」という理由が最も多く挙げられています。また、インターンシップに参加した学生の94%がその企業の本選考に応募したいと回答していることからも、インターンシップが学生の志望度向上に貢献していることがわかります。インターンシップでの経験は、選考における面接やエントリーシートの内容に深みを与えるだけでなく、企業側にとっても学生の潜在能力を見極める重要な判断材料となります。このように、インターンシップは単なる職業体験に留まらず、学生と企業双方にとって戦略的な採用活動の一環として位置づけられています。
インターンシップは、実施期間や形式によって様々な種類があり、それぞれ異なる体験を提供します。学生は自身の目的や学業スケジュールに合わせて最適なインターンシップを選択することが重要です。企業側も、求める人材像やインターンシップを通じて達成したい目標に応じて、適切な期間や形式のプログラムを設計する必要があります。例えば、短期間のプログラムは多くの学生に企業の存在を知ってもらう機会として有効であり、長期間のプログラムはより実践的な体験を通じて学生のスキル向上と企業理解を深めることに繋がります。
実施形式においても、対面式とオンライン式があり、それぞれにメリットとデメリットが存在します。対面式では実際の職場環境や社員との直接的な交流を通じて深い体験が得られる一方で、オンライン式では場所の制約なく多くの学生が気軽に参加できる利便性があります。これらの多様な選択肢の中から、学生は自身のキャリア形成に最も役立つ体験を選び、企業は効果的な採用戦略を構築することが求められます。
インターンシップは、その実施期間によって主に「短期」と「長期」に分類され、それぞれ異なる特徴とメリット・デメリットがあります。短期インターンシップは、1dayや半日といった超短期のものから、5日程度、またはサマーインターンのように数週間実施されるものまで多岐にわたります。これらは、学生が気軽に多くの企業や業界に触れる機会を提供し、企業側にとっては広範な母集団形成に繋がりやすい点が特徴です。
一方で、長期インターンシップは、5日以上から数ヶ月、さらには年単位にわたって実施されることがあります。特に2025年卒以降のルール改定では、5日以上の就業体験を伴うインターンシップが「汎用的能力・専門活用型インターンシップ」として採用活動に活用できるようになりました。長期インターンシップは、学生が企業文化や実際の業務に深く関わり、実践的なスキルや経験を積むことができるため、キャリアへの解像度を高め、企業への志望度を向上させる効果が期待されます。企業側も、学生の適性や能力を長期的に見極め、ミスマッチの少ない採用に繋げることが可能です。ただし、長期インターンシップは拘束時間が長くなる傾向があるため、学生は学業との両立を考慮する必要があります。期間によって得られる経験や目的が異なるため、学生は自身の目的や利用可能な時間を考慮して選択し、企業はインターンシップの目的に合わせて期間を設定することが重要です。
短期インターンシップは、一般的に1dayや半日から数日間、またはサマーインターンやウィンターインターンといった長期休暇中に5日〜2週間程度で実施されるプログラムを指します。これらの短期プログラムは、学生が様々な業界や企業に気軽に触れる機会を提供し、企業や仕事の概要を短期間で理解するのに役立ちます。例えば、1dayインターンシップでは、企業説明会や座談会、簡単なワークショップなどが実施されることが多く、職場見学や工場見学が内容に含まれることもあります。これにより、学生は企業や業界の雰囲気を掴み、自身の興味関心を広げることが可能です。企業側にとっては、認知度を高め、広範な母集団形成を行う上で非常に有効な手段となります。しかし、短期間であるため、実際の業務に深く関わる機会は限られ、深い業務理解やスキル習得には繋がりづらいというデメリットもあります。多くの学生が複数の短期インターンシップに参加し、幅広い視野を持つために活用しています。
長期インターンシップは、一般的に5日以上の期間にわたって実施されるプログラムを指します。具体的には、数週間から数ヶ月、さらには1年以上という長期間にわたるものまで存在します。特に、2025年卒以降の新ルールでは、5日以上で就業体験が必須となるインターンシップが「汎用的能力・専門活用型インターンシップ」として、採用選考に活用できる対象となりました。長期インターンシップの最大の特徴は、学生が実際の職場で社員と同様の仕事に携わり、実践的な業務経験を積める点にあります。これにより、学生は企業の実務内容、企業文化、職場の雰囲気を深く理解し、自身の専門スキルや汎用的能力を向上させることができます。企業側にとっては、学生の能力や適性を長期的に見極めることができ、入社後のミスマッチを防ぐ上で非常に有効な手段となります。また、優秀な学生を早期に囲い込み、新卒採用に繋がりやすいというメリットもあります。学生は、学業との両立を図りながら、給与が発生するケースも多いため、経済的な支援を受けつつ、より実践的なキャリア形成を行うことが可能です。
インターンシップの実施形式は、主に「対面式」と「オンライン式」に分けられます。それぞれの形式には独自のメリットとデメリットがあり、企業の目的や学生のニーズに合わせて選択されます。対面式インターンシップは、実際の職場環境で業務を体験し、社員と直接交流することで、企業文化や職場の雰囲気を肌で感じられる点が大きな特徴です。これにより、学生は入社後のイメージを具体的に描きやすく、企業への理解度や志望度を深めることができます。
一方、オンラインインターンシップは、場所の制約がなく、全国どこからでも参加できるため、学生にとっては参加のハードルが低く、多くの企業プログラムに触れる機会が増えます。企業側も、遠隔地の学生にもアプローチできるため、多様な人材の確保に繋がりやすくなります。また、オンラインでの実施は、採用担当者の負担を軽減し、中小企業やベンチャー企業でも導入しやすいという利点があります。企業は、インターンシップの目的や対象学生、プログラム内容に応じて、最適な実施形式を選択することが求められます。近年では、両方の形式を組み合わせたハイブリッド型インターンシップも増えており、それぞれの利点を最大限に活かす取り組みが進められています。
対面式インターンシップは、学生が企業のオフィスや現場に直接赴き、実際の職場で就業体験を行う形式です。この形式の最大の魅力は、企業文化や職場の雰囲気を肌で感じられる点にあります。社員との直接的なコミュニケーションを通じて、企業のリアルな働き方や人間関係を体験でき、入社後のイメージを具体的に描きやすくなります。また、実務に即した指導やフィードバックを直接受けることで、より深い学びやスキル習得に繋がりやすいというメリットもあります。特に、研究施設や工場見学、現場での業務体験など、オンラインでは再現が難しい内容のプログラムに適しています。学生にとっては、企業への理解度や志望度を深める上で非常に有効な機会となる一方で、企業にとっては、学生の主体性やコミュニケーション能力といった非認知能力を直接評価できる利点があります。ただし、参加には場所や時間の制約があるため、遠隔地の学生や学業との両立が難しい学生にとっては参加が困難な場合があります。
オンラインインターンシップは、インターネット環境を活用し、場所の制約なく参加できるweb形式のインターンシップです。この形式の利点は、学生が全国どこからでも参加できるため、参加のハードルが低い点にあります。これにより、地理的な理由でこれまで参加できなかった学生も、多様な業界や企業のプログラムにアクセスできるようになりました。企業側にとっても、幅広い層の学生にアプローチでき、地方の学生や海外の学生にも自社の魅力を伝える機会が生まれます。オンラインインターンシップの内容としては、座学やセミナー形式での企業説明、業界研究、グループワーク、ディスカッション、ケーススタディなどが中心となります。
また、Web会議システムを活用した社員との交流会や、オンラインでの業務体験が可能なプログラムも増えています。オンラインでの実施は、採用担当者の負担が比較的軽く、中小企業やベンチャー企業、初めて新卒採用に取り組む企業でも導入しやすいというメリットがあります。しかし、実際の職場環境や社風を伝えるのが難しい、学生の集中力維持が課題となるなどのデメリットも存在します。そのため、オンラインインターンシップを成功させるには、魅力的なコンテンツ設計と、学生が主体的に参加できるような工夫が求められます。
学生がインターンシップに求めるものは多岐にわたりますが、特に実践的な経験や企業理解を深められる内容が人気を集めています。単なる企業説明会ではなく、実際に仕事を体験できるプログラムや、社員との交流を通じてリアルな情報を得られる機会が学生にとって魅力的です。また、自身のキャリア形成に役立つような、学びや成長を感じられる内容も重視されています。企業側は、これらの学生のニーズを把握し、人気を集めるようなユニークで面白いプログラムを提供することで、優秀な人材との接点を増やし、企業への興味関心を高めることができます。業務体験ワークや事業企画、自己分析など、学生が主体的に参加できるコンテンツは特に人気が高く、終了後のフィードバックも学生の満足度を高める重要な要素となります。
学生がインターンシップに求めるものは、「就職活動に有利だと考えたため」という理由が最も多く、次いで「仕事に対する自分の適性を知るため」が挙げられます。このことから、学生はインターンシップを単なる企業見学ではなく、将来のキャリア選択や就職活動に直結する重要な機会と捉えていることがわかります。特に、具体的な仕事内容や業界について深く理解できる実践的なプログラムが学生からの人気を集めています。楽天みん就の調査によると、「業務体験ワーク」が最も人気が高く、26卒の学生の76.1%が興味を示しています。次いで、「事業企画」が52.1%、「自己分析」が31.6%、「現場受け入れ」が28.8%と続きます。
また、インターンシップを通じて、「業種について具体的に知ることができた」「仕事内容を具体的に知ることができた」という理由で満足度が高い傾向にあります。学生は、座学だけでなく、実際の業務に触れることで、企業や職場の雰囲気をリアルに感じ取りたいと考えています。さらに、社員との交流やフィードバックの機会も重視されており、これらを通じて自身の能力や適性について客観的な評価を得たいというニーズがあります。つまり、学生が面白いと感じ、満足度の高いインターンシップは、単なる情報提供に留まらず、実践的な体験と質の高い学びを提供することが求められます。
学生に人気の高いインターンシッププログラムには、いくつかの共通した特徴があります。最も人気が高いのは「業務体験ワーク」であり、学生が実際に企業の仕事の一部を体験できる内容です。例えば、グループで架空のサービスのデモを作成するプロジェクトワークや、実際の顧客課題を解決するための企画立案・提案を行うといった、実践的なワークが挙げられます。このようなワークを通じて、学生は仕事の面白さや難しさ、やりがいを肌で感じることができます。
次に人気なのは「事業企画」で、企業の新規事業立案や既存事業の改善提案など、ビジネスの根幹に関わる部分に学生が携われるプログラムです。これにより、学生はビジネス思考を養い、企業戦略の視点を学ぶことができます。専門性の高い理系学生には、実際の現場を受け入れる「現場受け入れ」型のインターンシップが人気です。これは、研究室での実験補助や、実際の製品開発プロジェクトへの参加など、自身の専攻や研究内容を直接活かせる機会を提供します。
社員による丁寧なフィードバックやメンター制度が導入されているプログラムも学生から高く評価されています。これにより、学生は自身の強みや課題を明確にし、成長に繋げることができます。ユニークな事例としては、社長のカバン持ちを一日体験し、経営者の考え方や営業としての心得を学ぶといった、普段経験できないような内容も学生の興味を引きます。オリエンテーションや説明会だけでなく、参加者が主体的に考え、行動し、結果に対してフィードバックを受けられるような、実践的で「面白い」と感じられる研修プログラムが、学生の人気を集める鍵となります。
2025年卒以降のインターンシップは、三省合意の改定により、その定義と位置づけが大きく変化しました。これまでの「就業体験」の提供に加え、特定の要件を満たすインターンシップで得られた学生情報が採用活動に活用できるようになったことは、企業の新卒採用戦略において大きな転換点となります。学生のキャリア形成支援は、オープン・カンパニー、キャリア教育、汎用的能力・専門活用型インターンシップ、高度専門型インターンシップの4つの類型に整理され、特にタイプ3とタイプ4が「インターンシップ」として採用直結の対象となります。期間別には短期と長期、実施形式では対面とオンラインがあり、それぞれに異なる特徴とメリットがあります。
学生は、自身の目的や学業との両立を考慮し、実践的な業務体験や社員との交流を通じて、企業や仕事への理解を深められるプログラムを求めています。企業側は、学生のニーズを把握し、業務体験ワークや事業企画、フィードバック制度など、学生が主体的に学び、成長を実感できる魅力的な内容を提供することで、優秀な人材の確保とミスマッチの防止に繋げることが可能です。今回の改定は、学生がより質の高い就業体験を得られる機会を増やし、企業が自社に合った人材を効率的に見つけるための重要な一歩となるでしょう。


記事公開日 : 2026/02/13
最終更新日 : 2026/01/15
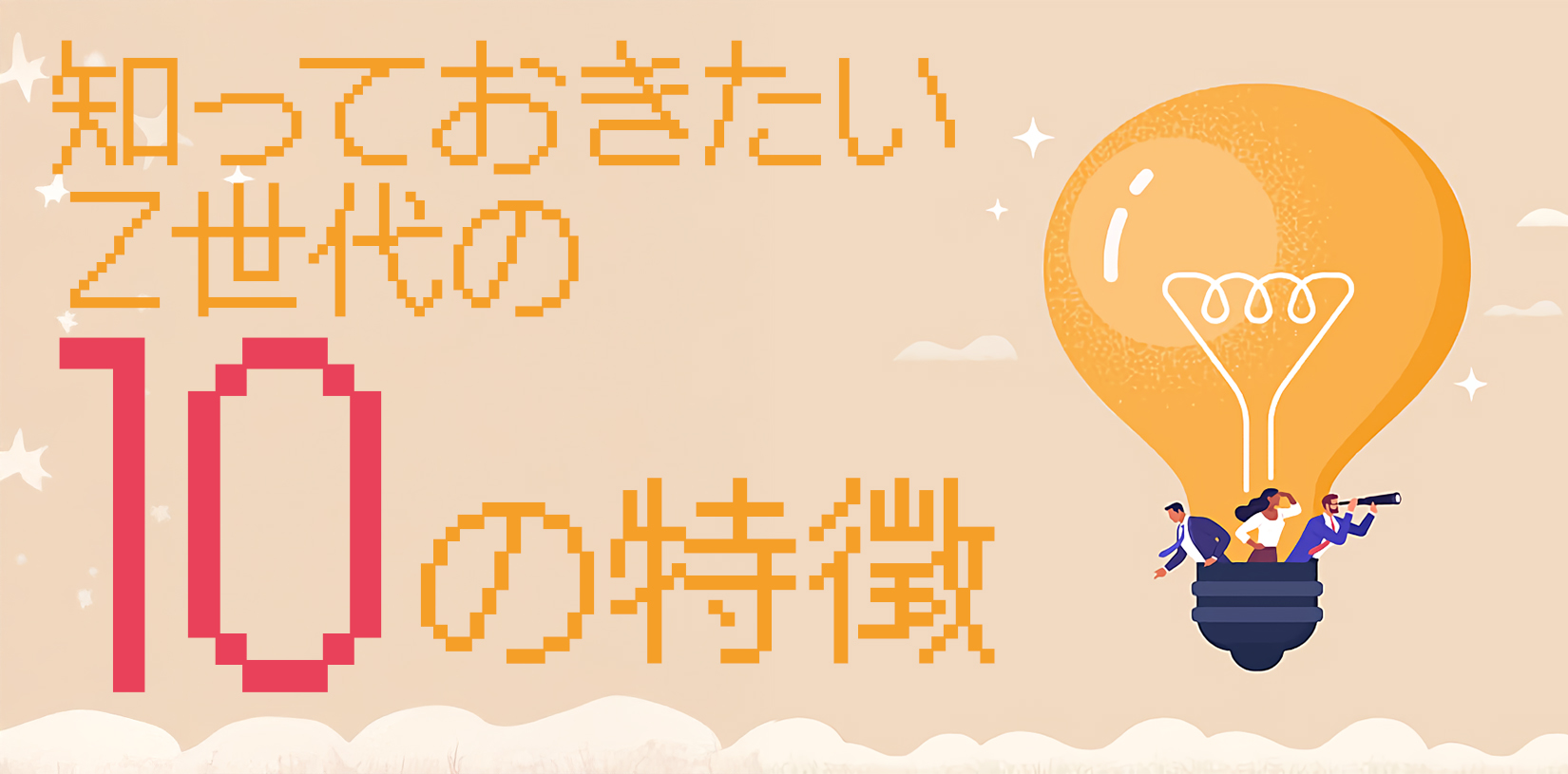
記事公開日 : 2026/02/11
最終更新日 : 2026/01/15
CONTACT