
Z世代が重視する「タイパ」とは?採用選考プロセスに取り入れるべき3つの改善点
記事公開日 : 2026/02/13
最終更新日 : 2026/01/15
記事公開日 : 2025/11/17
最終更新日 : 2026/01/15

Z世代を対象とした採用活動において、企業の魅力を伝え、自社にマッチした人材から選ばれるための「採用ブランディング」が重要性を増しています。採用ブランディングとは、自社の理念や文化、働きがいなどを一貫して発信し、求職者の中にポジティブなイメージを形成していく計画的な活動を指します。
本記事では、Z世代の価値観を踏まえ、彼らに響く採用ブランディングの進め方や具体的な施策、成功事例を解説し、効果的な採用戦略の構築を支援します。

少子化に伴う労働人口の減少と、新卒採用市場における売り手市場の加速により、Z世代の獲得競争は激しさを増しています。
デジタルネイティブであるZ世代は、就職情報サイトだけでなく、SNSや口コミなど多様な情報源から企業を多角的に評価するため、従来の採用手法だけでは優秀な人材を惹きつけることは困難です。企業の独自性や価値観を明確に伝え、共感を促す採用ブランディングが不可欠となっています。
Z世代は、企業の規模や知名度、給与といった条件面だけでなく、その企業が持つ独自の価値観やビジョン、社会に対する姿勢といった「らしさ」を強く意識します。彼らは、自分の価値観と企業の理念が一致しているか、その企業で働くことに社会的な意義や自己実現の可能性を感じられるかを重視する傾向があります。
そのため、企業は自社のパーパス(存在意義)やカルチャーを明確に定義し、それを採用活動のあらゆる場面で一貫して伝えることが求められます。企業の「らしさ」への共感が、Z世代の入社意欲を大きく左右する要因となるのです。
Z世代は、物心ついた頃からインターネットやスマートフォンが身近にあるデジタルネイティブ世代です。彼らにとって、スマートフォンは情報収集の主要なツールであり、就職活動においても企業のSNSアカウントや口コミサイト、動画コンテンツなどを日常的にチェックしています。
そのため、企業は彼らが普段利用するプラットフォーム上で、彼らの心に響くコンテンツを発信する必要があります。これは、ターゲット顧客に商品を届けるマーケティング活動と考え方が似ており、採用活動においても候補者の視点に立った情報提供や体験設計が不可欠です。
少子高齢化が進む日本において、若年層の労働人口は減少の一途をたどっています。それに伴い、新卒採用市場は学生優位の「売り手市場」が定着しており、企業は優秀な人材を確保するために厳しい競争にさらされています。
このような状況下で、企業はただ待っているだけでは求める人材を確保できません。自社の魅力を積極的に発信し、他社との違いを明確に打ち出す採用ブランディングを通じて、「この会社で働きたい」と強く思わせる努力が必要です。求職者から選ばれる存在になるための戦略的な取り組みこそが、企業の持続的な成長を支える基盤となります。
効果的な採用ブランディングを実践するためには、まず対象となるZ世代の価値観や仕事観を深く理解することが不可欠です。彼らは、それ以前の世代とは異なる社会背景の中で育ち、独自の価値基準を持っています。
これからの若者が仕事やキャリアに対して何を求め、どのような環境で働くことを望んでいるのかを把握することが、彼らの心に響くメッセージを構築する第一歩となります。この理解がなければ、企業の魅力も適切に伝わりません。
Z世代の仕事選びにおける価値観は多様化していますが、特に重視される傾向にあるのが「オープンで良好な人間関係」「自己成長とキャリアパスの明確さ」「ワークライフバランスと効率性」の3点です。
彼らは心理的安全性が高く、互いを尊重し合える職場環境を求めます。また、自身の市場価値を高めるためのスキルアップ機会や、将来のキャリアが見通せることを重視します。さらに、プライベートの時間を大切にし、仕事においてもタイムパフォーマンスを意識した効率的な働き方を好む点が特徴です。
Z世代は、オンラインでのコミュニケーションに慣れ親しんでいる一方で、職場ではオープンでフラットな人間関係を重視します。上司や同僚と気軽に意見交換ができ、互いに尊重し合える心理的安全性の高い環境を求めます。
そのため、企業選びの際には、説明会や面接での社員の対応、SNSで発信される職場の日常風景などから、リアルな社風を読み取ろうとします。企業のウェブサイトに掲載されている情報だけでなく、「どのような人たちが、どのような雰囲気の中で働いているのか」という点が、彼らにとって重要な判断材料になるのです。
終身雇用制度の崩壊を前提とするZ世代は、一つの会社に依存するのではなく、自らの専門性やスキルを高めてキャリアを切り拓いていく意識が強いです。そのため、自身の市場価値を高められるような成長機会があるかどうかを、企業選びの重要な軸としています。
具体的には、研修制度の充実度、資格取得支援、若手にも裁量権のある仕事が与えられる環境などをチェックします。また、入社後にどのようなステップでキャリアを積んでいけるのか、具体的なモデルケースやキャリアパスが示されていると、将来をイメージしやすく魅力的に映ります。
Z世代は「タイパ(タイムパフォーマンス)」を重視し、仕事においても無駄を嫌い、効率的に成果を出すことを好みます。プライベートの時間を犠牲にするような長時間労働や、旧来の非効率な慣習には強い抵抗感を示します。
そのため、フレックスタイム制度やリモートワークの導入、ITツールを活用した業務効率化など、柔軟で合理的な働き方ができる環境を高く評価します。ワークライフバランスを保ち、仕事と個人の生活を両立できるかどうかが、彼らが企業を選ぶ上で欠かせない判断基準の一つとなっています。
Z世代に向けた採用ブランディングを戦略的に行うことは、単に応募者数を増やすだけでなく、企業に多くの好影響をもたらします。自社の理念や文化に共感する人材からの応募が増え、採用の質が向上するほか、採用活動全体の効率化やコスト削減にもつながります。
ここでは、採用ブランディングがもたらす具体的な4つのメリットを解説します。
企業のビジョンやカルチャー、働きがいといった情報を一貫して発信することで、自社の価値観に共感する人材に効果的にアプローチできます。これにより、単に条件面だけで企業を選ぶのではなく、企業の理念や社風に惹かれた、自社とのマッチ度が高いターゲットからの応募が増加します。結果として、選考プロセスにおける見極めの精度が上がり、入社後の活躍が期待できる優秀な人材を確保しやすくなるでしょう。応募の「量」だけでなく、「質」の向上が期待できるのです。
採用ブランディングは、求職者だけでなく、より広い層に対して企業の魅力を伝える機会となります。SNSやオウンドメディアを通じて発信される社員の生き生きとした姿や、事業の社会貢献性に関する情報は、企業の認知度向上に直接貢献します。継続的な情報発信により、社会に対してポジティブで一貫した企業イメージを構築することが可能です。これは採用力強化に留まらず、商品やサービスのブランドイメージ向上、ひいては企業全体の価値を高めることにも結びつきます。
ブランディングが成功し、企業の魅力が求職者に広く認知されるようになると、高額な費用がかかる求人広告への依存度を下げることができます。自社のSNSや採用サイト経由での応募が増え、ダイレクトリクルーティングやリファラル採用も活性化するためです。また、自社にマッチした人材からの応募が増えることで、選考プロセスが効率化され、面接官の工数が削減されます。さらに、内定辞退率の低下も期待でき、結果として一人当たりの採用コストを大幅に抑制することが可能になります。
過程では企業の魅力的な側面だけでなく、仕事の厳しさやカルチャーのリアルな部分も正直に伝えることが重要です。これにより、候補者は入社後の働き方を具体的にイメージでき、「こんなはずではなかった」という入社後のギャップ、すなわちミスマッチを最小限に抑えられます。結果として、新入社員のエンゲージメントが高まり、早期離職率の低下につながります。人材の定着は、再採用や再教育にかかるコストと労力を削減し、組織の安定的な成長に貢献するでしょう。
Z世代に響く採用ブランディングを成功させるためには、計画的かつ段階的に施策を進めることが重要です。まずは自社が求める人材を明確に定義し、適切な情報発信チャネルを選び、候補者との双方向のコミュニケーションを設計していくという流れになります。このステップを着実に実行することで、効果的な採用活動が実現します。
採用ブランディングの最初のステップは、自社が本当に必要としている人材は誰なのかを具体的に定義することです。これを「採用ペルソナ」の設定と呼びます。単に「コミュニケーション能力が高い人」といった曖昧な条件ではなく、年齢、価値観、興味関心、キャリアへの考え方、情報収集の方法まで、一人の人物像として詳細に描き出します。
ペルソナが明確になることで、その後のメッセージの内容や発信するチャネル、コンテンツの方向性が定まり、ターゲットに的確にアプローチできるようになります。
次に、設定したペルソナに対して、自社のどのような点が魅力的に映るのかを洗い出し、言語化します。給与や福利厚生といった待遇面だけでなく、事業の社会性、独自の企業文化、社員の成長環境、働きがいなど、多角的な視点から自社の強みを分析することが重要です。
そして、洗い出した魅力の中から最も伝えたい核心的なメッセージを抽出し、採用活動全体を貫く「採用コンセプト」として策定します。このコンセプトが、今後の情報発信における一貫した軸となります。
策定した採用コンセプトを、定義したペルソナが日常的に接触するチャネルを通じて発信する必要があります。Z世代は、従来の就職情報サイトに加えて、Instagram、X(旧Twitter)、TikTok、YouTubeといったSNSや動画プラットフォームを積極的に活用して情報収集を行います。
各チャネルにはそれぞれ特性があるため、自社の伝えたいメッセージやコンテンツの形式に合わせて、最も効果的な媒体を複数選定します。チャネルの選定を誤ると、せっかくの魅力的な情報もターゲットに届きません。
選定したチャネルで発信するコンテンツは、Z世代が信頼を寄せる「リアルさ」を重視して作成します。美しく作り込まれた広告よりも、社員の日常や生の声を伝えるコンテンツの方が、彼らの心に響きます。
例えば、若手社員の一日に密着したVlog、様々な部署の社員による座談会、オフィスの様子がわかるルームツアー動画などが効果的です。飾らないありのままの姿を見せることで、候補者は働くイメージを具体的に掴むことができ、企業への親近感や信頼感を抱くようになります。
採用ブランディングは、企業からの一方的な情報発信で完結するものではありません。Z世代は、企業と対等な立場でコミュニケーションを取ることを望んでいます。SNSの投稿に寄せられたコメントや質問には丁寧に返信する、オンラインでのカジュアルな座談会を開催して社員と直接話せる機会を設けるなど、候補者との対話を重視する姿勢が求められます。企業が候補者と真摯に向き合い、関係性を構築していくプロセスそのものが、強力なブランディングとなるのです。
Z世代へのアプローチでは、彼らが日常的に利用するチャネルの特性を理解し、それぞれに最適化された施策を展開することが成功の鍵です。ビジュアル重視のInstagram、リアルタイム性が強みのX(旧Twitter)、ショート動画で注目を集めるTikTokなど、各SNSの強みを活かした情報発信が求められます。
また、それらの入り口から興味を持った候補者が、より深く企業の情報を得られる受け皿として、企業の想いや価値観を伝える採用サイトの役割も依然として重要です。
Instagramは、写真や動画といったビジュアル要素で、企業の雰囲気や世界観を直感的に伝えるのに最適なプラットフォームです。特に24時間で消えるストーリーズ機能は、加工されていないリアルな情報を発信するのに適しており、オフィスの日常風景やランチの様子、社員のオフショットなどを気軽に投稿することで親近感を醸成できます。
また、ストーリーズの質問箱やアンケート機能を活用すれば、フォロワーである学生と双方向のコミュニケーションを活発に行うことも可能です。
X(旧Twitter)の強みは、情報のリアルタイム性と拡散力にあります。説明会の告知やプレスリリースといった公式情報の発信はもちろんのこと、業界ニュースに対する社員の見解や、日々の業務での気づきなど、よりパーソナルでカジュアルな内容も発信しやすいのが特徴です。
ハッシュタグを効果的に活用して投稿のリーチを広げたり、就職活動に関する学生の投稿に「いいね」やリプライを送ったりすることで、候補者との距離を縮め、親しみやすい企業イメージを構築できます。
TikTokは、短い尺の動画でエンターテインメント性の高いコンテンツが好まれるプラットフォームです。採用活動においては、一見難しそうに見える仕事内容を1分で解説する動画や、オフィスでの「あるあるネタ」、社員の意外な特技を披露する動画など、視聴者が楽しみながら企業文化に触れられるような企画が効果を発揮します。
トレンドの音源やエフェクトを積極的に取り入れ、企業の堅いイメージを払拭し、遊び心のあるコンテンツを発信することで、潜在的な候補者層への認知拡大が期待できます。
YouTubeでは、ショート動画よりも長い尺で、より深く多角的な情報を伝えることが可能です。特に、様々な部署や経歴を持つ社員へのインタビュー動画は、候補者が最も知りたい「リアルな働き方」を伝える上で非常に有効です。仕事のやりがい、大変だった経験、入社後のキャリアパス、職場の人間関係など、社員の生の声を通じて、企業の魅力を具体的に伝えることができます。
その他、プロジェクトの裏側を追ったドキュメンタリーや、事業内容を分かりやすく解説するコンテンツも、企業理解を深めるのに役立ちます。
SNSが候補者との最初の接点や興味喚起を担う一方で、採用サイトは企業の情報を網羅し、候補者の企業理解を深めるための「本丸」としての役割を果たします。
事業内容や募集要項といった基本的な情報はもちろん、経営者のメッセージや創業ストーリー、企業理念に込められた想い、大切にしている価値観などを丁寧に伝えるコンテンツを用意することが重要です。デザインや構成にもこだわり、企業のブランドイメージを体現することで、候補者の入社意欲を最終的に高めることができます。
ここでは、実際にZ世代に向けた採用ブランディングに取り組み、成果を上げている企業の成功事例を紹介します。各社がどのような課題を持ち、ターゲットであるZ世代の心に響くためにどのような戦略や施策を実行したのかを具体的に見ていきます。
SNSの活用法、コンテンツの工夫、イベント設計など、他社の成功事例から自社の採用活動に応用できるヒントを見つけ出し、より効果的なアプローチを検討しましょう。
あるIT企業では、専門的で堅いという業界イメージを払拭するため、TikTokやInstagramリールを活用したショート動画配信に注力しました。若手エンジニアの一日の業務に密着したVlog風の動画や、複雑なプログラミングの概念をダンスで表現するユニークなコンテンツを投稿。これにより、仕事の面白さや若手が生き生きと活躍する社風を視覚的に伝え、学生からのコメントや質問が殺到するなど高いエンゲージメントを獲得しました。結果、インターンシップへの応募数が前年度の2倍に増加しました。
伝統的なメーカーであるA社は、学生に会社のリアルな姿が伝わりにくいという課題を抱えていました。そこで、採用サイトとYouTubeチャンネルを連携させ、様々な部署で働く若手からベテランまで、幅広い層の社員インタビューコンテンツを大幅に拡充しました。仕事のやりがいだけでなく、「入社後に感じたギャップ」や「最大の失敗談」といった踏み込んだテーマにも触れることで、誠実な企業姿勢をアピール。これにより、企業の価値観に深く共感した学生からの応募が増え、内定承諾率の向上に繋がりました。
急成長中のB社は、知名度の低さをカバーし、自社が求める特定のスキルを持つ学生に効率的にアプローチする必要がありました。そこで、大規模な説明会ではなく、ターゲット学生に特化したオンラインハッカソンや新規事業立案コンテストを企画。イベントを通じて、学生は事業の面白さや課題解決の醍醐味を実践的に体感し、企業側も学生のポテンシャルを直接見極めることができました。参加者との深い関係性を築き、イベント後には優秀な学生を複数名採用することに成功しています。
採用ブランディングは、進め方を誤ると期待した効果が得られないばかりか、かえって企業のイメージを損なう可能性もあります。成功事例から学ぶと同時に、よくある失敗のパターンを理解し、同じ過ちを避けることが重要です。
ここでは、採用ブランディングにおいて陥りがちな3つの失敗事例を取り上げ、その原因と対策を解説します。これらの注意点を踏まえることで、より確実で持続可能なブランディング活動を展開できます。
採用向けに「風通しが良い」「挑戦を歓迎する」といった魅力的なイメージを発信しても、実際の社内文化がそれに伴っていなければ、大きな問題を引き起こします。入社した新入社員は理想と現実のギャップに失望し、早期離職の直接的な原因となります。さらに、SNSや口コミサイトを通じて、ネガティブな情報が拡散されるリスクも高まります。
採用ブランディングは、社内の実態に基づいた等身大の姿を伝えることが大前提です。まずは、発信したいイメージにふさわしい組織文化を社内で醸成することが不可欠です。
「できるだけ多くの学生に応募してほしい」と考えるあまり、万人受けする当たり障りのないメッセージを発信してしまうケースは少なくありません。しかし、特徴のないメッセージは誰の心にも深く刺さらず、結果的にその他大勢の企業の中に埋もれてしまいます。
この失敗は、採用活動の初期段階であるペルソナ設定が不十分な場合に起こりがちです。自社が本当に求める人物像を具体的に描き、そのターゲットの価値観や興味に響くような、鋭く、的を絞ったメッセージを打ち出す勇気が必要です。
SNSアカウントを開設し、定期的にコンテンツを投稿しているだけで、採用ブランディングを行っていると満足してしまうのは危険な兆候です。Z世代は、企業からの情報を受け取るだけでなく、企業と対等な立場で対話することを望んでいます。投稿へのコメントやDMに返信しない、質問会で一方的に話し続けるなど、双方向のコミュニケーションを軽視する姿勢は、候補者のエンゲージメントを著しく低下させます。候補者一人ひとりと向き合い、丁寧に関係性を築いていく姿勢そのものが、信頼の醸成に繋がります。
Z世代の採用を成功させるためには、彼らの価値観を深く理解した上で、自社の「らしさ」を正直かつ魅力的に伝える採用ブランディングの実践が不可欠です。
本記事で解説したように、まずは求める人物像(ペルソナ)を明確に定義し、自社の魅力を言語化して採用コンセプトを策定することから始めます。その上で、InstagramやTikTokといったZ世代に有効なチャネルを選定し、リアルな企業文化が伝わるコンテンツを通じて、双方向のコミュニケーションを図ることが重要です。成功事例と失敗例を参考に自社の採用戦略を見直し、Z世代から選ばれる企業を目指しましょう。


記事公開日 : 2026/02/13
最終更新日 : 2026/01/15
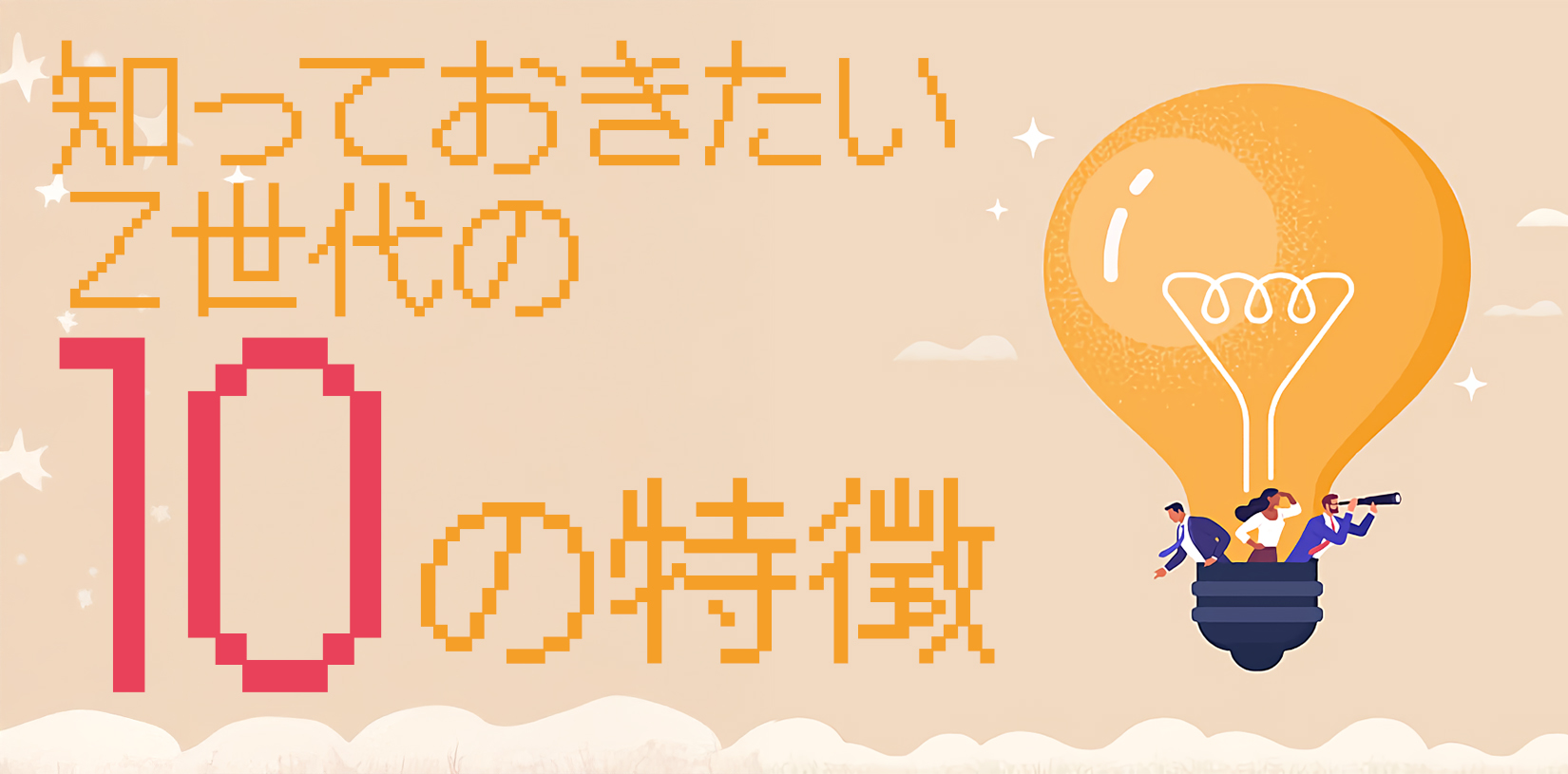
記事公開日 : 2026/02/11
最終更新日 : 2026/01/15
CONTACT