
タイパ抜群!?録画選考の活用法|Z世代に響かせるための動画面接
記事公開日 : 2026/01/29
最終更新日 : 2026/01/15
記事公開日 : 2025/10/06
最終更新日 : 2026/01/15
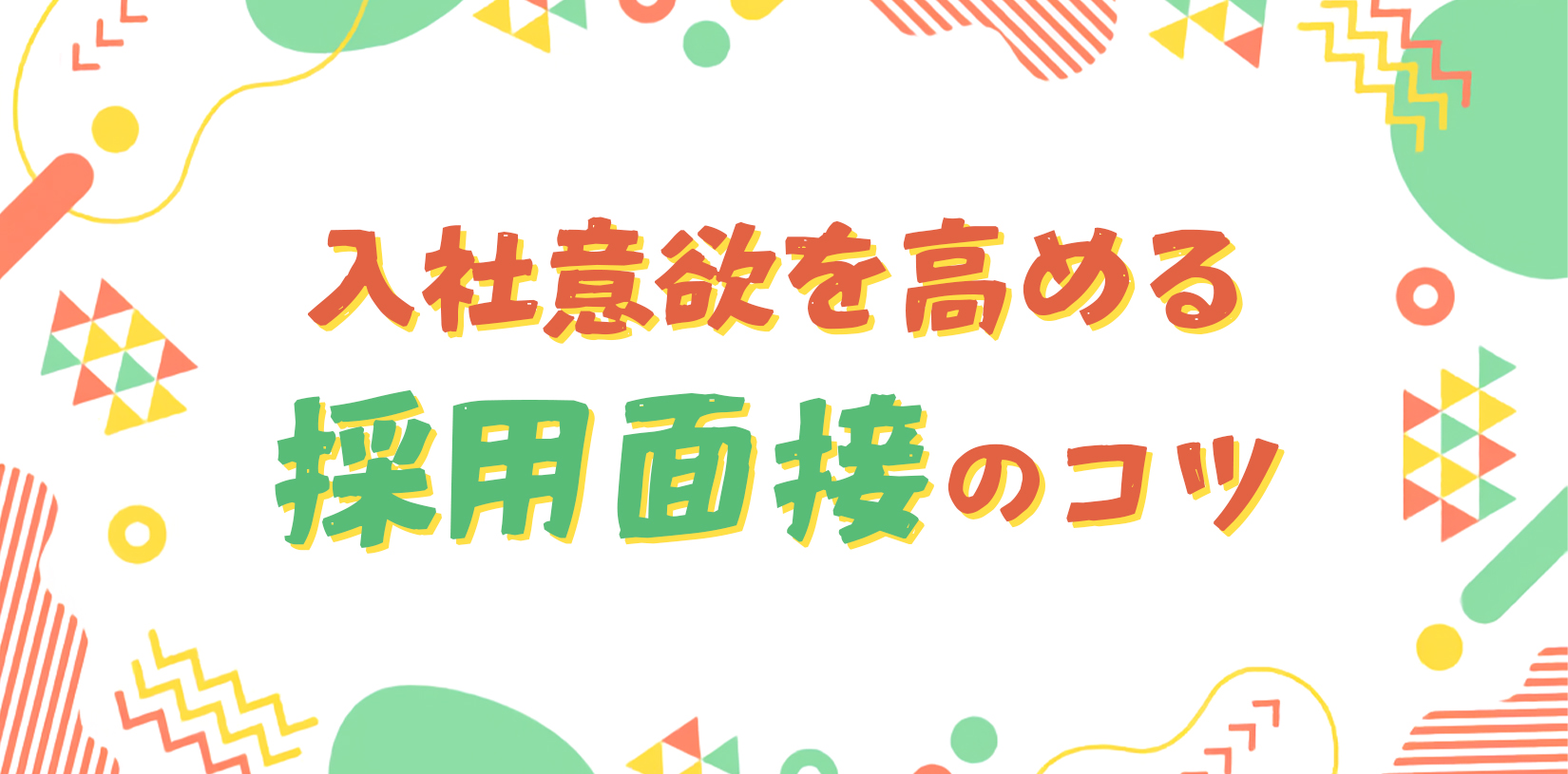
採用面接は、候補者が自社にふさわしい人材かを見極めるだけでなく、候補者に入社したいと思ってもらうための重要な機会です。優秀な人材ほど複数の企業から内定を得るため、面接を通じて候補者の入社意欲を高める工夫が、採用成功の鍵を握ります。
本記事では、候補者の入社への意欲を引き出し、内定辞退を防ぐための具体的な面接のコツや、面接後のフォローアップ方法を解説します。

優秀な人材を確保するためには、面接時に候補者の入社意欲を高めることが不可欠です。現代の就職活動では、求職者側も企業を吟味する傾向にあり、特に優秀な人材ほど複数の企業から内定を得ることが多いため、企業は選ぶ立場ではなく選ばれる立場にあると言えます。入社意欲を高めることは、内定辞退を防ぎ、採用のミスマッチを減少させる重要な要素です。「ここで働きたい」という強い気持ちを持たせることは、入社後の定着率向上やパフォーマンス発揮にも大きく影響します。
候補者の入社意欲を高めるためには、面接の進め方に工夫が必要です。面接官の印象から、対話の形式、伝える内容まで、細やかな配慮が候補者の心に響きます。
ここでは、候補者に「この会社で働きたい」と思わせるための、採用面接における5つの具体的なコツを紹介します。これらのポイントを意識することで、面接は単なる選考の場から、魅力的な企業体験の場へと変わるでしょう。
面接官は、候補者が対話する企業の顔であり、その第一印象が企業全体のイメージを大きく左右します。清潔感のある身だしなみや、明るく丁寧な挨拶、正しい言葉遣いは基本的なマナーです。候補者を尊重する姿勢を示すために、時間を守り、真摯な態度で面接に臨みましょう。
高圧的な態度や否定的な言動は、候補者の入社意欲を著しく削いでしまいます。面接官自身が企業の代表であるという自覚を持ち、候補者に良い印象を与えるよう常に心がけるべきです。
面接に臨む前に、候補者の応募書類を深く読み込んでおくことは極めて重要です。履歴書や職務経歴書に書かれている内容を把握した上で質問をすることで、候補者は「自分の経歴や志にしっかりと目を通してくれている」と感じ、企業への信頼感を抱きます。
特に、候補者がこれまでの経験で何を成し遂げ、どのようなスキルを培ってきたのかを理解し、それに基づいた質問を投げかけると良いでしょう。パーソナルな部分に関心を示すことで、候補者は心を開きやすくなります。
企業の魅力やビジョンを伝える際は、一方的な説明に終始するのではなく、対話形式で候補者の反応を見ながら進めることが大切です。候補者の関心事を引き出し、それに対して企業が提供できる価値や、候補者のスキルがどう活かせるのかを具体的に伝えることで、企業への興味を深められます。また、企業の理念や将来のビジョンを語る際には、抽象的な言葉だけでなく、具体的なプロジェクト事例や社員の成功体験を交えて説明すると、候補者はより鮮明に働くイメージを描けます。
面接では、候補者のスキルや経験を具体的に評価し、入社後に期待する役割を明確に伝えることが重要です。企業が候補者にどのような価値を求めているのか、そして候補者がその中でどのように貢献できるのかを具体的に話すことで、自身のキャリアパスをより鮮明にイメージできます。また、正直なフィードバックは、候補者に企業への信頼感を与えるとともに、自身の強みや課題を客観的に認識する機会を提供します。企業と候補者の双方向の理解を深めることが、入社後のミスマッチを防ぐことにも繋がります。
候補者の本音や潜在能力を引き出すためには、リラックスできる雰囲気作りが非常に重要です。面接の冒頭で面接官が自己紹介を行うことや、アイスブレイクとして雑談を交わすことで、候補者の緊張を和らげることができます。こうした配慮は、候補者が本来の個性や能力を十分に発揮し、企業にとっても適切な人材を見極めることにつながります。
候補者が仕事に求める価値観は多種多様です。ある候補者に響く魅力が、別の候補者には全く響かないことも少なくありません。そのため、面接での対話を通じて候補者のタイプを見極め、それぞれに合わせたアプローチを行うことが、入社意欲を高める上で非常に効果的です。
ここでは代表的な4つのタイプを取り上げ、それぞれの候補者の心に響く効果的な伝え方を解説します。
仕事を通じて成長したいという志を持つ候補者には、具体的な業務内容や、その仕事が持つ社会的な意義を伝えることが効果的です。裁量権の大きさや、チャレンジングなプロジェクトに携われる機会、スキルアップを支援する研修制度や資格取得支援制度など、自己実現につながる環境があることをアピールすると良いでしょう。
また、将来的なキャリアパスのモデルケースを示し、入社後にどのような成長曲線を描けるのかを具体的にイメージさせることが、彼らの意欲を刺激します。
生活の安定を重視する候補者に対しては、給与や賞与、昇給モデルといった待遇面について、具体的な数字やデータを用いて客観的に説明することが信頼につながります。また、住宅手当や家族手当、退職金制度といった福利厚生の詳細や、利用実績を伝えることも有効です。企業としての安定性を示すために、業績の推移や市場での立ち位置などを説明するのも良いでしょう。曖昧な表現は避け、事実に基づいた情報を提供することで、候補者は安心して将来設計を描けます。
企業の理念や価値観への共感を大切にする候補者には、ミッション・ビジョン・バリューを、具体的なエピソードを交えて語ることが響きます。どのような経緯でその理念が生まれたのか、社員が日々どのように理念を体現しているのかを伝えることで、言葉に血が通い、共感を生み出します。
また、社内の雰囲気やコミュニケーションのスタイル、評価制度など、組織文化を形成する要素を正直に話すことが重要です。入社後のミスマッチを防ぐためにも、良い面だけでなく、課題と感じている部分も誠実に伝える姿勢が求められます。
仕事と私生活の両立を重視する候補者には、具体的な働き方に関する情報を提供することが不可欠です。月間の平均残業時間、有給休暇の取得率といった客観的なデータを正直に開示しましょう。
リモートワークやフレックスタイム制度が導入されている場合は、その利用率や運用ルールについて詳しく説明することで、柔軟な働き方が可能であることを伝えられます。さらに、育児や介護と両立している社員の事例を紹介することも、候補者が自身のライフプランと照らし合わせて働く姿をイメージする助けとなります。
オンライン面接は手軽で便利な一方、対面の面接に比べて企業の雰囲気や熱意が伝わりにくいという側面があります。また、通信環境によるトラブルなど、意図せず候補者の心象を損ねてしまうリスクも潜んでいます。
ここでは、オンラインという環境の特性を踏まえ、候補者の入社意欲を高めるための3つの注意点を解説します。
オンライン面接は、対面の面接に比べて候補者の緊張感が高まりやすいという特徴があります。カメラ越しでは面接官の表情や場の雰囲気が伝わりにくいため、候補者は普段以上に身構えてしまう傾向があるからです。そこで、面接の冒頭では、意識的にアイスブレイクの時間を設けて、候補者の緊張をほぐすように努めましょう。面接官の自己紹介や、軽い雑談を交わすことで、候補者がリラックスして面接に臨めるような雰囲気作りが大切です。
オンライン面接の大きなデメリットは、オフィスの様子や社員が働く雰囲気といった、言語化しにくいリアルな情報が伝わらない点です。この課題を補うために、画面共有機能を積極的に活用しましょう。
例えば、オフィスツアーの動画や、社員が働く様子を収めた短いクリップを見せることで、候補者は企業の雰囲気を具体的にイメージでき、入社後のミスマッチを防ぐことにもつながります。言葉だけの説明よりも視覚的な情報を加えることが、企業の魅力を効果的に伝え、入社後のイメージを膨らませるのに役立ちます。
オンライン面接では、音声が途切れたり、映像が固まったりといった通信トラブルはつきものです。こうした不測の事態は、候補者に不要なストレスや不安を与えかねません。トラブルが発生した際に慌てないよう、面接の案内メールなどで、あらかじめ電話番号やチャットツールのIDといった代替の連絡手段を伝えておきましょう。
万が一の際にスムーズにリカバリーできる体制を整えていることを示すことで、企業としての丁寧さや危機管理能力をアピールでき、候補者に安心感を与えられます。
採用活動は、面接を終え、内定を出したら終わりではありません。候補者が内定を承諾し、実際に入社するまでの期間は、他社と比較検討したり、入社への不安を感じたりする「内定ブルー」に陥りやすい時期です。この期間に適切なフォローアップを行うことが、内定辞退を防ぎ、入社意欲を維持・向上させる上で極めて重要になります。
選考結果は、合否にかかわらず、約束した期日内に、できるだけ早く通知することが重要です。選考結果の連絡が遅れると、候補者は企業への関心が低いと感じ、その間に他社の選考が進んでしまう可能性があります。選考結果の通知と同時に、次の選考や面談の日程、内定後の手続きといった今後の流れを具体的に明示することで、候補者は安心して次のステップに進むことができます。
内定承諾から入社日までの期間が長い場合、候補者は不安を抱きやすくなります。そこで、人事担当者から定期的にメールを送付したり、社内報やイベント情報を共有したりして、企業との接点を維持することが重要です。また、内定者向けの懇親会や交流会を開催し、同期となる仲間や先輩社員との交流を促すことも効果的です。こうした継続的なコミュニケーションが候補者の不安を解消し、入社への期待感を高めることにつながります。
内定後の候補者の入社への意欲をさらに高めるためには、実際に現場で働く社員との面談や座談会の機会を設けることが非常に効果的です。これにより、候補者は入社後の具体的な働き方や職場の雰囲気、社員間の関係性などを直接感じることができます。
特に、配属予定部署の社員や年齢の近い先輩社員との交流は、候補者が抱える漠然とした不安を解消し、入社後のイメージをより明確にする上で役立ちます。企業側も、候補者の疑問や懸念を直接解消し、不安なく入社を迎えられるようサポートすることが重要です。
採用面接では、候補者のスキルや経験を見極めるだけでなく、企業が選ばれる立場にあることを意識し、入社意欲を高めるアプローチが重要です。面接官の印象向上から、応募書類の読み込み、企業の魅力やビジョンを対話形式で伝えること、具体的な評価と期待する役割の明示、そしてリラックスできる雰囲気作りまで、多角的な視点での工夫が求められます。
オンライン面接では、アイスブレイクの丁寧さ、会社の雰囲気が伝わる資料の活用、通信トラブル対策が特に重要です。内定辞退を防ぐためには、選考結果の迅速な通知、定期的なコミュニケーション、そして現場社員との交流機会の提供といった内定後のきめ細やかなフォローアップが不可欠です。これらの施策を通じて、候補者が安心して入社できるような体制を整えましょう。


記事公開日 : 2026/01/29
最終更新日 : 2026/01/15
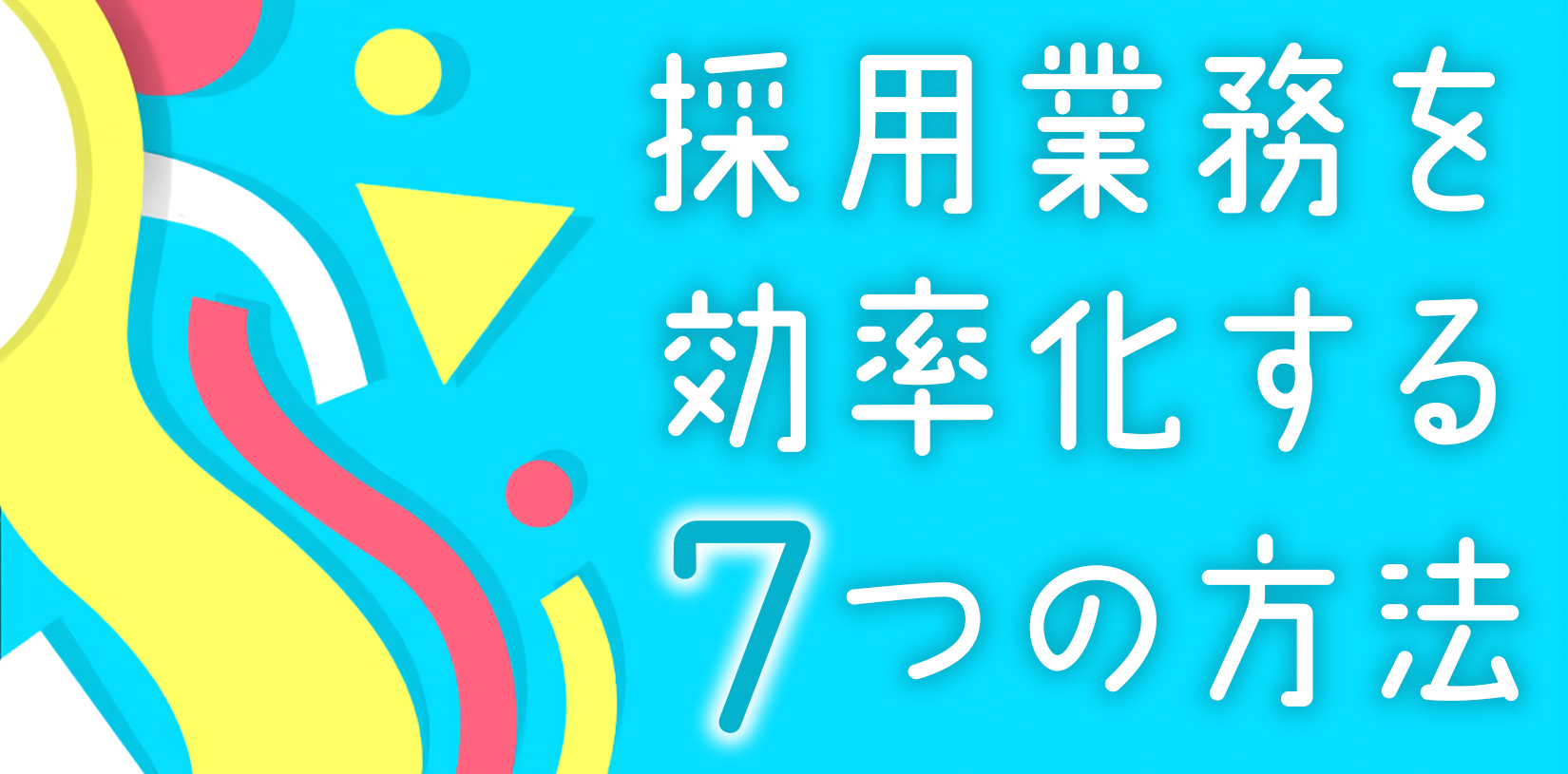
記事公開日 : 2026/01/27
最終更新日 : 2026/01/15
CONTACT