
Z世代が重視する「タイパ」とは?採用選考プロセスに取り入れるべき3つの改善点
記事公開日 : 2026/02/13
最終更新日 : 2026/01/15
記事公開日 : 2025/11/05
最終更新日 : 2026/01/15
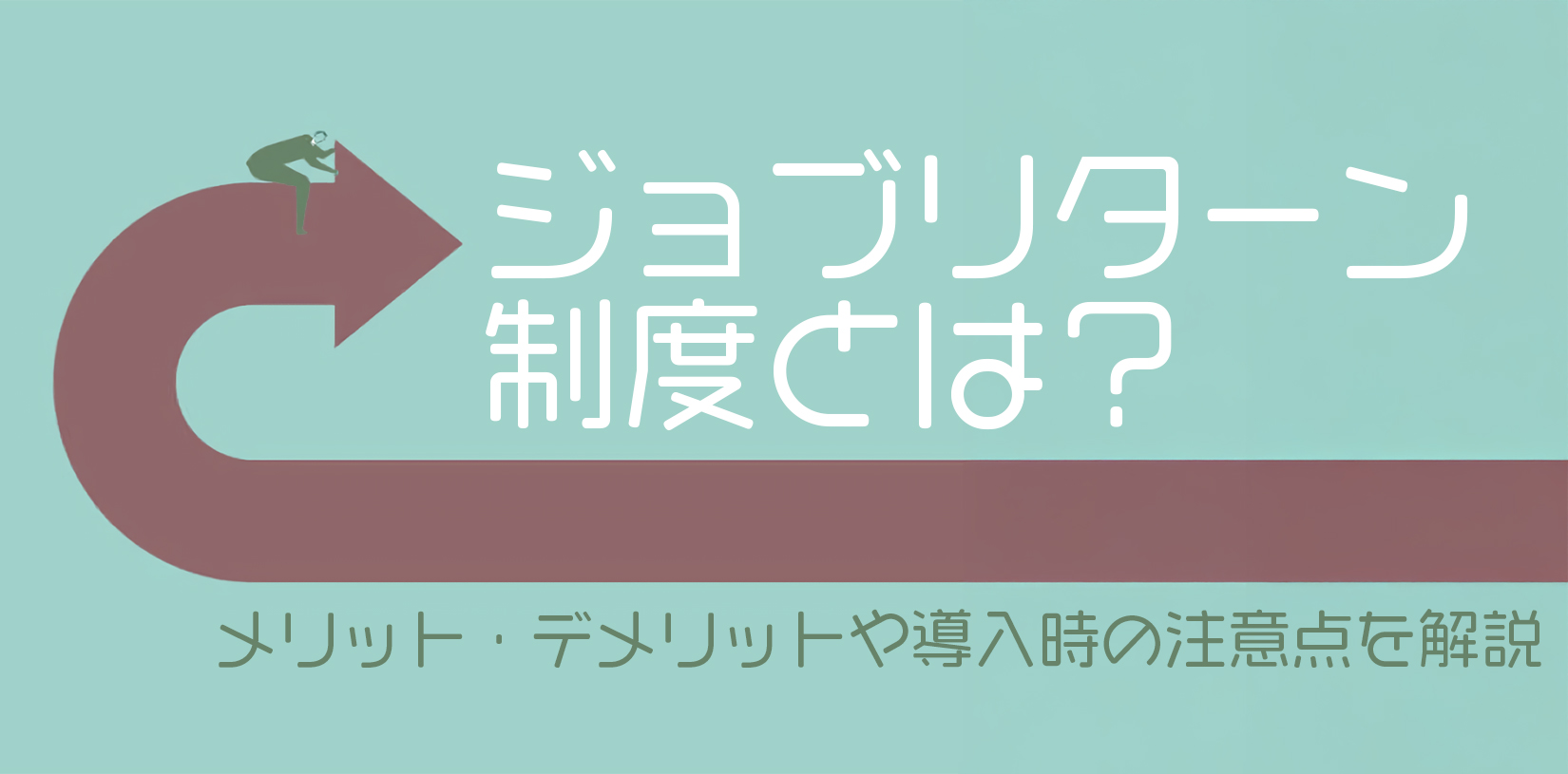
ジョブリターン制度とは、育児や介護、あるいは転職などを理由に一度退職した社員を、企業が再び雇用する仕組みのことです。人材不足が深刻化する中、即戦力となる優秀な人材を確保する有効な手段として注目を集めています。
この記事では、ジョブリターン制度の概要から、企業が導入する際のメリット・デメリット、そして制度を成功させるための運用ポイントまでを具体的に解説します。自社の人材戦略を見直す上での参考にしてください。

ジョブリターン制度とは、結婚や出産、育児、介護、配偶者の転勤といったライフイベント、あるいは転職や留学などキャリアアップを目的として退職した社員を、企業が再雇用する制度です。この制度の主な目的は、自社の事業内容や企業文化を深く理解している優秀な人材を、即戦力として再び確保することにあります。また、新規の採用活動におけるミスマッチのリスクを低減し、採用や教育にかかるコストを削減する狙いも含まれています。
ジョブリターン制度が注目される背景には、少子高齢化に伴う労働力人口の減少と、働き方の多様化があります。
終身雇用の考え方が変化し、キャリアアップなどを目的とした転職が一般的になりました。厚生労働省も多様なキャリア形成を支援しており、企業は外部からの採用だけでなく、一度自社で活躍した人材に再び目を向ける必要性が高まっています。
退職者が他社で得た新しいスキルや経験は、自社に新たな価値をもたらす可能性を秘めており、貴重な人材資源と見なされるようになりました。こうした状況から、優秀な人材を確保するための有効な戦略として、この制度が多くの企業で導入され始めています。
ジョブリターン制度とアルムナイ制度は、どちらも企業の退職者を対象とする点で共通していますが、その目的と対象範囲に明確な違いが存在します。ジョブリターン制度は、文字通り「再雇用」を主目的としており、特定の退職理由を持つ元社員が再び自社で働くことを想定した制度です。
一方、アルムナイ制度は「退職者との継続的なネットワーク構築」を目的としています。再雇用に限らず、退職者をビジネスパートナーとして協業したり、情報交換を行ったり、あるいはリファラル採用につなげたりするなど、より広範で多角的な関係性の維持を目指します。つまり、再雇用に特化しているのがジョブリターン制度、より広い関係構築を志向するのがアルムナイ制度と区別されます。
企業がジョブリターン制度を導入することには、多くのメリットが存在します。人材獲得競争が激化する現代において、この制度は有効な採用戦略の一つとなり得ます。
主なメリットとしては、採用後のミスマッチを回避しつつ即戦力を確保できる点、採用や教育に関連するコストを大幅に削減できる点、そして退職者が社外で培った新たな知見を組織に取り込める点などが挙げられます。これらのメリットは、企業の競争力強化と持続的な成長に直接的に貢献します。
ジョブリターン制度の最大の利点は、採用におけるミスマッチを大幅に低減できることです。再雇用される社員は、すでに自社の企業文化や事業内容、業務プロセス、人間関係などを深く理解しています。そのため、入社後に「思っていた環境と違った」というカルチャーフィットの問題が起こりにくいのが特徴です。また、基本的な業務知識やスキルが備わっているため、入社直後から能力を発揮する即戦力としての活躍が期待できます。
これにより、一般的な新規採用者に比べてオンボーディング期間が大幅に短縮され、受け入れ部署の負担も軽減されます。企業と元社員の双方が互いを熟知した上での再雇用となるため、高い定着率も見込めます。
新規採用の場合、求人広告の出稿費用や人材紹介会社への成功報酬など、多額の費用が発生します。ですがジョブリターン制度では、退職者との直接的な接点を通じて採用活動を進めるため、これらの採用関連費用を大幅に抑制可能です。
また、再雇用者は基本的なビジネスマナーや社内ルール、業務内容を既に習得しているため、入社後の新人研修やOJTにかかる時間と費用も大きく削減できます。採用プロセスから戦力化までの期間が短いことから、費用対効果が非常に高い採用手法で、人事部門の業務効率化にもつながります。
一度退職した社員が、他社での業務経験や留学、起業などを通じて得た新しいスキル、専門知識、そして人脈は、企業にとって非常に価値のある資産となります。自社にはない新しい視点やノウハウが組織にもたらされることで、既存の業務プロセスの見直しや業務効率化、さらには新規事業の創出といったイノベーションのきっかけになり得ます。
特に、異なる業界や職種を経験した人材であれば、組織の硬直化を防ぎ、新たな活力を与える存在となるでしょう。自社の強みと弱みを客観的に理解している元社員が持ち帰る知見は、組織を成長させる上で重要な役割を果たします。
ジョブリターン制度の導入は、社員の多様なライフプランやキャリアパスを尊重する企業姿勢を社外に示すことにつながります。ニトリをはじめとする多くの導入企業は、「社員を大切にする働きやすい会社」というポジティブな企業イメージを構築しています。
このような評判は、企業の採用ブランディングにおいて有利に働き、優秀な人材を引きつける要因となります。また、「一度辞めた社員が戻りたいと思えるほど魅力的な職場である」という事実そのものが、企業の魅力の高さを証明します。結果として、在籍している社員のエンゲージメント向上にも寄与し、組織全体の活性化が期待できます。
ジョブリターン制度は多くのメリットをもたらす一方で、導入と運用にあたってはいくつかのデメリットや注意点も存在します。制度設計を慎重に行わないと、かえって組織内に混乱や不公平感を生じさせてしまう可能性があります。
具体的には、再雇用者の処遇を巡る既存社員との軋轢、安易な離職を助長してしまうリスク、そして制度のルール設計や周知活動にかかる工数などが挙げられます。これらのデメリットを事前に理解し、対策を講じることが制度を成功させる鍵となります。
再雇用する元社員の給与や役職といった処遇の決定には、細心の注意が必要です。例えば、退職期間中の他社での経験を高く評価した結果、長年自社に貢献し続けてきた既存社員よりも優遇された条件を提示してしまうと、「なぜ一度会社を離れた人が評価されるのか」といった不公平感や不満が生じる原因となります。こうした不満は、既存社員のモチベーションを著しく低下させ、チームワークや組織の一体感を損なうことにもなりかねません。
処遇を決定する際は、退職後の経験を適正に評価しつつも、社内の給与体系や評価制度との整合性を保ち、誰もが納得できる客観的で透明性の高い基準を設けることが不可欠です。
ジョブリターン制度の存在が、「もし転職に失敗しても、また元の会社に戻れる」という一種のセーフティネットとして機能することで、社員の安易な離職を助長してしまうリスクも考えられます。本来であれば社内で解決すべき課題や不満があった際に、深く考えずに退職という選択肢を選びやすくなる可能性があります。
このリスクを回避するためには、制度の適用対象となる条件を厳格に設定することが重要です。例えば、一定の勤続年数を満たしていることや、円満退職であることなどを条件に加えることで、制度の本来の趣旨から外れた利用を防ぐ必要があります。制度が悪用されると、かえって人材の定着率を低下させることになりかねません。
ジョブリターン制度を効果的に機能させるためには、導入前の準備に相当な工数がかかります。まず、対象となる社員の条件(勤続年数、退職理由、退職後の経過期間など)や、再雇用時の選考プロセス、給与・役職といった待遇の決定基準など、詳細かつ公平なルールを設計しなければなりません。設計したルールは、就業規則や関連規程へ正式に盛り込む必要もあります。
さらに、この制度の目的や内容、利用方法について、社内報や説明会などを通じて全社員に正しく周知する活動も不可欠です。こうした制度設計と周知徹底を怠ると、制度が形骸化したり、社員間の不公平感を生んだりする原因となるため、事前の準備を丁寧に行う必要があります。
ジョブリターン制度を導入し、そのメリットを最大限に引き出すためには、戦略的な運用が不可欠です。単に制度を設けるだけでなく、それが円滑に機能し、企業と社員双方にとって有益なものとなるよう工夫を凝らす必要があります。
具体的な運用ポイントとしては、まず公平で透明性の高いルールを定めること、そして多様な働き方に対応できる環境を整備することです。再雇用時の面接プロセスを適切に設計し、社内外への周知を徹底すること、退職後も良好な関係を維持する仕組みを構築することも、制度の成功を左右します。
制度運用の根幹となるのが、明確で公平なルールの設定です。まず、制度の対象となる条件として、最低勤続年数や対象となる退職理由、申請可能な退職後の期間などを具体的に定めます。これにより、誰が制度を利用できるのかを明確にします。
次に、再雇用時の選考プロセス(書類選考、面接など)や、不採用となる場合の基準も事前に決めておくことで、恣意的な判断を排除します。特に重要なのが待遇の決定基準であり、在籍時の役職や評価、勤続年数、そして退職後の経験やスキルをどのように処遇に反映させるかを具体的に規定することが求められます。 これらのルールを就業規則などに明記し、全社員に公開することで、制度の透明性を確保し、既存社員の不満を防ぎます。
ジョブリターン制度を利用する社員には、育児や介護といった家庭の事情を抱えているケースが多く見られます。そのため、彼らが能力を最大限に発揮できるよう、柔軟な働き方をサポートする環境整備が不可欠です。具体的には、短時間勤務制度やフレックスタイム制度の導入、テレワークやリモートワークの選択肢を提供することが挙げられます。
こうした制度を整備するだけでなく、時間的な制約がある社員も気兼ねなく働けるような、職場の理解と協力的な風土を醸成することも重要です。多様な働き方に対応できる労働環境は、再雇用者だけでなく、現在在籍している全社員の働きやすさや定着率の向上にもつながり、企業全体の魅力を高めます。
優れた制度を構築しても、その存在が認知されていなければ意味がありません。社内に対しては、イントラネットや社内報、定期的な説明会などを活用し、制度の目的、対象者の条件、申請方法などを繰り返し周知することが重要です。これにより、社員は自身の将来のキャリアプランの一つとして制度を認識できます。
社外、特に退職者に向けては、企業の採用サイトや公式SNS、プレスリリースなどで制度の存在を積極的に発信します。退職者専用の連絡網などを設け、活用するのも有効な手段です。こうした広報活動は、退職者への直接的なアプローチになるだけでなく、人材を大切にする企業としてのブランディング向上にも寄与し、新規採用活動においても良い影響をもたらします。
退職者が将来的にジョブリターン制度の利用を検討するためには、退職後も企業とのつながりを感じられることが重要です。そのため、退職者との良好な関係を継続的に維持する仕組みを構築することが求められます。例えば、退職者向けのメーリングリストやSNSグループを運営し、企業の近況やイベント情報などを定期的に発信する方法があります。
また、OB・OG会のような交流イベントを企画し、元上司や同僚とコミュニケーションを取る機会を設けるのも効果的です。こうした取り組みは、再雇用の候補者リストを自然に形成するだけでなく、より広範な退職者ネットワーク(アルムナイ)の構築にもつながり、将来的なビジネス連携やリファラル採用など、多様な価値を企業にもたらす可能性があります。
ジョブリターン制度は、労働力人口が減少する現代において、企業が経験豊富で優秀な人材を確保するための有効な戦略です。この制度は、採用ミスマッチの防止や採用・教育コストの削減といった直接的なメリットに加え、社外の新たな知見を取り込み、企業イメージを向上させる効果も期待できます。
一方で、その導入と運用には、既存社員との公平性の担保や、安易な離職を助長させないための配慮も必要です。制度を成功させるには、対象者や待遇に関する明確なルールを定め、多様な働き方を許容する環境を整備し、制度の存在を社内外へ十分に周知することが不可欠です。これらの点を踏まえた上で、自社の状況に合わせた制度を設計・運用することが、持続的な組織力の強化を実現します。


記事公開日 : 2026/02/13
最終更新日 : 2026/01/15
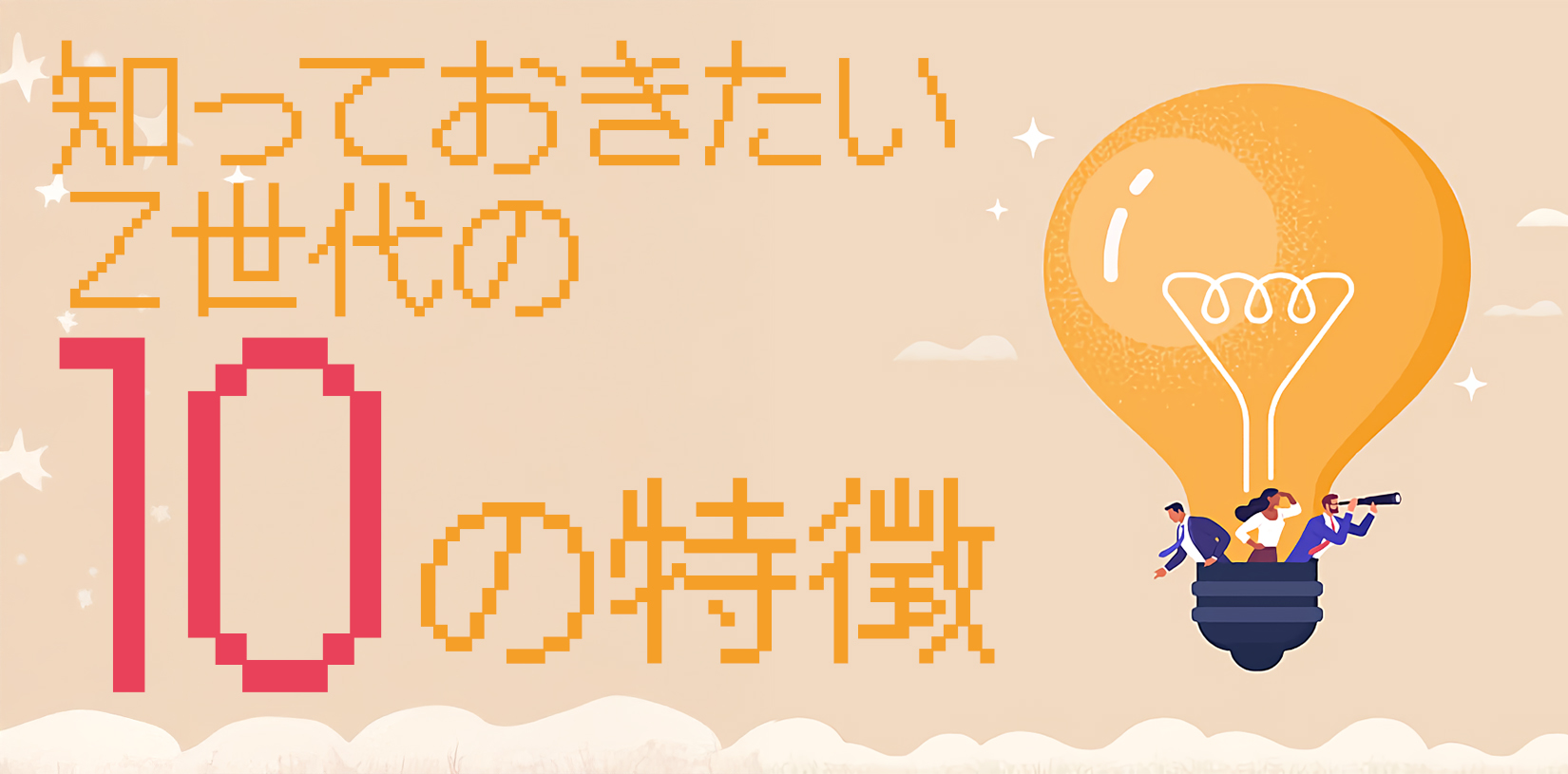
記事公開日 : 2026/02/11
最終更新日 : 2026/01/15
CONTACT