
Z世代が重視する「タイパ」とは?採用選考プロセスに取り入れるべき3つの改善点
記事公開日 : 2026/02/13
最終更新日 : 2026/01/15
記事公開日 : 2025/11/11
最終更新日 : 2026/01/15
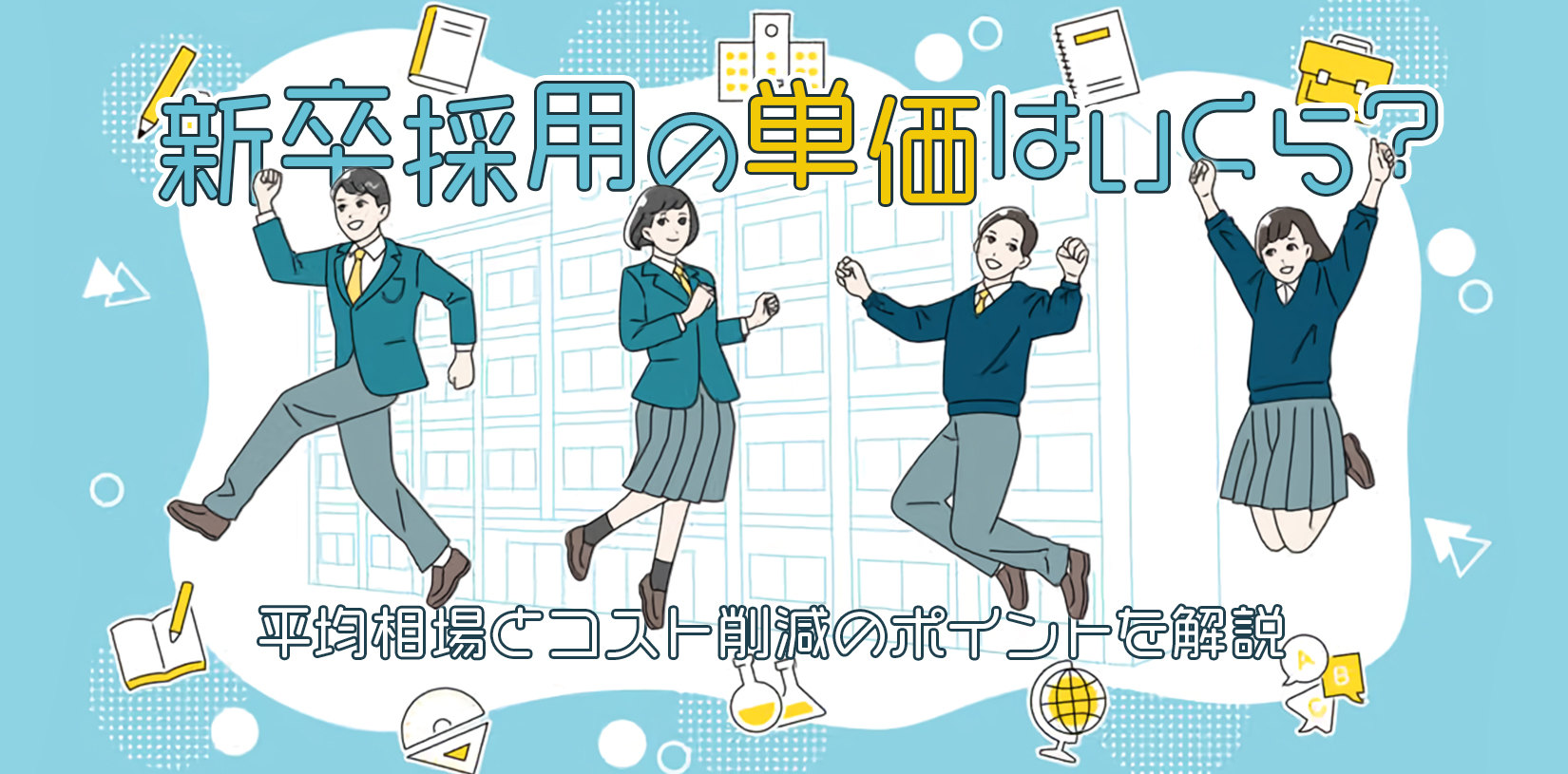
新卒採用市場の競争が激化する中で、多くの企業が採用コストの高騰という課題に直面しています。採用活動を成功させるためには、一人あたりの採用単価を正確に把握し、その内訳を理解した上で、効果的なコスト削減策を講じることが不可欠です。
この記事では、新卒採用における単価の平均相場から、具体的なコスト削減の方法、そして成功のためのポイントまでを網羅的に解説します。自社の採用活動を見直し、費用対効果を最大化するための参考にしてください。

採用コストの適正化を図る第一歩は、市場の平均単価を把握することから始まります。自社の採用コストが平均と比較してどの程度の水準にあるのかを知ることで、現状の課題が明確になり、具体的な改善策を検討しやすくなります。
近年の採用市場は売り手市場が続いており、採用手法も多様化しているため、一人あたりの採用費用は変動しやすい状況です。まずは最新のデータに基づいた平均的な金額感を掴み、自社のコスト分析の基準としましょう。
株式会社リクルートの就職みらい研究所が発表した「就職白書2023」によると、2022年度における新卒採用の1人あたりの平均採用コストは99.4万円でした。これは、求人広告費や人材紹介サービス費などの外部コストと、採用担当者の人件費といった内部コストを合計した金額です。
この調査では、前年度の72.6万円から大幅に増加しており、採用競争の激化がコストを押し上げている状況がうかがえます。企業の規模や業種、採用する職種によって単価の相場は変動しますが、この数値を一つのベンチマークとして自社のコストと比較検討することが有効です。
新卒採用の単価は、近年上昇傾向が続いています。その背景には、少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少や、学生の価値観の多様化、そして採用手法のオンライン化・複雑化など、複数の要因が絡み合っています。特に、早期化・長期化する採用活動に対応するため、企業はより多くの時間と費用を投じる必要に迫られています。
今後もこの売り手市場は続くと予測され、優秀な人材を獲得するための競争はさらに激しくなる見込みです。そのため、採用単価は高止まりするか、あるいはさらに上昇する可能性も考えられ、企業にはより戦略的なコスト管理が求められます。
採用単価を効果的に管理するためには、まずどのような費用が発生しているのか、その内訳を正確に把握することが重要です。採用コストは、大きく分けて社外のサービスや業者に支払う「外部コスト」と、社内で発生する人件費などの「内部コスト」の二種類に分類されます。
これらのコスト構造を理解することで、自社の採用活動においてどの部分に費用が集中しているのかを可視化し、具体的なコスト削減のポイントを見つけ出すことが可能になります。
外部コストとは、採用活動を目的として社外の企業やサービスに支払う費用の総称です。代表的なものとして、就職情報サイトへの求人広告掲載費、人材紹介会社へ支払う成功報酬、合同企業説明会や採用イベントへの出展料などが挙げられます。その他にも、採用管理システム(ATS)の利用料、企業の魅力を伝えるための採用パンフレットや動画の制作費、Web広告の出稿費用なども外部コストに含まれます。
これらの費用は採用手法に直結しており、採用コスト全体の中でも大きな割合を占める傾向にあります。どのチャネルにどれだけの費用を投じるかが、コスト管理の鍵となります。
内部コストは、採用活動を遂行するために社内で発生する費用のことです。最も大きな割合を占めるのが、採用担当者や面接官の人件費であり、採用活動に費やした時間をもとに算出されます。その他、応募者や内定者の交通費・宿泊費の支給、内定者懇親会や内定式といったイベントの開催費用、リファラル採用(社員紹介)で紹介者に支払うインセンティブなども内部コストに含まれます。
これらの費用は、外部への直接的な支払いではないため見落とされがちですが、採用活動全体のコストを正確に把握するためには、内部コストの算出が不可欠です。
採用単価が高騰する中で、コストを抑えつつ質の高い人材を確保することは企業にとって重要な課題です。コスト削減を実現するためには、従来のやり方を見直し、より効率的で費用対効果の高い手法を取り入れる必要があります。ここでは、明日からでも実践可能な具体的なコスト削減方法を7つ紹介します。
これらの施策を自社の状況に合わせて組み合わせることで、採用活動全体の最適化を図ることができます。単に費用を削るのではなく、賢く投資先を見極める視点が求められます。
ダイレクトリクルーティングは、企業がデータベースなどから自社の求める要件に合致する候補者を探し、直接アプローチする採用手法です。従来の求人広告のように応募を待つ「待ち」の姿勢とは異なり、企業側から能動的に働きかける「攻め」の採用活動ができます。ターゲットを絞ってアプローチするため、応募者の質が高まり、選考プロセスの効率化が期待できます。
結果として、面接官の工数削減やミスマッチの防止につながり、内部コストの抑制に貢献します。単純に比較すれば求人広告費より高額ですが、内部コストも含めると、一人あたりの採用単価を低く抑えられる可能性がある手法です。
リファラル採用は、自社の社員に知人や友人を紹介してもらう採用手法です。社員の人脈を活用するため、求人広告費や人材紹介会社への成功報酬といった外部コストを大幅に削減できる点が最大のメリットです。
紹介者である社員が、候補者に対して企業の文化や仕事内容を事前に詳しく説明するため、候補者の企業理解が深く、入社後のミスマッチが起こりにくい傾向にあります。これにより、早期離職のリスクが低減し、再募集にかかる追加コストの発生を防ぐ効果も期待できます。紹介者へのインセンティブ制度を設けても、外部サービスを利用するより費用を抑えられる場合が多いです。
自社の採用サイトやオウンドメディア、公式SNSアカウントなどを活用して、継続的に情報発信を行うことは、長期的な視点で採用コストを削減する上で非常に有効です。企業のビジョンや文化、働く社員の様子などを積極的に発信することで、求職者からの認知度と興味を高め、企業のファンを育成します。
これにより、求人広告媒体への依存度を下げることができ、広告費の削減につながります。また、自社の理念に共感した候補者からの応募が増えるため、マッチングの精度が向上し、選考の効率化や内定辞退率の低下も期待できるでしょう。
現在利用している求人媒体や採用イベントなどの各チャネルについて、定期的に費用対効果を検証することが重要です。具体的には、それぞれのチャネルから何人の応募があり、そのうち何人が選考を通過し、最終的に何人が採用に至ったのかをデータで可視化します。そして、各チャネルに投じた費用を採用決定人数で割り、チャネルごとの採用単価を算出します。
この結果を基に、費用対効果の低いサービスへの出稿を停止したり、逆に効果の高いチャネルへ予算を重点的に配分したりすることで、採用活動全体の投資効率を高め、無駄なコストを削減することが可能になります。
採用活動における内部コスト、特に人件費を削減するためには、採用プロセス全体の効率化が不可欠です。例えば、採用管理システム(ATS)を導入すれば、応募者情報の一元管理や選考進捗の自動追跡が可能になり、採用担当者の事務作業を大幅に削減できます。
また、一次面接をWeb面接に切り替えることで、候補者と面接官双方の移動時間や交通費を削減し、日程調整もスムーズに進められます。書類選考の基準を明確にしたり、面接の評価シートを標準化したりすることも、選考の迅速化と質の均一化に寄与し、結果的に工数削減につながります。
内定辞退や入社後の早期離職は、それまでに投じた採用コストを無駄にしてしまうだけでなく、欠員補充のための追加コストを発生させる大きな要因です。これを防ぐためには、採用のミスマッチを減らす取り組みが欠かせません。選考過程において、企業の魅力だけでなく、仕事の厳しさや課題といった側面も正直に伝えるRJP(現実的な仕事情報の提供)を心がけましょう。
また、インターンシップや現場社員との座談会を通じて、学生がリアルな働き方を体験し、入社後の姿を具体的にイメージできる機会を提供することも、ミスマッチの防止に非常に有効です。
企業の採用活動を支援するために、国や地方自治体が提供している助成金や補助金制度が存在します。これらの制度を積極的に活用することで、採用コストの負担を直接的に軽減することが可能です。例えば、特定の条件下で若者や女性、地方からの移住者などを正社員として雇用した場合に支給される助成金があります。
また、テレワーク導入やDX推進など、特定の取り組みに伴う人材確保を支援する補助金も考えられます。自社の所在地や採用計画が、これらの制度の対象となるかを確認し、申請要件を満たす場合は積極的に活用を検討すべきです。最新の情報は、厚生労働省や各自治体のウェブサイトで確認できます。
ただ採用コストの削減施策を実行するだけでは、かえって採用の質を低下させてしまうリスクも伴います。コスト削減を成功させるためには、目先の費用を削ることだけに囚われず、戦略的な視点を持つことが不可欠です。
採用活動は企業の将来を担う人材を確保するための重要な投資であり、その質を維持・向上させながら効率化を図る必要があります。ここでは、コスト削減の取り組みを真の成功に導くために、必ず押さえておくべき3つの基本的なポイントを解説します。
効果的な採用活動とコスト削減の土台となるのが、自社が本当に求める人物像、すなわち採用要件を明確に定義することです。必要なスキルや経験はもちろん、自社の企業文化や価値観にマッチする人柄、将来のポテンシャルなどを具体的に言語化します。
採用要件が明確であれば、ターゲットに響く求人情報の作成や、訴求力のある採用チャネルの選定が可能になります。また、選考過程においても評価基準がブレにくくなるため、面接官による評価のばらつきを防ぎ、選考の精度を高めることができます。結果として、ミスマッチによる無駄な選考工数や内定辞退を減らし、採用コストの最適化に直結します。
採用コストを削減するためには、採用活動のプロセス全体を俯瞰し、非効率な部分や無駄な工程がないか徹底的に見直す視点が求められます。例えば、書類選考の段階で時間がかかり過ぎていないか、複数の部署間での情報共有はスムーズか、面接の日程調整に煩雑な手間が発生していないかなど、各ステップを検証します。
ボトルネックとなっている工程を特定し、採用管理システムの導入や情報共有ルールの策定、選考フローの簡略化といった改善策を講じることで、採用担当者や面接官の工数を削減できます。これにより、見えにくい内部コストの圧縮を実現し、採用活動全体の生産性を向上させます。
短期的なコスト削減施策と並行して、中長期的な視点での採用ブランディング強化に取り組むことは、持続可能なコスト最適化のために極めて重要です。「この会社で働きたい」と求職者に思われるような魅力を醸成し、それを継続的に社外へ発信していく活動が採用ブランディングです。
自社の採用サイトやSNS、社員インタビューなどを通じて、事業の将来性や独自の企業文化、働く環境の魅力を伝えることで、企業の認知度と志望度を高めます。これにより、高額な求人広告に頼らなくても自然に応募者が集まる状態を構築でき、将来にわたって安定した母集団形成と採用コストの抑制が期待できます。
新卒採用の単価は上昇傾向にあり、多くの企業にとってコスト管理は重要な経営課題です。採用単価には求人広告費などの外部コストと、担当者の人件費といった内部コストがあり、その内訳を理解することが最適化の第一歩となります。
コストを抑えるためには、ダイレクトリクルーティングやリファラル採用といった能動的な手法の導入、SNSなどを活用した自社からの情報発信、採用プロセスの効率化などが有効です。これらの施策を成功させるには、自社が求める人物像を明確にし、採用活動全体の無駄をなくすとともに、長期的な視点で採用ブランディングを強化することが求められます。


記事公開日 : 2026/02/13
最終更新日 : 2026/01/15
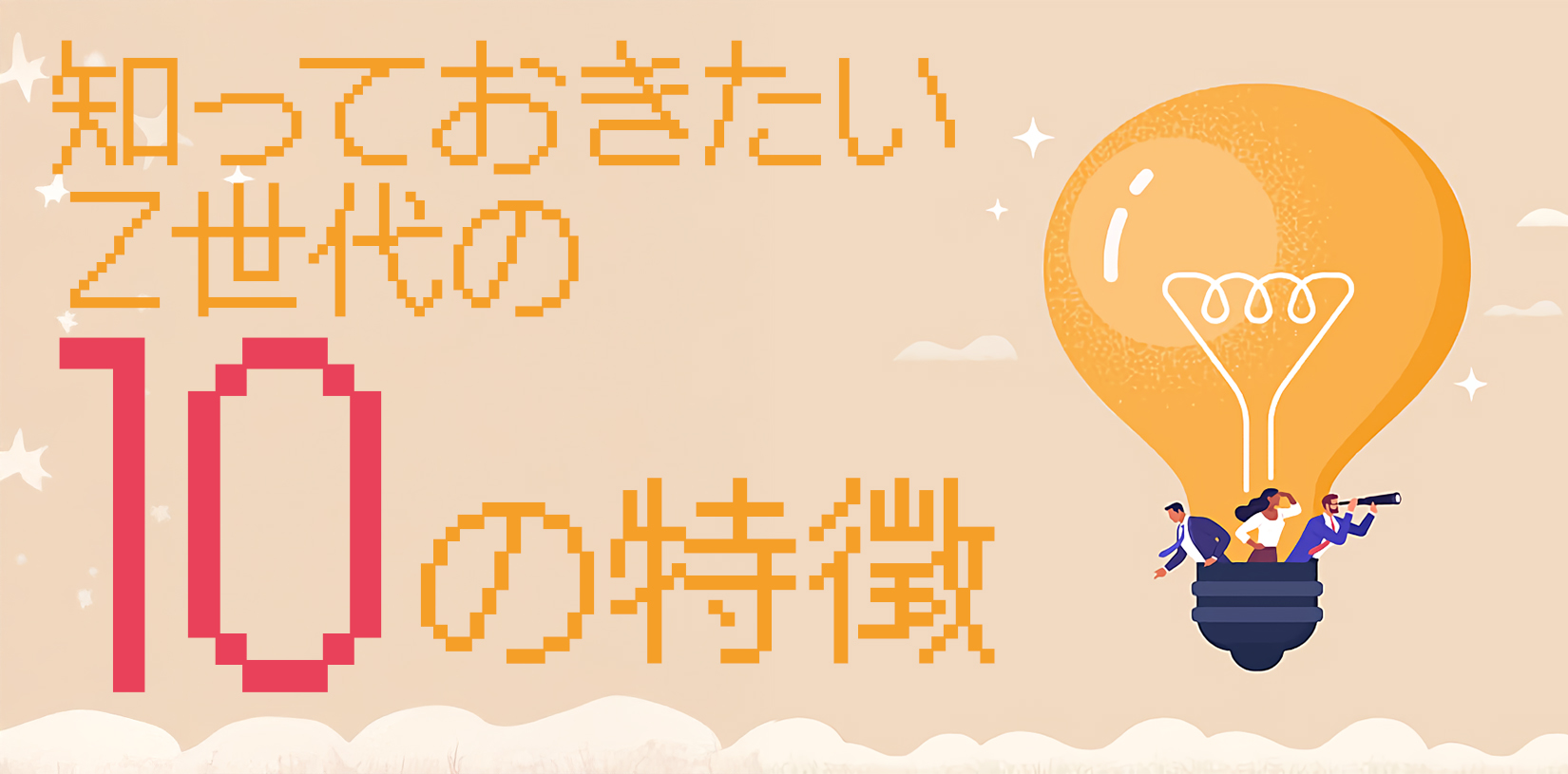
記事公開日 : 2026/02/11
最終更新日 : 2026/01/15
CONTACT