
タイパ抜群!?録画選考の活用法|Z世代に響かせるための動画面接
記事公開日 : 2026/01/29
最終更新日 : 2026/01/15
記事公開日 : 2025/05/26
最終更新日 : 2026/01/15

企業の採用担当者や経営者の皆様にとって、若い世代であるZ世代の新卒採用は重要な課題です。彼らに効果的にアプローチするためには、彼らが日常的に利用しているSNSの活用が不可欠となります。本記事では、Z世代の就活における特徴から、SNSを活用した採用活動の具体的な方法、そして成功事例までを詳しく解説し、貴社の新卒採用活動の一助となる情報を提供します。

Z世代は、1990年代後半から2010年代初頭に生まれ、デジタルネイティブとして育った若い世代を指します。インターネットやスマートフォンが当たり前の環境で育った彼らは、情報収集やコミュニケーションにおいてSNSを積極的に活用しています。また、過去の不況や社会情勢を見てきたことから、安定志向が強く、ワークライフバランスや自分らしい働き方を重視する傾向が見られます。ある調査によると、Z世代の約6割が就職活動においてSNSを活用しており、企業の情報収集に役立てていることがわかっています。
Z世代は、他の世代と比較して仕事に求める価値観に違いが見られます。彼らは単に給与が高いという理由だけでなく、ワークライフバランスの実現や、仕事を通じて自己成長できる機会があるかを重視する傾向があります。不確実性の高い社会情勢を経験しているため、安定志向が強く、終身雇用よりも自身の市場価値を高めることに関心を持つ人も少なくありません。
多様な価値観に触れて育ったことから、個性を尊重し、自分らしく働ける環境を求めます。情報収集においても、企業の公式情報だけでなく、SNSなどを通じたリアルな声や評判を参考にし、企業文化や職場の雰囲気を把握しようとします。
近年の就職活動は、売り手市場化やテクノロジーの進化、そしてZ世代といった若い世代の価値観の変化によって多様化しています。従来のナビサイト偏重の情報収集から、SNSや企業の採用ホームページ、求人サイトなど、学生が情報を得るチャネルは多様化しています。これは、デジタルネイティブであるZ世代が、自ら積極的に情報を取りに行くことに慣れていることも影響しています。ある調査によると、多くの就活生が情報収集にSNSを活用しており、特にX(旧Twitter)やInstagram、YouTubeなどが頻繁に利用されています。企業側も、従来の採用手法だけでは学生にリーチしきれないと感じており、SNSを活用した採用活動を取り入れるケースが増加しています。
新卒採用において、SNSは学生の情報収集ツールとしてだけでなく、企業が学生にアプローチし、関係性を構築するための重要な採用活動のプラットフォームとなっています。学生は企業の公式ホームページだけでは得られないリアルな情報や雰囲気をSNSから得ようとしており、企業の日常や働く人々の様子を知ることで、企業への興味や志望度を高めることがあります。企業側も、SNSを通じて自社の魅力や文化を発信することで、自社にマッチする人材との接点を増やし、効果的な採用活動を展開することが可能になります。
就活生が情報収集にSNSを活用することには多くのメリットがあります。まず、企業の最新情報やリアルタイムな動向を素早く把握できる点が挙げられます。企業の公式発表だけでなく、社員の日常の発信や会社の雰囲気を感じられる投稿から、より深い企業理解を得ることができます。また、同じ就活生やOG/OBと繋がることで、情報交換や相談ができるなど、就活における悩みを共有し、精神的な支えを得ることも可能です。さらに、企業によってはSNS上で質問会や説明会を実施することもあり、企業との双方向のコミュニケーションを通じて疑問点を解消したり、企業理解を深めたりする機会にもなります。
企業がSNSを活用して積極的に情報発信を行うことは、就活生への効果的なアプローチ手段となります。単に求人情報を掲載するだけでなく、企業の文化や働く環境、社員の生の声などを発信することで、企業の魅力を多角的に伝えることができます。
例えば、日々の業務風景や社内イベントの様子を写真や動画で共有したり、若手社員へのインタビューを掲載したりするなどの事例が見られます。これにより、就活生は働くイメージを具体的に描きやすくなり、企業への親近感や興味を持つきっかけとなります。SNSを通じたインタラクションは、一方的な情報提供に留まらず、学生からの質問に答えたり、コメントに反応したりすることで、企業と学生の間に良好な関係性を築くことも可能です。
各SNSにはそれぞれ異なる特性があり、それに合わせた発信を行うことが重要です。企業文化やターゲット層、伝えたいメッセージに応じて最適なプラットフォームを選択し、効果的な採用活動を展開するための参考に、それぞれのSNSにおける具体的な発信事例を紹介します。
Instagramは視覚的なコンテンツが中心となるため、写真や短時間の動画を活用して企業の雰囲気や社員の様子を魅力的に伝えるのに適しています。オフィス環境や社員食堂、休憩スペースなど、働く環境を紹介する写真や、社員の日常の一コマ、社内イベントの様子を捉えた動画などが有効な事例です。フィード投稿で企業のストーリーや取り組みを丁寧に伝えたり、ストーリーズやリールで短い動画を投稿し、手軽に企業のリアルな姿を見せたりすることも効果的です。
例えば、JALスカイでは客室乗務員の採用向けに、業務風景や会社の雰囲気を写真とテキストを組み合わせて発信しています。また、伊藤忠商事やアーバンリサーチなどもInstagramを採用活動に活用しており、社員紹介やイベント募集などを投稿しています。
TikTokは短い動画コンテンツが中心で、特に若年層に高いリーチ力を持つSNSです。企業の日常やユニークな取り組みをテンポの良い動画で紹介することで、親しみやすさや魅力を効果的に伝えることができます。ダンスチャレンジや流行りのBGMを取り入れた動画、社員が登場する企画動画などが事例として挙げられます。
三和交通や大京警備保障などは、社員が登場するユニークな動画で企業の雰囲気を伝え、採用に繋げています。動画制作が比較的容易であり、バズることで高い拡散力が期待できるため、企業の認知度向上にも繋がります。
X(旧Twitter)はリアルタイム性と速報性が特徴のSNSであり、最新の採用情報やイベント告知、企業のニュースなどを素早く発信するのに適しています。短いテキストに加え、画像や動画を添付することでより具体的に情報を伝えることができます。採用担当者が日常や会社の出来事についてツイートすることで、企業の「中の人」の視点からの情報を届け、親近感を持ってもらうという事例も見られます。
テレビ東京は日常の投稿でテレビ局らしさを表現し、DeNAは社員のリレー形式の発信で技術職アプローチするなど、企業の特徴を活かした事例があります。また、ハッシュタグを活用することで、関連情報に関心のあるユーザーにリーチしやすくなります。
YouTubeは長尺の動画を掲載できるため、会社説明会や社員インタビュー、オフィスツアーなど、企業の情報を網羅的に伝えるのに適しています。採用活動においては、企業のビジョンや事業内容を詳しく解説する動画、部署紹介、一日の仕事の流れを紹介する動画などが有効な事例です。社員が登場し、仕事内容ややりがい、会社の魅力などを語るインタビュー動画は、就活生にとって非常に参考になります。
ANAやJAL、東北電力グループなどはYouTubeチャンネルで採用関連の動画を発信しています。映像コンテンツを通じて企業の雰囲気や働く人の人柄を伝えることで、学生の入社意欲を高める効果が期待できます。
LINEは国内ユーザーが多く、特に若年層の利用率が高いSNSです。採用活動においては、学生との個別コミュニケーションや情報提供のツールとして活用できます。会社説明会や選考に関するリマインダーを送信したり、学生からの質問にチャットで回答したりするなど、きめ細やかなフォローアップが可能です。
LINE公式アカウントを通じて、学生が求める情報をプッシュ通知で届けたり、リッチメニューでアクセスしやすいように整理したりすることも効果的です。日本生命や日本マクドナルドなども採用活動にLINEを活用しており、円滑なコミュニケーションを図っています。
SNSを効果的に採用活動に活用するためには、単にアカウントを開設して情報を発信するだけでなく、戦略的なアプローチが必要です。各SNSの特性を理解し、ターゲットとなる就活生に響くタイミングで情報発信を行い、さらに潜在的なリスクである炎上を避けるための対策を講じることが重要となります。
SNSをマーケティングツールとして採用活動に活用する上で、各プラットフォームが持つ独自の特性を深く理解することが不可欠です。
例えば、Instagramは写真や動画といった視覚的なコンテンツに強みがあり、企業の雰囲気や社員の日常を感覚的に伝えるのに適しています。一方、X(旧Twitter)はテキストベースの情報発信やリアルタイム性が特徴で、最新の採用情報や企業に関するニュースを迅速に届けられます。TikTokは短尺動画でエンタメ性の高いコンテンツが好まれ、企業のユニークな側面や働く楽しさを表現するのに向いています。YouTubeは長尺動画で詳細な情報提供が可能であり、企業説明会や社員インタビューなどを通じて深い企業理解を促すことができます。LINEはクローズドなコミュニケーションに適しており、個別の質疑応答や面談調整などに活用できます。
それぞれのSNSのユーザー層やコンテンツの消費され方を把握し、自社の採用ターゲットに合わせたプラットフォームを選定し、最適な発信戦略を立てることが、効果的な採用活動に繋がります。
就活生に効果的に情報発信を行うためには、彼らがどのようなタイミングで情報収集を行っているかを理解することが重要です。一般的に、就活は情報収集期と意思決定期に分かれます。
Z世代の就活生は、情報収集期よりも意思決定期にSNSでの情報収集を加速させる傾向があります。選考が進み、入社の意思決定を行う段階で、企業文化や働く環境といったより具体的な情報を求めていると考えられます。そのため、企業の日常や社員の雰囲気を伝えるコンテンツは、選考期間中に積極的に発信すると効果的でしょう。また、インターンシップの募集開始時期や本選考のエントリー受付開始時期など、就活の特定のイベントに合わせて情報を発信するのも、学生の目に留まりやすくなります。
SNSでの情報発信には、意図しない形で情報が拡散し、企業のイメージを損なう「炎上」のリスクが伴います。炎上を避けるためには、発信する情報の内容に十分注意し、不適切と思われる表現や誤解を招く可能性のある内容は避ける必要があります。また、社員個人がSNSで情報発信する際にも、会社の評判に関わるような不適切な内容を含まないように、事前にガイドラインを設けるなどの対策が求められます。定期的に自社に関連するSNS上の情報を調査し、ネガティブな投稿がないかを確認することも重要です。万が一、炎上してしまった場合には、迅速かつ誠実な対応を心がけ、火消しに努めることが被害を最小限に抑える鍵となります。
⇒SNS採用の全貌が知りたい方はこちらの記事もチェック!
新卒採用市場において、多くの企業の中から就活生に選ばれるためには、魅力的な情報発信に加え、戦略的な採用活動が不可欠です。企業側の情報収集と分析を進め、応募の「量」と「質」の両方を高めるための工夫を取り入れることで、より自社にマッチした優秀な人材の採用に繋げることが可能となります。
効果的な採用活動を行うためには、企業側も積極的に情報収集と分析を行う必要があります。まず、自社の採用ターゲットとなるZ世代の学生がどのような媒体で情報収集をしているのか、どのような情報に関心があるのかを調査します。SNSの利用状況や、企業を選ぶ際に重視する点などをアンケートや座談会などを通じて把握することが有効です。また、競合他社がどのような採用マーケティングを展開しているのか、どのような情報発信が学生に響いているのかを分析することも重要です。これらの情報をもとに、自社のSNS戦略や採用コンテンツの内容を検討し、学生のニーズに合致したアプローチを計画的に実行していくことが求められます。
新卒採用において応募数を増やすことは、多様な人材と出会い、採用の選択肢を広げるために重要です。応募数を増やす手法としては、まず企業の認知度向上施策が挙げられます。SNS広告の活用や、就活生が多く利用するプラットフォームでの露出を増やすことが効果的です。また、企業の採用ホームページや求人サイトの情報を充実させ、学生が興味を持つような魅力的なコンテンツを掲載することも重要です。さらに、会社説明会やオープンキャンパスなどのイベント開催を通じて、学生との接点を増やし、企業への興味を喚起することも応募数増加に繋がります。
単に応募数を増やすだけでなく、自社にマッチした質の高い学生からの応募を増やすことも、新卒採用の成功には不可欠です。応募の質を高めるためには、ターゲット層を明確にし、その層に響くメッセージを効果的に発信することが重要です。企業の理念や求める人物像を明確に伝え、それに共感する学生からの応募を促します。また、社員インタビューや仕事内容を具体的に紹介するコンテンツを通じて、入社後の働きがいやキャリアパスをイメージしやすくすることも有効です。
SNSを活用する際には、ターゲット学生が多く利用するプラットフォームで、彼らが求めるリアルな情報や企業の雰囲気を伝えることで、興味・関心を高め、質の高い応募に繋げることが期待できます。
Z世代の就活において、SNSは情報収集や企業とのコミュニケーションに不可欠なツールとなっています。新卒採用を成功させるためには、企業もSNSの特性を理解し、効果的な発信を行うことが重要です。
各SNSに合わせたコンテンツ戦略を立て、就活生に響くタイミングで企業の魅力や働く環境を伝えることで、学生の興味を引きつけ、応募意欲を高めることができます。SNSを活用した採用活動は、企業の認知度向上や採用ブランディングにも繋がり、結果として自社にマッチした人材の採用に貢献するでしょう。


記事公開日 : 2026/01/29
最終更新日 : 2026/01/15
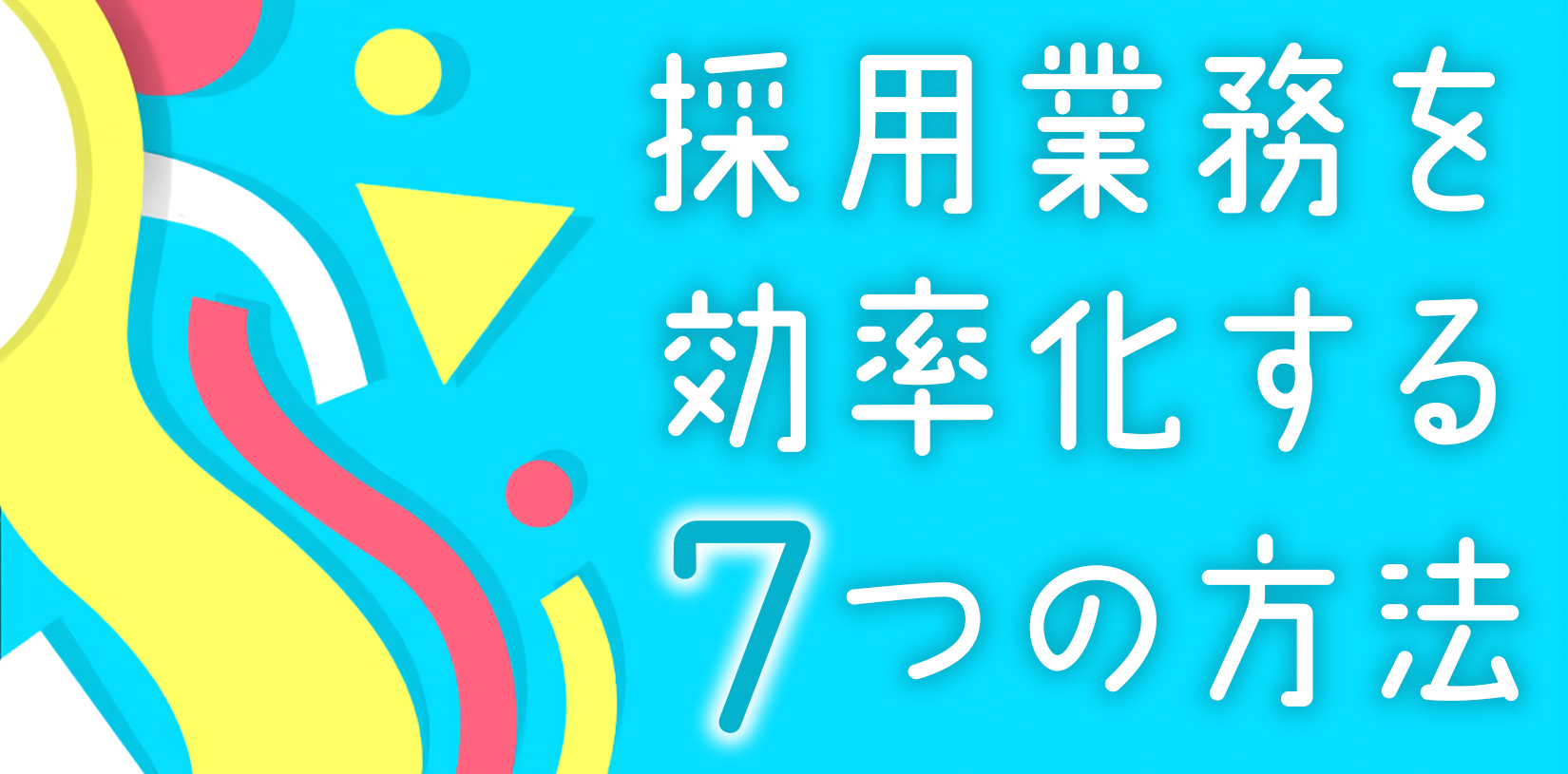
記事公開日 : 2026/01/27
最終更新日 : 2026/01/15
CONTACT