
Z世代のホンネを引き出すカジュアル面談の進め方|目的別の質問例と注意点
記事公開日 : 2025/12/16
最終更新日 : 2026/01/15
記事公開日 : 2025/08/28
最終更新日 : 2026/01/15
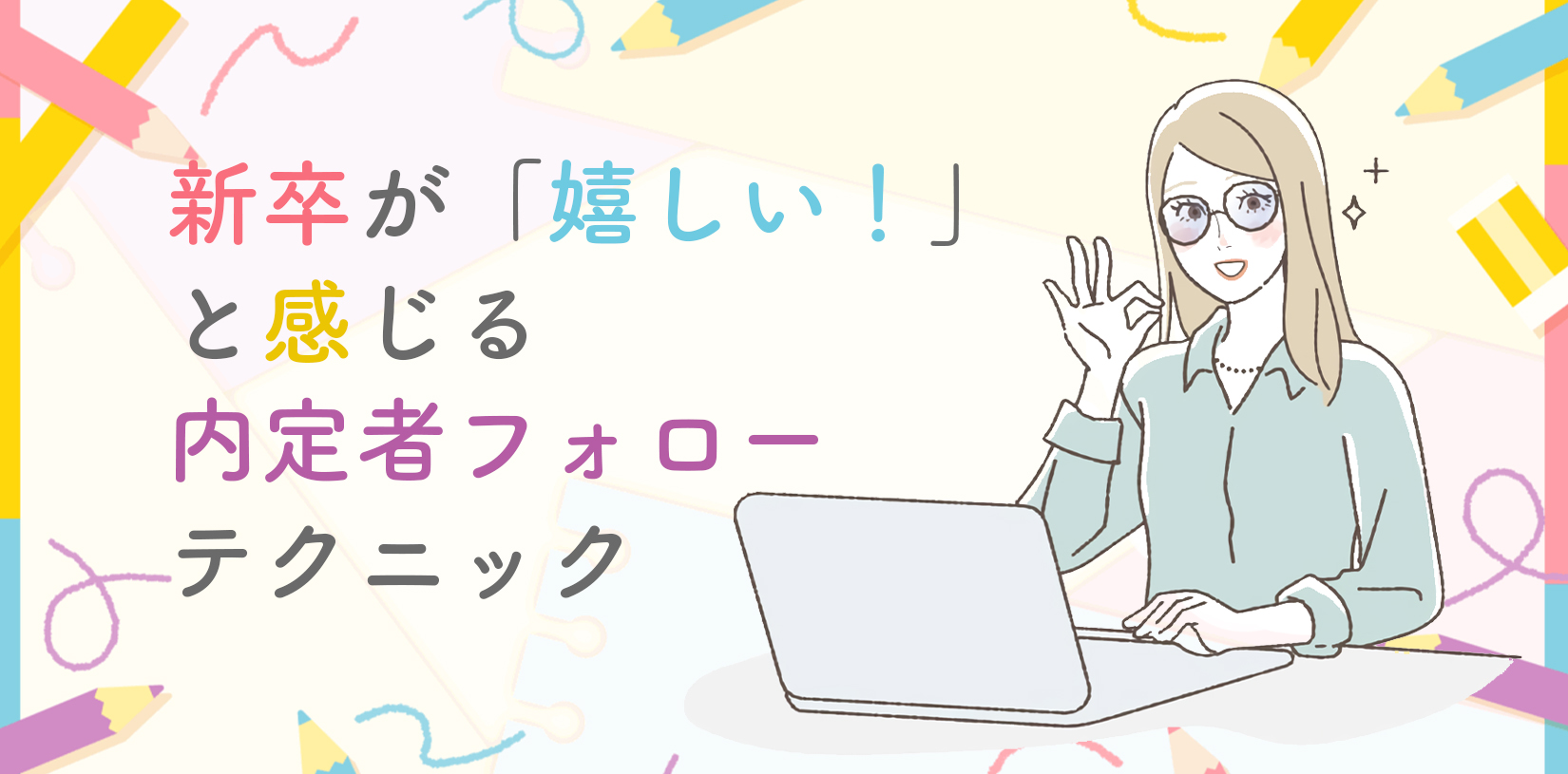
新卒採用において、内定を出した後のフォローは非常に重要です。内定後の期間は、学生が複数の企業を比較検討し、本当にこの会社で良いのかと迷いが生じやすい時期であり、内定辞退を防ぐための対策が不可欠です。
本記事では、新卒の内定者が嬉しいと感じる効果的なフォロー方法を、具体的な事例を交えながらご紹介します。内定辞退を未然に防ぎ、入社後の活躍を支援するためのヒントを見つけていきましょう。

近年、新卒採用市場は「売り手市場」と呼ばれ、優秀な学生ほど複数の企業から内定を獲得する傾向にあります。そのため、企業側は内定を出したからといって安心してはいられません。内定後から入社までの期間が半年以上と長期化する中で、学生の企業への興味や期待が薄れる可能性があり、内定辞退を防ぐための内定者フォローがますます重要になっています。
内定者フォローは、内定者の不安を解消し、企業への期待感を高めることで、内定辞退の防止だけでなく、入社後の早期離職を防ぎ、スムーズな入社準備を促す目的があります。採用には多大なコストと時間がかかるため、内定辞退や早期離職は企業にとって大きな損失となるからです。
内定者は、内定後から入社までの期間に様々な不安を抱えることがあります。これらの不安を解消することが、内定辞退を防ぐための重要な鍵となります。主な不安として、以下の5つが挙げられます。
内定後、内定者は「この会社の雰囲気やカルチャーは自分に合っているのか」という不安を抱くことがあります。特に、企業理念や価値観が社風に反映されているかどうかは、多くの内定者にとって気になる点です。この不安を解消するためには、会社見学やインターンシップを通じて、自社の雰囲気や社員の働く様子を実際に体験してもらう機会を設けることが有効です。
新しい環境で働くにあたり、内定者は「同期や先輩社員と良好な人間関係を築けるだろうか」という不安を抱くことがあります。特に、新卒の場合は初めての社会人経験となるため、人間関係への不安はより顕著です。内定後、内定者懇親会や座談会、社内イベントへの参加を促すことで、内定者同士や社員との交流機会を創出し、人間関係への不安を払拭することができます。
内定者は、内定後、入社後の業務で自分のスキルや知識が通用するかどうかについて自信を持てないことがあります。特に、「会社からの期待に応えられるか」「成長していけるか」といった漠然とした不安を感じる学生も少なくありません。内定者インターンシップや学習支援、ビジネスマナー研修などを提供することで、入社前に必要なスキルや知識を習得する機会を設け、内定者の自信を高めることができます。
内定者は、内定後に「本当にこの会社を選んで正しかったのか」という迷いを抱えることがあります。これは、就職活動における選択への不安であり、他社との比較や親や友人からの意見によって増幅されることもあります。この不安を解消するためには、企業側から継続的に会社の魅力を伝え、入社後のキャリアパスや働き方を具体的に提示することが重要です。
内定後、企業からの連絡が途絶えると、内定者は「放置されている」と感じ、不安を増幅させることがあります。定期的な連絡やコミュニケーションがないと、企業に対する不信感が芽生え、内定辞退につながる可能性が高まります。内定後も、適切な頻度で連絡を取り、会社の最新情報や入社準備に関する案内を共有することで、内定者の不安を軽減し、安心感を与えることができます。
内定者が「嬉しかった!」と感じるフォローは、入社に対する不安を払拭し、企業への期待感を高める上で非常に重要です。ここでは、具体的なイベント事例を交えながら7つのフォローをご紹介します。
内定者にとって、実際に働く先輩社員との交流は、入社後の具体的なイメージを掴む上で非常に有益です。座談会などのイベントを通じて、先輩社員から仕事のやりがいや会社の雰囲気、リアルな働き方を聞くことで、入社への不安が解消され、モチベーションが向上します。特に、さまざまな部署の社員と話す機会を設けることで、新たな気づきが得られやすくなります。
例えば、若手社員からは入社後のキャリアパスや研修制度について、中堅社員からは仕事の難しさや面白さ、ベテラン社員からは会社の歴史や将来性について話を聞くことができ、多角的に企業を理解できます。質疑応答の時間を設けることで、内定者が抱えている具体的な疑問を解消できるだけでなく、社員との距離が縮まり、入社への期待感が高まるでしょう。このような交流は、内定者が企業文化に触れ、自分がその一員となるイメージを具体的に描く上で不可欠です。
オンライン懇親会は、内定者同士が互いに知り合い、入社前の不安を解消する上で非常に有効なイベントです。特に、遠方に住む内定者にとっては、会場に足を運ぶことなく気軽に参加できるため、参加のハードルが低いというメリットがあります。
このイベントでは、ただ顔を合わせるだけでなく、オンライン上でも楽しめるゲームやグループワークを企画することで、自然な形で内定者間の親睦を深められます。例えば、共通の趣味や関心事を持つグループに分かれてディスカッションをしたり、チーム対抗のクイズ大会を実施したりすることで、会話が生まれやすくなります。
最初は互いに遠慮があるかもしれませんが、企業側がアイスブレイクのきっかけを用意し、積極的に交流を促すことで、内定者同士の距離がぐっと縮まります。このようなオンライン懇親会は、入社後の同期との関係性を円滑にするだけでなく、入社へのモチベーションを高める重要な機会となるでしょう。
内定者が抱える不安や疑問を個別に解消するためには、人事担当者との定期的な面談が有効です。内定者にとっては、選考中から関わってきた人事担当者が最も身近な存在であり、他の社員には話しにくい内容も相談しやすい傾向があります。面談を通じて、内定者の状況を丁寧にヒアリングし、不安を払拭することで、企業への信頼感を高めることができます。例えば、入社前の学習に関する悩みや、配属先への不安など、具体的に抱えている疑問について、人事担当者が親身になって相談に乗ることで、内定者は「この会社は自分を大切にしてくれている」と感じることができます。
また、面談では、入社後のキャリアパスや研修制度について具体的な情報を提供することも重要です。これにより、内定者は入社後の自分の姿を具体的にイメージしやすくなり、目標設定にも役立ちます。さらに、面談の回数を重ねることで、人事担当者と内定者の間に信頼関係が構築され、入社後の良好な関係性にもつながります。人事担当者が、内定者一人ひとりの個性や状況を理解し、個別のアドバイスを提供することで、内定者はより安心して入社準備を進めることができるでしょう。このような個別かつ継続的なフォローは、内定辞退を防ぐだけでなく、入社後の定着率向上にも寄与します。
社内報やSNSを活用した情報発信は、内定者が会社のリアルな姿を知る上で有効です。社内報の送付や社員ブログ、SNSでの情報発信を通じて、会社の理念や事業内容、日々の様子を伝えることで、内定者の企業理解を深められます。特に、社内イベントの様子や社員の働き方を発信することで、より具体的に会社の雰囲気を感じてもらうことができます。
例えば、社員が日々の業務で奮闘している姿や、社内レクリエーションで楽しんでいる様子を写真や動画で共有することで、内定者は入社後の自分の姿をより鮮明にイメージできます。また、SNSを活用することで、タイムリーな情報を発信でき、内定者は企業と常に繋がっていると感じることができます。社員のインタビュー記事を掲載したり、職場のオフショットを公開したりすることも、内定者にとっては興味深く、企業のオープンな姿勢を感じるきっかけとなります。これにより、入社前の不安が軽減され、企業への親近感や期待感が高まるでしょう。
入社後に必要となるスキルや知識を習得したいと考える内定者に対して、資格取得や書籍購入の費用をサポートすることは、入社への意欲向上につながる有効なフォローです。例えば、業務に必要なIT系の資格や、語学力を高めるためのTOEIC®などの検定費用を企業が一部または全額負担することで、内定者は入社前から自身のスキルアップに積極的に取り組めます。
また、ビジネススキルや業界知識に関する書籍の購入費用を補助することも、内定者の自律的な学習を促し、入社へのモチベーションを高めることにつながります。通信教育やeラーニングのプログラムを提供することも有効であり、内定者自身が学びたい分野を選択できるため、高いモチベーションで学習を継続できます。
特に、入社までに身につけておくと良いスキルや知識について具体的に提示し、その習得をサポートすることで、内定者は入社までに自信をつけ、スムーズなスタートを切る準備ができます。このような費用サポートは、企業が内定者の成長を支援する姿勢を示すことになり、内定者エンゲージメントの向上にも寄与します。
内定者一人ひとりに対するパーソナルな連絡は、「自分のことを歓迎してくれている」という気持ちを内定者に抱かせ、企業への帰属意識を高めます。メールやLINEなどの身近なツールを活用し、カジュアルに連絡を取り合うことで、内定者側も小さな不安をすぐに解消できるようになります。
例えば、内定者の興味や関心に合わせて、関連するイベント情報や業界のニュースを送る、あるいは内定者との会話で触れた個人的な話題(例:趣味、出身地など)に触れたメッセージを送るなどが考えられます。これにより、企業が内定者一人ひとりに目を向け、大切にしているというメッセージが伝わります。
また、定期的な連絡は、内定者の安心感や信頼感を増す上で非常に効果的です。単なる事務的な連絡だけでなく、例えば「最近、学業はどうですか?」「何か困っていることはありませんか?」といった、内定者の状況を気遣う一言を添えることで、よりパーソナルな印象を与えられます。内定者が気軽に返信できるよう、返信を強要しない配慮も大切です。このようなきめ細やかな連絡は、内定者が企業との距離を近く感じ、入社への期待感を高めることにつながります。
企業の良い面だけでなく、課題やデメリットも包み隠さず正直に伝えることは、内定者からの信頼を得る上で非常に重要です。入社前にリアリティのある情報を共有することで、入社後のギャップを減らし、早期離職の防止につながります。
例えば、特定の事業における課題や、現在の組織体制における改善点などを具体的に共有することで、内定者は「この会社は透明性が高く、信頼できる」と感じるでしょう。また、働き方改革における課題や、将来的な事業展開の難しさなども正直に伝えることで、内定者はより深く企業を理解し、自身のキャリアプランと照らし合わせて考えることができます。
メンター制度を導入し、先輩社員から具体的な業務内容や社内の実情を聞く機会を設けることも有効です。先輩社員が自身の経験に基づいて、仕事のやりがいだけでなく、苦労話や解決策を共有することで、内定者は入社後の「こんなはずではなかった」というミスマッチを防ぎやすくなります。さらに、入社後のキャリアパスについても、単なる理想論だけでなく、実際に経験するであろう困難や成長の過程を具体的に提示することで、内定者は自身の成長をより具体的にイメージし、企業への信頼感を深めることができるでしょう。
内定者フォローにおいて、他社との差別化を図り、内定者の心に残るユニークなアイデアを取り入れることは非常に有効です。ここでは、内定者が主体的に参加できるような施策を中心に3つのアイデアをご紹介します。これらのアイデアは、内定者のエンゲージメントを高め、入社への期待感をさらに高めることが期待できます。
内定者自身に翌年の採用パンフレットやサイト制作、社内報の企画・運営といったプロジェクトを任せることは、内定者の主体性を引き出し、企業への理解を深める非常にユニークなイベントです。例えば、内定者だけでチームを組み、新規事業の提案を考えるグループワークを実施することも、企業理解を深める良い機会となります。
このようなプロジェクトは、内定者が自ら企画・運営に携わることで、より高いモチベーションで取り組むことが期待できます。実際に、内定者が自主的にイベントを企画・実行する企業事例では、内定者同士の連帯感が強まり、入社後のスムーズな人間関係構築にも繋がったという報告もあります。
これは、単に企業が用意したプログラムに参加するだけでなく、内定者自身が「自分たちの手で何かを創り上げる」という経験を通じて、企業への愛着や貢献意欲を高める効果があるためです。さらに、企画を通じて得られた内定者視点のアイデアは、今後の採用活動や社内コミュニケーションの改善にも役立てられるため、企業にとっても大きなメリットとなります。プロジェクトのテーマは、採用活動の改善提案や、自社商品のプロモーション企画、社内イベントの立案など、企業の事業内容や文化に合わせて多岐にわたります。企業は内定者に対し、プロジェクトの目的や期待するアウトプットを明確に伝え、必要なサポート体制を整えることが重要です。
内定者に企業オリジナルのグッズをプレゼントすることは、特別感を演出し、企業への愛着を育むユニークなフォローの一つです。内定式でオリジナルの内定証を渡したり、企業ロゴの入ったノートを贈ったりする企業もあります。実用的なものやデザイン性の高いものなど、内定者が普段使いできるようなグッズを選ぶと喜ばれやすいでしょう。
例えば、社名入りの文房具やタンブラー、スマートフォンケースなどが考えられます。 特に、ビジネスシーンで使える名刺入れやボールペン、キーケース、ハンカチなどは、内定が決まってから入社までの早い時期に贈ると喜ばれる傾向があります。 これらのアイテムは、学生から社会人になる節目に役立つだけでなく、企業側が内定者を歓迎し、今後の活躍を期待しているというメッセージを伝えることにも繋がります。
プレゼントを選ぶ際は、日常的に使用できるよう、名入れや企業ロゴは目立たせすぎず、ワンポイント程度にすることで、センスの良い記念品となります。 また、価格帯も考慮しつつ、実用性が高く、品質の良いアイテムを選ぶことが重要です。 例えば、シンプルでスタイリッシュなデザインのボールペンや、保温・保冷機能のあるスリムなステンレスボトルなどが挙げられます。 このようなプレゼントは、内定者の企業への帰属意識を高めるきっかけにもなり、入社へのモチベーション向上に繋がるでしょう。
先輩社員の1日の仕事の流れを密着取材した動画コンテンツは、内定者が入社後の働き方を具体的にイメージする上で非常に役立ちます。求人情報だけでは伝わりにくいリアルな業務内容や職場の雰囲気を視覚的に伝えることで、内定者の不安を解消し、入社意欲を高めることができます。例えば、営業職の先輩社員であれば、朝の出社から顧客訪問、社内での打ち合わせ、資料作成、退社までの一連の流れを撮影し、ナレーションやテロップで具体的な業務内容を解説すると良いでしょう。特定の職種や部署に特化した動画を作成することで、より具体的なイメージを持ってもらうことも可能です。
さらに、社員が実際に使用しているツールやシステム、オフィスのレイアウトなども盛り込むと、内定者は入社後の自分の姿をより鮮明に想像できます。休憩時間の過ごし方や、社員同士のコミュニケーションの様子など、会社生活の「リアル」を垣間見せることで、会社の雰囲気やカルチャーへの理解も深まります。動画の最後には、密着取材された先輩社員から内定者へのメッセージを添えることで、親近感や安心感を高める効果も期待できます。これにより、内定者は入社後の「こんなはずではなかった」というミスマッチを減らし、スムーズな入社準備につながります。
内定者フォローを成功させるためには、内定者の心理を理解し、適切なタイミングと方法でアプローチすることが重要です。ここでは、そのための3つのコツをご紹介します。
内定者フォローを成功させるためには、内定者が抱える不安や疑問に寄り添ったコミュニケーションを心がけることが最も重要です。内定者の気持ちを理解し、共感する姿勢を示すことで、安心感や信頼感が生まれます。特に、内定者からの質問には迅速かつ丁寧に回答し、気軽に相談できる環境を整えることが大切です。
例えば、LINEやチャットツールを活用し、日常的にコミュニケーションを取ることも有効です。また、内定者が不安を感じる可能性のあること、例えば配属先や研修内容などについて、企業側から積極的に情報提供を行うことも、安心感を与える上で重要です。内定者一人ひとりの個性や状況に合わせた柔軟な対応を心がけることで、「自分を大切にしてくれている」という気持ちを抱かせ、企業への愛着を深めることができるでしょう。
内定者との接点を定期的に持つことは、内定辞退を防ぐ上で不可欠な要素です。月に1回といった適切な頻度で定期的に連絡を取ることで、内定者は企業に気にかけてもらっていると感じ、安心感を抱きます。これにより、企業への信頼感とエンゲージメントが向上します。連絡内容としては、会社の最新情報や入社準備に関する案内、あるいは内定者のちょっとした近況確認などが考えられます。例えば、新事業の立ち上げや社内イベントの開催情報、入社までに準備しておくことなどを共有すると、内定者は企業との繋がりを感じられます。
連絡が途絶えると、内定者は「放置されている」と感じ、不安を増幅させてしまう可能性があるため、継続的なコミュニケーションを意識することが重要です。特に、就職活動を終えたばかりの時期は、複数の選択肢と比較検討する中で、企業からの連絡が途絶えることで漠然とした不安を抱きやすくなります。定期的な連絡を通じて、企業が内定者を大切にしているというメッセージを伝えることで、内定者のモチベーションを維持し、入社への意欲を高めることができるでしょう。
オンラインとオフラインの施策を組み合わせることは、内定者フォローにおいて非常に効果的です。特に、遠隔地に住む内定者や学業で忙しい内定者にとって、オンラインでのコミュニケーションは手軽で参加しやすいため、情報提供や進捗確認、質問対応などに活用すると良いでしょう。例えば、定期的なオンライン説明会や個別面談、チャットツールでの情報共有などが挙げられます。
一方で、企業文化への理解を深め、内定者同士や社員との一体感を醸成するためには、対面での交流が不可欠です。懇親会や座談会、オフィス見学、内定式などのオフラインイベントは、実際に会社の雰囲気を肌で感じ、顔を合わせてコミュニケーションを取ることで、オンラインでは得られない安心感や信頼感を築くことができます。オンラインとオフラインそれぞれの利点を活かし、内定者の状況やニーズに合わせて柔軟に組み合わせることで、よりきめ細やかで効果的なフォローが実現できます。
内定者フォローは、やり方を間違えると逆効果になり、内定者の志望度を下げてしまう可能性があります。ここでは、内定者ががっかりしたと感じるNGフォローの事例をご紹介します。内定辞退を避けるためにも、これらの点に注意しましょう。
内定後、企業側からプライベートに過度に踏み込む質問をされると、内定者は不快に感じ、企業への不信感を抱くことがあります。 例えば、家族構成や恋愛関係、政治信条など、業務に直接関係のない個人的な事柄を詮索するような質問は避けるべきです。
内定者との良好な関係を築くためには、あくまでビジネスの範囲内でのコミュニケーションを心がけましょう。
複数の内定者がいる場合、連絡の頻度や内容、イベントへの招待などに差があると、内定者は不公平感を抱く可能性があります。特定の学生にだけ手厚いフォローを行い、他の学生にはほとんど連絡を取らないといった対応は、内定者の企業への不信感を募らせるため避けるべきです。例えば、内定者懇親会の案内を一部の内定者にしか送らなかったり、個別面談の機会を特定の学生に優先的に提供したりするケースが考えられます。
このような対応は、内定者間で「自分は大切にされていない」と感じさせ、入社への意欲を低下させる原因となります。全ての内定者に対して、公平かつ丁寧な対応を心がけることが、内定辞退を防ぐ上で重要になります。連絡は全員に一斉送信し、個別対応が必要な場合でも、他の内定者にも同様の機会が提供されていることを明確に伝えることが大切です。
内定後、企業からの連絡が頻繁すぎたり、過度な課題を強要されたりすると、内定者は負担に感じ、企業への入社意欲を低下させてしまうことがあります。特に、卒業論文や資格取得などで忙しい時期の内定者にとって、過度な拘束は大きなストレスとなります。例えば、週に何度も状況確認の連絡が来たり、入社前に提出を義務付けられる課題の量があまりにも多かったりすると、学業やプライベートの時間が圧迫され、精神的な負担が増大してしまうのです。
ある調査では、内定者へのアンケートで「フォローが過剰だと感じたこと」として、「課題が多くて負担になった」「連絡頻度が高すぎて窮屈に感じた」といった声が挙げられています。このような状況は、内定者が企業に対して「入社したらもっと拘束されるのではないか」という懸念を抱かせ、結果として内定辞退につながる可能性もあります。内定者の状況を考慮し、適切な頻度と内容で連絡や課題を設定することが大切です。
内定承諾後、これまで親身に接してくれていた採用担当者の態度が急に冷たくなることは、内定者が企業への信頼を失い、入社意欲を低下させる大きな要因となります。このような態度の変化は、内定者が「もう自分は必要とされていないのか」と感じるきっかけとなり、最終的に内定辞退につながる可能性もあります。特に、内定後から入社までの期間が長期にわたる場合、担当者からの連絡が途絶えたり、対応が事務的になったりすると、内定者は「放置されている」と感じてしまいがちです。
例えば、選考中は頻繁に連絡を取り合っていたにもかかわらず、内定承諾後は定型のメールしか来なくなった、質問への返信が遅くなった、といった変化があると、内定者は不信感を抱きやすくなります。企業側としては、内定後も変わらず丁寧な対応を心がけ、内定者を歓迎する姿勢を示し続けることが重要です。個別の状況を気遣うメッセージを送ったり、定期的にコミュニケーションの機会を設けたりすることで、内定者は「自分は大切にされている」と感じ、企業への信頼感を維持できます。また、内定後も変わらず学生の不安や疑問に寄り添うことで、安心して入社準備を進めてもらうことができるでしょう。
内定者フォローは、内定辞退の防止だけでなく、入社後の定着率向上や早期戦力化にも繋がる重要な採用活動の一環です。本記事で紹介したように、内定者が抱える不安を解消し、企業への期待感を高めるための様々な施策があります。内定式での丁寧な対応から始まり、定期的な情報提供や交流イベントの開催、スキルアップ支援など、多角的なアプローチで内定者をサポートすることが大切です。
特に、内定者一人ひとりの個性やニーズに合わせたきめ細やかなフォローは、内定者に「自分は大切にされている」という実感を与え、企業へのエンゲージメントを高めます。企業理念や文化を伝えるだけでなく、良い面も課題も正直に共有することで、入社後のギャップを減らし、早期離職を防ぐことにも繋がるでしょう。内定承諾後も継続的に内定者と良好な関係を築き、入社へのモチベーションを維持してもらうことで、企業と内定者の双方にとって実りある結果を生み出すことができます。


記事公開日 : 2025/12/16
最終更新日 : 2026/01/15
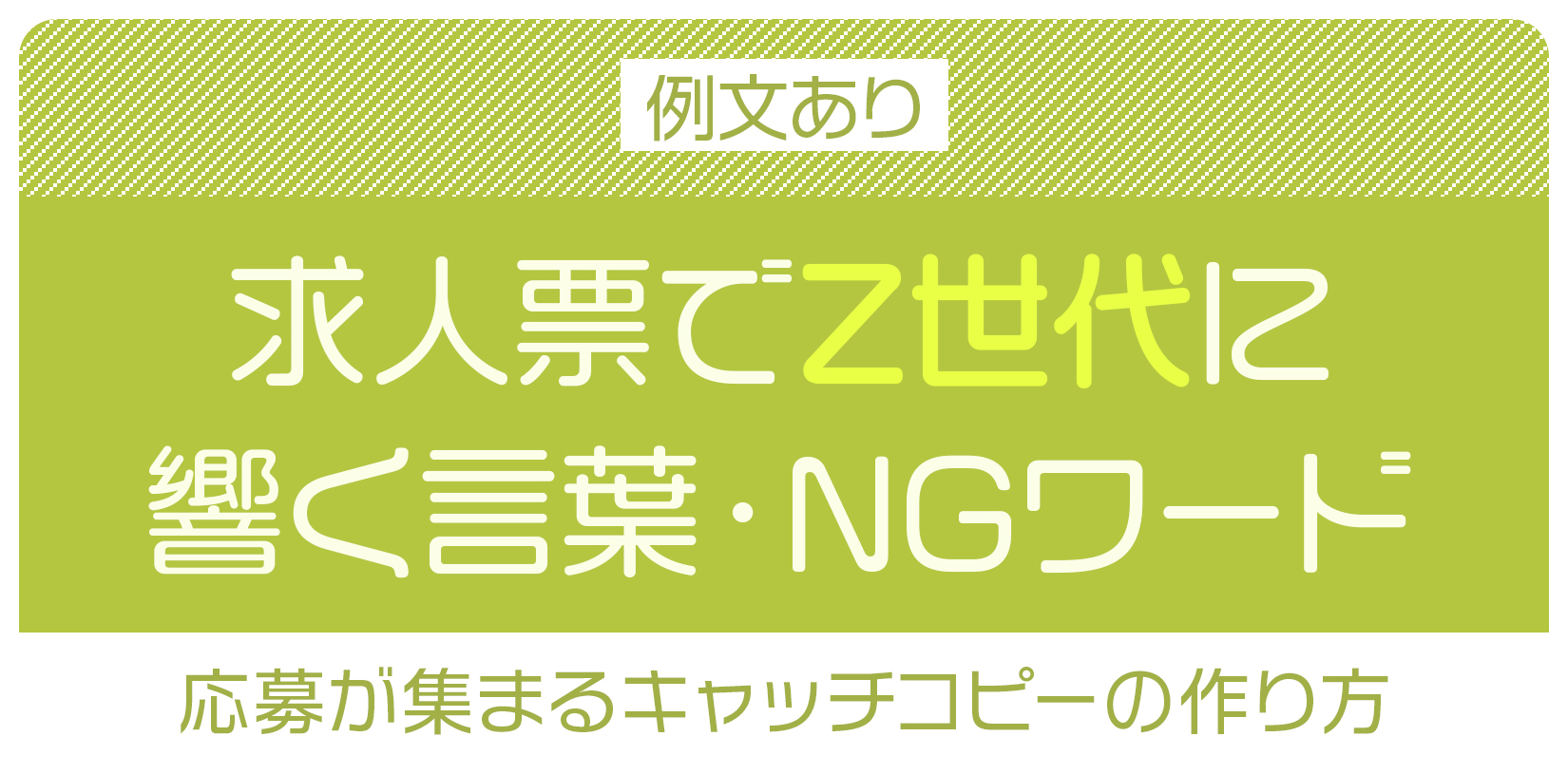
記事公開日 : 2025/12/12
最終更新日 : 2026/01/15
CONTACT