
【福利厚生としても注目!】近年話題のキャリアブレイクとは?
記事公開日 : 2026/01/16
最終更新日 : 2026/01/15
記事公開日 : 2025/08/21
最終更新日 : 2026/01/15
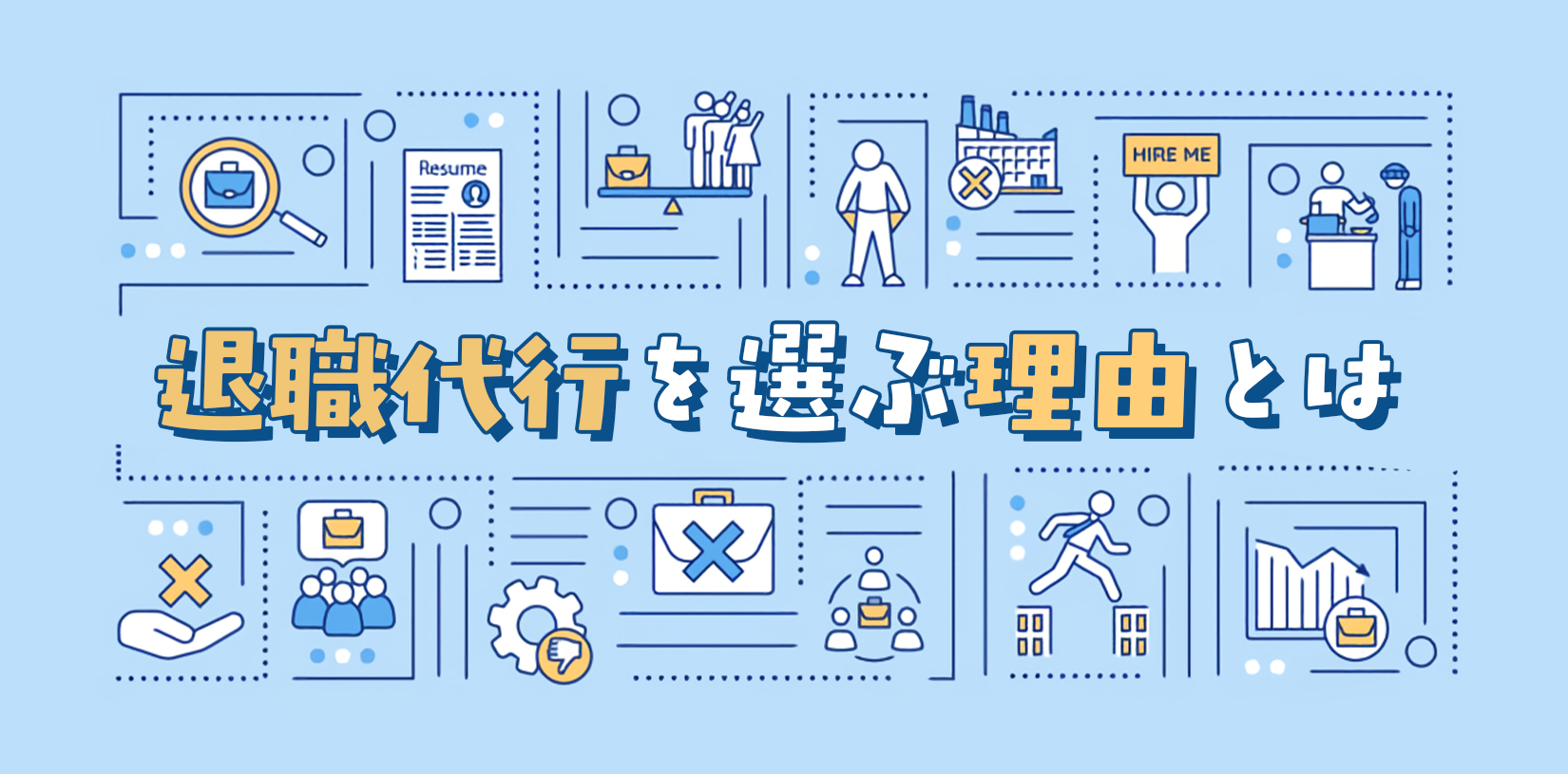
会社を辞めたいけれど、上司に直接退職の意思を伝えるのが難しいと感じる方は少なくありません。近年、このような悩みを解決する手段として「退職代行サービス」の利用が注目され、利用者も急増しています。特に若い世代で利用が多いこのサービスは、現代社会の働き方や価値観の変化を背景に広まりを見せています。本記事では、退職代行サービスの概要から利用が増加する背景、そして企業側が退職代行の利用を防ぐためにできることについて解説します。

退職代行サービスは、退職を希望する従業員に代わって、意思を企業に伝えるサービスです。通常、退職の意思を伝える際は上司や人事担当者と直接やり取りが必要ですが、退職代行を利用すると、これらのやり取りを代行業者が代わりに行ってくれます。これにより、依頼者は会社と直接連絡を取る必要がなくなり、精神的な負担を軽減しつつ退職手続きを進められるのが特徴です。退職代行サービスには、主に弁護士が運営するものと民間の業者が運営するものの2種類があります。
退職代行とは、退職を希望する依頼者の代理として、会社に退職の意思を伝えるサービスです。会社を退職したいと考えているにもかかわらず、上司から退職を受け入れてもらえなかったり、退職を言い出しにくい環境にあったりする状況で多く利用されています。このサービスは、依頼者に代わって退職の意思と退職日を会社に伝えることが主な役割です。退職代行を利用することで、依頼者は自ら会社に出向いたり、会社の人たちと直接話したりする必要がなく、全てのやり取りを代行業者が代理で行うことで、スムーズに退職手続きを完了させることが可能となります。
弁護士が運営する退職代行サービスは、法律の専門家である弁護士が対応するため、単に退職の意思を伝えるだけでなく、法的な交渉も可能です。具体的には、未払い賃金の請求、退職条件の交渉、有給休暇の消化交渉、退職金の請求など、労働問題に関するあらゆる交渉を代理人として行うことができます。また、会社が退職を拒否したり、不当な引き止めを行ったりした場合でも、弁護士が法的な観点から交渉を進めるため、依頼者が直接対応する必要がありません。万が一、労働審判や裁判に発展した場合でも、弁護士が代理人として対応できるため、より安心してサービスを利用できるでしょう。
弁護士によるサービスは、民間の退職代行サービスと比べて費用が若干高くなる傾向がありますが、法的トラブルのリスクを最小限に抑え、確実な退職を実現したい場合に適しています。
民間の退職代行サービスは、弁護士が運営するサービスとは異なり、依頼者の退職意思を会社に伝達する役割に限定されます。これらのサービスは、労働問題に関する交渉権を持たず、会社側から退職条件の調整や未払い賃金の請求などを求められたとしても、法律上対応することはできません。
民間の業者が適法に行えるのは、あくまで「使者として」依頼者の退職の意思を会社に伝えることのみであり、退職の可否や具体的な退職日に関する交渉は「非弁行為」にあたるため、違法となります。そのため、法的な知識が不足している業者も存在し、会社からの問い合わせに適切に対応できなかったり、トラブルに発展するケースも報告されています。
ただし、民間の退職代行サービスは弁護士に比べて費用が安価な場合が多く、手軽に利用できるというメリットがあります。会社との間で特にトラブルがなく、単に退職の意思を伝えにくいという場合に検討されることが多いサービスです。
近年、退職代行サービスの利用者が急増しており、その背景には現代の働き方や社会環境の変化が深く関わっています。2025年に入社した新卒社員の4人に1人が退職代行サービスの利用を検討する可能性があるという調査結果もあり、若年層を中心に退職代行が新しい退職方法として定着しつつあります。
従来の企業との直接交渉で退職を申し出るのが一般的だった時代から、第三者にその役割を依頼する人が多い状況へと変化しています。この現象は、ブラック企業問題やパワハラなど、職場環境が健全でないと感じるケースが増えていること、働き方改革によって個々人の価値観が多様化し、自身の生活スタイルを優先したいという意識が強まっていることが要因として挙げられます。その結果、「嫌な環境から早く抜け出したい」という心理的なプレッシャーから、多くの人が退職代行を選択する傾向にあると考えられます。
日本企業に長く根付いてきた終身雇用の価値観は、従業員が退職の意思を伝えにくい大きな要因の一つです。一つの企業で長く働くことが美徳とされ、転職が一般的ではなかった時代には、退職は裏切り行為と見なされることも少なくありませんでした。このような企業文化は、従業員に「辞めたい」と言い出すことへの強い心理的ハードルを与えています。特に、真面目で責任感が強い人ほど、自分だけが会社を辞めることに罪悪感を覚え、退職を言い出せない傾向があります。
加えて、人手不足が常態化している企業では、退職を申し出ても「今辞められたら困る」「後任が見つかるまで待ってほしい」などと強く引き止められるケースも多く、その結果、退職の意思がなかなか受け入れられない状況に陥ることがあります。このような状況下では、従業員は自力での退職が困難だと感じ、退職代行サービスの利用を検討せざるを得なくなります。終身雇用の価値観が崩壊し、雇用の流動化が進む現代においても、依然として退職のハードルが高い企業が存在することが、退職代行の利用者増加に繋がっていると言えるでしょう。
退職代行サービスを利用する人の多くは、職場の人間関係に問題を抱えているといわれています。上司からのパワハラや同僚からのいじめ、職場の雰囲気が悪く退職を言い出しにくい環境など、従業員が一人で悩みを抱え込み、精神的なストレスを募らせるケースが少なくありません。特に、退職の意思を伝えることで、これ以上人間関係が悪化することを避けたい、あるいは、上司と直接対面して話すこと自体が苦痛であると感じる従業員にとって、退職代行は有効な選択肢となります。
職場に馴染めず、仕事の悩みを相談できる相手がいない場合、従業員は孤立感を深め、自分から退職を伝えることがさらに困難になります。このような状況では、第三者である退職代行サービスを介して退職の意思を伝えることで、精神的な負担を大きく軽減し、会社との直接的なやり取りを避けてスムーズに退職できるメリットがあります。人間関係の悪化は、従業員の心身の健康にも影響を及ぼし、退職を考える大きな理由となるのです。
企業による強い引き止めは、従業員が退職代行サービスを利用する大きな理由の一つです。従業員が退職の意思を伝えたにもかかわらず、「今辞められたら困る」「後任が決まるまで待ってほしい」「損害賠償を請求する」などと、会社側から執拗に引き止められるケースが少なくありません。こうした強引な引き止めは、従業員にとって大きな心理的負担となり、退職を諦めてしまったり、精神的に追い詰められたりする原因となります。
また、一部のブラック企業では、人手不足を理由に退職を認めなかったり、退職を強要したりする事例も存在します。こうした状況下では、従業員が自力で退職交渉を行うのは非常に困難であり、第三者である退職代行サービスに依頼することで、会社との直接的な交渉を避け、スムーズな退職を目指すことができます。弁護士が運営する退職代行サービスであれば、法的な交渉権限を持つため、不当な引き止めや損害賠償請求といったトラブルにも対応し、従業員の退職の権利を守ることが可能です。
精神的な不調を抱えている従業員が退職代行サービスを利用するケースは非常に多いです。職場でのパワハラ、モラハラ、過重労働、人間関係の悩みなどが原因で、うつ病や適応障害、社会不安障害などの精神疾患を患ってしまう人も少なくありません。こうした精神的に限界な状態では、自分で会社と対峙して退職を伝えること自体が大きなストレスとなり、心身のさらなる不調を引き起こす可能性があります。退職代行サービスを利用することで、会社との直接的なやり取りによる精神的負担を大幅に軽減し、心身の回復に専念できるというメリットがあります。
労働基準法では、労働者にはいつでも退職する自由が認められており、病気を理由に退職することも可能です。精神科医も、精神的に追い詰められた状況で無理をして仕事を続けることは症状を悪化させる可能性があるため、退職代行を早期に利用することを推奨しています。実際に、退職代行サービスの利用者の多くが、精神的な理由で退職を決意しており、退職代行は、心の健康を守るための有効な手段として認識されつつあります。
従業員が退職代行サービスを利用することは、企業にとって一時的に業務への支障や他の従業員への影響といったデメリットが生じる可能性があります。しかし、退職代行サービスの利用は、企業が抱える潜在的な問題を示すシグナルと捉えることもできます。退職代行の利用を防ぐためには、従業員が退職代行サービスに頼らざるを得ない状況を根本から改善する対策を講じることが重要です。従業員が抱える不満を把握し、それに対する適切な対策を行うことで、退職代行の利用を未然に防ぎ、従業員が安心して働ける職場環境を構築することが可能となります。
退職希望者が直接相談しやすい環境を整備することは、退職代行サービスの利用を防ぐための重要な対策の一つです。従業員が「退職したい」と直接伝えることができず、退職代行に頼る背景には、職場の人間関係の悪化やハラスメント、上司からの強引な引き止めなど、会社に相談しにくい雰囲気が存在することが多いと考えられます。
こうした状況を改善するためには、まず上司と部下の間のコミュニケーションを見直し、信頼関係を築くことが不可欠です。定期的な1on1ミーティングの実施や、悩みや不満を安心して相談できる窓口の設置、ハラスメント対策の徹底など、従業員が心理的な負担なく退職の意思を伝えられるような仕組みを構築することが求められます。また、自己申告による配置換え制度の導入など、従業員がキャリアパスについて主体的に考え、必要に応じて相談できる機会を設けることも有効です。従業員が孤立することなく、自分の意見や希望を伝えられる環境があれば、退職代行サービスを利用する選択肢を考える前に、会社内で問題を解決しようと試みる可能性が高まるでしょう。
円滑な退職を可能にする仕組みを構築することは、退職代行の利用を防ぐ上で非常に重要です。従業員が退職代行を利用する理由として、「退職を言い出しにくい」「退職の引き止めが強い」「退職後のトラブルを懸念する」といった点が挙げられます。これらの懸念を払拭するためには、企業として退職手続きを明確にし、従業員が安心して退職できる環境を整える必要があります。具体的には、就業規則に退職に関する規定を明記し、退職の申し出から退職日までの流れ、有給休暇の消化、退職金や未払い賃金の支払いなどの条件を明確にすることが有効です。
また、従業員が退職を申し出た際に、強引な引き止めを行わず、速やかに退職手続きを進める姿勢を示すことも重要です。例えば、退職希望者に対して、業務の引き継ぎ期間や有給消化のスケジュールについて柔軟に対応し、不必要なトラブルを避けるよう努めるべきです。企業が退職を円滑に受け入れる仕組みを構築することで、従業員は退職代行サービスに頼らずとも、安心して次のキャリアへ進むことができるようになります。これにより、結果的に企業側にとっても、労務管理の効率化や法的リスクの低減といったメリットが生まれる可能性があります。
ハラスメント対策とメンタルヘルスケアの強化は、従業員が退職代行サービスを利用する原因となる根本的な問題を解決するために不可欠な取り組みです。パワハラやセクハラ、長時間労働などが横行する職場では、従業員が精神的な不調を抱えやすく、結果として退職を検討するケースが多くなります。こうした状況を防ぐためには、企業はハラスメントに対する明確な方針を定め、従業員への周知徹底、相談窓口の設置、そしてハラスメントが確認された場合の厳正な対応を行う必要があります。
また、従業員のメンタルヘルスケアも重要です。定期的なストレスチェックやカウンセリング制度の導入、産業医との連携強化などにより、従業員の心の健康状態を早期に把握し、必要なサポートを提供できる体制を整えることが求められます。特に、精神的な不調を抱える従業員が退職代行を考える前に、安心して相談できる環境を整備することが重要です。企業が積極的にハラスメント対策とメンタルヘルスケアに取り組むことで、従業員は安心して働き続けられると感じ、退職代行サービスを利用する必要性を感じにくくなるでしょう。
退職代行サービスの利用が広まる背景には、終身雇用の価値観が残る中で退職を言い出しにくい企業文化、職場の人間関係の悪化、企業による強い引き止め、精神的な不調を抱える従業員の増加など、様々な要因が絡み合っています。特に、会社と直接やり取りしたくない、すぐに退職したい、といった心理的負担を軽減したいというニーズが、このサービスを求める多くの人々に共通しています。
企業側としては、退職代行の利用を単なる甘えと捉えるのではなく、従業員が退職代行に頼らざるを得ない状況を改善する機会と捉えることが重要です。具体的には、退職希望者が直接相談しやすい環境を整備し、円滑な退職を可能にする仕組みを構築すること、ハラスメント対策とメンタルヘルスケアを強化することで、従業員が安心して働ける、あるいは退職できる職場環境を築くことが求められます。これらの対策を通じて、従業員満足度の向上と、結果的に退職代行サービスの利用を防ぐことに繋がるでしょう。


記事公開日 : 2026/01/16
最終更新日 : 2026/01/15
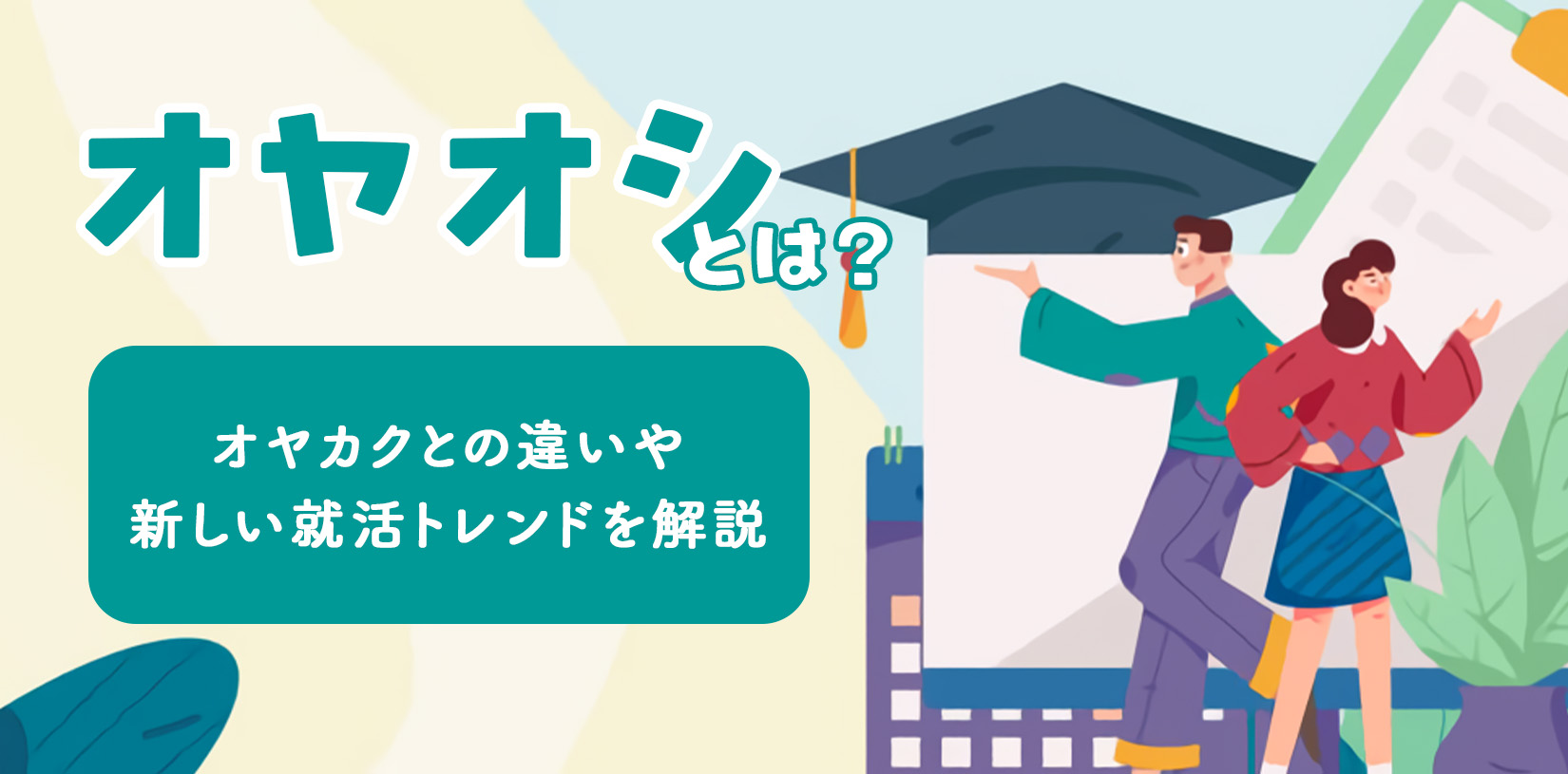
記事公開日 : 2026/01/13
最終更新日 : 2026/01/15
CONTACT