
タイパ抜群!?録画選考の活用法|Z世代に響かせるための動画面接
記事公開日 : 2026/01/29
最終更新日 : 2026/01/15
記事公開日 : 2025/10/27
最終更新日 : 2026/01/15

1dayインターンシップは、多くの学生と早期に接点を持ち、企業の魅力を伝える有効な手段です。成功させるためには、目的の明確化から本選考に繋げるための戦略的な設計が求められます。
この記事では、人事担当者が知るべき1dayインターンシップの基本概要、メリット・デメリット、学生を惹きつけるプログラム内容、企画から開催後までの具体的なステップ、そして採用成果に結びつけるためのコツまでを網羅的に解説します。

初めて1dayインターンシップの導入を検討する人事担当者にとって、その定義や目的を正確に理解することは不可欠です。企業説明会との違いや、多くの企業が導入するに至った背景を知ることで、自社に合った企画の土台を築けます。
ここでは、企画を始める前に押さえておくべき、1dayインターンシップとは何か、その基本的な概要について解説します。
1dayインターンシップとは、その名の通り1日で完結する職業体験プログラムです。企業が開催する目的は多岐にわたりますが、主には学生に対する企業の認知度向上、事業内容や社風への理解促進、そして採用活動における母集団形成が挙げられます。
2025年卒以降の採用活動からは、特定の要件を満たすことでインターンシップで得た学生情報を採用選考に活用できるようになりました。これにより、企業は1dayインターンシップを通じて学生の能力や適性を見極め、早期の段階で優秀な人材と接点を持つ機会として活用しています。短期間で多くの学生にアプローチできるため、効率的な広報および採用活動の手段として位置づけられます。
1dayインターンシップ導入の背景には、採用活動の早期化とオンライン化の進展があります。かつては経団連の指針により、採用に直結するインターンシップの開催時期が制限されていましたが、そのルールが変化し、企業の採用活動はより早期から始まるようになりました。特に2025年卒の学生からは、一定要件を満たしたインターンシップで得た学生情報を広報活動や採用選考に利用することが認められました。
しかし、採用選考活動に直結しない「オープン・カンパニー」としての1dayイベントは学年不問で実施できるため、早期から学生との接点を持つ手段として広く活用されています。また、学業で多忙な学生にとっても参加のハードルが低く、企業側は効率的に母集団を形成できるという利点も導入を後押ししています。
企業説明会が主に企業側から学生へ向けた一方向の情報提供の場であるのに対し、インターンシップは学生が能動的に参加する「体験型」のプログラムである点が大きく異なります。説明会ではパンフレットやスライドを用いて事業内容や福利厚生を伝えることが中心ですが、インターンシップではグループワークや社員との座談会などを通じて、実際の業務に近い体験や社内の雰囲気を感じ取ってもらうことに重きを置きます。
学生は説明会だけでは得られないリアルな企業情報に触れることで、入社後の働き方を具体的にイメージしやすくなり、企業理解を深めることが可能です。企業側にとっても、学生の主体性や人柄を評価する機会となります。
1dayインターンシップを導入することは、企業にとって多くの利点をもたらします。特に、採用競争が激化する現代において、早期から多くの学生と接点を持ち、自社の魅力を効果的に伝えることは重要です。また、採用ブランディングの強化や、運営コストの抑制といった側面も見逃せません。
ここでは、人事担当者が企画を推進する上で把握しておくべき、企業側の具体的な3つのメリットと、それが早期選考にどう繋がるのかを解説します。
1dayインターンシップは、学業やアルバイトで忙しい学生でも気軽に参加しやすいため、これまで接点が持てなかった多様な層の学生にアプローチできる機会となります。中長期のプログラムと比較して参加へのハードルが低く、より多くの学生を集めやすいのが大きな利点です。これにより、採用広報活動が本格化する前から、幅広い学生に対して自社の認知度を高め、良好な関係を築くことが可能になります。
特に、まだ特定の業界や企業に志望を固めていない学生に早期の段階で接触することで、将来の採用候補者となる母集団を効率的に形成できます。多くの学生と接点を持つことは、自社の魅力を広く伝え、採用の選択肢を広げる上で非常に有効です。
1dayインターンシップは、企業の魅力や独自の社風を学生に直接伝える絶好の機会です。プログラムの内容を工夫することで、事業の面白さや社会的な意義、働く社員の姿などを具体的に示し、学生の共感を呼ぶことができます。特に、一般消費者向けの製品やサービスを持たないBtoB企業や、設立間もないベンチャー企業にとっては、自社の存在や事業内容を広く知ってもらうための有効な手段となります。
参加した学生がSNSや口コミで好意的な感想を発信すれば、その効果はさらに広がり、採用市場における企業のブランドイメージ向上に貢献します。魅力的な体験を提供することは、学生の入社意欲を高めるだけでなく、企業のファンを増やすことにも繋がります。
1dayインターンシップは開催期間が1日と短いため、企画から運営までにかかるコストを大幅に抑制できる点が大きなメリットです。例えば、会場費や資料作成費、社員の工数を最小限に抑えられます。長期インターンでは、学生一人ひとりに対してメンターをつけ、継続的な指導やフィードバックを行う必要があり、現場社員の負担が大きくなりがちです。
しかし、1dayであれば関わる社員の人数や時間を限定できるため、通常業務への影響も少なく済みます。コストやリソースを抑えられる分、開催頻度を増やしたり、複数の異なるテーマでプログラムを実施したりと、柔軟な運用が可能になり、結果としてより多くの学生と接点を持つ機会を創出できます。
1dayインターンシップは多くのメリットがある一方で、手軽さゆえのデメリットや注意点も存在します。プログラム内容が表面的になりがちで、学生の企業理解に深く繋がらないケースや、多くの学生と接するがゆえに関係性が希薄になってしまう可能性があります。企画段階でこれらの課題を認識し、対策を講じなければ、期待した効果を得られないことも少なくありません。
ここでは、1dayインターンシップを成功させるために、事前に把握しておくべきデメリットと注意点を解説します。
1日という限られた時間では、伝えられる情報量や学生が体験できる業務内容に限界があります。そのため、プログラムの設計を誤ると、単なる会社説明会と変わらない内容になってしまいがちです。
学生は、企業の一方的な説明を聞くことよりも、具体的な仕事内容や社風を体験的に理解することを期待しています。内容が浅いと、「どの会社も同じようなことしか言わない」という印象を与え、かえって学生の志望度を下げてしまうリスクも考えられます。
企業の本当の魅力や仕事のやりがいを伝えるためには、テーマを一つに絞り込み、その分野を深く掘り下げるなど、短時間でも強い印象を残せるようなコンテンツの工夫が不可欠です。ありきたりな内容では、学生の満足度は得られません。
1dayインターンシップは多くの学生を集めやすい反面、一人ひとりの学生と深いコミュニケーションを取ることが難しいという側面があります。参加人数が多い場合、名前と顔を一致させることも難しく、自己紹介だけで終わってしまい、個々の学生の特性や考えを十分に把握できないまま終了することも少なくありません。イベント当日だけの関わりで終わってしまうと、せっかく築いた接点も時間とともに薄れてしまい、本選考への応募に繋がりません。
このデメリットを克服するためには、インターンシップ開催後のフォローアップが重要になります。アンケートの実施や個別のフィードバック、参加者限定のイベント案内など、継続的にコミュニケーションを取る仕組みをあらかじめ設計しておく必要があります。
近年の就職活動において、多くの学生は複数の企業のインターンシップに参加するため、その目は非常に肥えています。ありきたりな企業説明や簡単なグループワークだけでは、学生の心に響かず、他社との差別化を図ることは困難です。学生が「この会社で働いてみたい」と感じるような、期待を超える体験価値を提供するためには、自社の強みや仕事の面白さを体感できる、独自性の高いプログラムを企画する必要があります。
しかし、こうした魅力的なコンテンツをゼロから設計するには、人事担当者に相応の企画力と準備時間が求められ、大きな負担となることも事実です。他社の事例を参考にしつつも、自社ならではの魅力をどう伝えるかを突き詰めて考えることが成功の鍵となります。
学生の満足度を高め、自社への興味を喚起するためには、プログラムの内容が重要です。単なる企業説明に終始するのではなく、学生が主体的に参加し、学びや気づきを得られる体験型のコンテンツを盛り込む必要があります。
ここでは、多くの学生から「参加してよかった」という声が上がるような、魅力的で効果的な1dayインターンシップのプログラム例を4つ紹介します。これらの例を参考に、自社の魅力が伝わる独自のプログラムを企画してください。
実際の業務内容に近いテーマを設定したワークショップやグループディスカッションは、学生が仕事の面白さや難しさをリアルに体感できる人気のプログラムです。例えば、新商品の企画立案や既存サービスの改善提案といった課題を与え、チームで議論しながら成果物を発表してもらいます。
このプロセスを通じて、学生は自社の事業内容への理解を深めると同時に、チームで働くことの醍醐味を味わえます。企業側は、議論の進め方や発表内容から、学生の論理的思考力、協調性、創造性といった潜在的な能力を見極めることも可能です。
員がファシリテーターとして各グループのワークをサポートし、適宜フィードバックを行うことで、より学びの深い体験を提供できます。
学生が企業に対して抱く疑問や不安を解消し、働くことへの解像度を高める上で、現場で働く社員との座談会は非常に効果的です。特に、年齢の近い若手社員から管理職まで、様々な役職や部署の社員に参加してもらうことで、多様なキャリアパスや働き方を提示できます。
学生は、Webサイトやパンフレットだけでは分からない社内の雰囲気や人間関係、仕事のやりがいといったリアルな情報を直接質問し、知ることが可能です。企業側は、学生からの素朴な質問に真摯に答えることで、誠実な姿勢を示し、学生との信頼関係を築けます。少人数のグループに分けて実施すると、学生一人ひとりが発言しやすくなり、より密なコミュニケーションが期待できます。
ビジネスケーススタディは、企業が過去に直面した実際の課題や、現在進行中のプロジェクトを題材に、学生に解決策を考えさせるプログラムです。例えば、ある商品の営業戦略を立案したり、新規事業の市場調査を行ったりといった、より実践的なテーマを設定します。
このプログラムは、学生に当事者意識を持たせ、ビジネスの複雑さや意思決定の難しさを体験させるのに適しています。また、社員からのフィードバックを通じて、プロの視点や思考プロセスを学ぶことができ、学生にとって大きな成長の機会となります。企業側にとっても、課題解決能力や分析力といった、実務に近いスキルレベルを評価する良い機会です。
学生にとって、実際に働くことになるオフィス環境は、企業選びの重要な要素の一つです。執務スペースや会議室、食堂、リフレッシュスペースなど、社内の様々な場所を案内するオフィス見学は、学生が入社後の働き方を具体的にイメージする手助けとなります。
社員が生き生きと働く様子を実際に見ることで、Webサイトや資料だけでは伝わらない企業の雰囲気や文化を肌で感じ取ることができ、企業への親近感を高める効果があります。また、こだわりのオフィス設備や独自の福利厚生制度などを紹介することで、働きやすさをアピールし、他社との差別化を図ることも可能です。オンライン開催の場合でも、動画やVRを活用したバーチャルオフィスツアーで同様の効果が期待できます。
1dayインターンシップを成功させるには、戦略的な計画と実行が不可欠です。目的設定から始まり、魅力的なコンテンツ企画、効果的な集客、スムーズな当日運営、そして次へと繋げるアフターフォローまで、一連の流れを体系的に捉える必要があります。
ここでは、企画段階から開催後に至るまで、1dayインターンシップを成功に導くための具体的な5つのステップを解説します。この手順に沿って準備を進めることで、効果を最大化できます。
まず最初に、何のために1dayインターンシップを実施するのかという開催目的を明確に定義することが重要です。目的がBtoB企業である自社の認知度向上なのか、特定職種の母集団形成なのか、あるいは早期選考候補者の見極めなのかによって、プログラムの内容やアプローチ方法は大きく異なります。
目的に合わせて、ターゲットとなる学生像も具体的に設定します。学部や専攻、スキル、価値観、志向性などを詳細に定めることで、より学生に響くメッセージを発信でき、効果的な集客活動に繋がります。この初期段階の設計が、インターンシップおよび採用全体の成否を左右すると言っても過言ではありません。
目的とターゲットが明確になったら、次はその学生たちに「参加してよかった」と思ってもらえるような魅力的なコンテンツを企画します。ステップ1で定めた目的に沿って、企業の何を伝えたいのか、学生に何を得てほしいのかを考え、具体的なプログラムに落とし込みます。
例えば、仕事の面白さを伝えたいなら実践的なワークショップを、社風の良さを感じてほしいなら社員との座談会をメインに据えるなど、目的に応じた最適なコンテンツを選択します。全体のタイムスケジュール、各プログラムの担当者、準備物などを詳細にリストアップし、実行可能な計画を立てることが、当日のスムーズな運営には不可欠です。
どれほど魅力的なプログラムを企画しても、ターゲットとなる学生にその情報が届かなければ意味がありません。設定したターゲット学生像に基づき、最も効果的な集客チャネルを選定します。就職情報サイトへの掲載、大学のキャリアセンターとの連携、研究室への直接アプローチ、ダイレクトリクルーティングサービスの活用、さらにはX(旧Twitter)やInstagramといったSNSでの情報発信など、多様な方法が考えられます。
告知文では、インターンシップの魅力を簡潔に伝え、参加することで何を得られるのかを具体的に示すことが、学生の応募意欲を高める上で重要です。複数のチャネルを組み合わせ、多角的にアプローチすることが成功の鍵となります。
当日の運営が円滑に進むかどうかは、参加者の満足度に直結します。司会進行役、グループワークのファシリテーター、受付担当、機材トラブルに対応する技術担当など、それぞれの役割を事前に明確に割り振り、責任の所在をはっきりさせておく必要があります。可能であれば、本番さながらのリハーサルを行い、時間配分や進行の流れ、連携の仕方を確認しておくと安心です。
また、学生から寄せられるであろう質問をあらかじめ想定し、回答をまとめたQ&A集を準備しておくことも、質の高い対応に繋がります。予期せぬトラブルが発生した場合の対応フローも決めておくなど、万全の体制で当日を迎えることが求められます。
1dayインターンシップは、開催して終わりではありません。その後のアフターフォローこそが、学生の志望度を高め、本選考への応募、ひいては内定承諾へと繋げるための重要なプロセスです。参加者全員にお礼のメールを送るのはもちろん、アンケートを実施してフィードバックを収集し、今後の改善に活かします。
特に優秀だと感じた学生や、自社とのマッチ度が高いと感じた学生には、社員との個別面談や、参加者限定のセミナー、早期選考ルートなどを案内し、特別な接点を継続的に持ちます。こうした丁寧なフォローを通じて、学生との関係性を深化させることが、採用成功の鍵となります。
1dayインターンシップを開催する最終的な目的は、採用成果、すなわち優秀な人材の内定獲得にあります。そのためには、イベントを一過性のものとせず、参加した学生を本選考へと効果的に誘導する戦略的な仕掛けが不可欠です。
ここでは、インターンシップの価値を最大化し、採用活動に直結させるための3つの具体的なコツを紹介します。これらの施策を通じて、学生の志望度を高め、他社との差別化を図ることが可能になります。
グループワークや発表など、学生のアウトプットに対して、人事担当者や現場社員から個別のフィードバックを行うことは非常に効果的です。一人ひとりの良かった点や今後の課題などを具体的に伝えることで、学生は「自分のことを見てくれている」と感じ、企業への信頼感やエンゲージメントが高まります。
この丁寧な対応は、学生にとって自己分析を深める貴重な機会となるだけでなく、企業側が学生一人ひとりに真摯に向き合う姿勢を示すことにも繋がります。このような特別感のある体験は、学生の記憶に強く残り、数ある企業の中から自社を選んでもらう動機付けとなり、その後の採用プロセスにおいて有利に働きます。
インターンシップ参加者に対して、一般の応募者とは異なる特別な選考ルートを用意することは、優秀な学生を惹きつけ、囲い込むための強力な手法です。例えば、一次選考を免除したり、役員との座談会に招待したりといった特典を提供することで、学生に「選ばれている」という優越感を与え、志望度を格段に高めることができます。
このような参加者限定の早期選考やイベントの案内は、インターンシップで得た企業への興味・関心を具体的な応募行動へと繋げる強力な後押しとなります。他社に先駆けて優秀な学生と継続的な接点を持つことで、採用競争を有利に進めることが可能です。
インターンシップ終了後、学生との関係を途切れさせないことが、内定承諾率を高める上で極めて重要です。メールマガジンやLINE公式アカウントなどを活用し、企業の最新ニュースや社員インタビュー、次のイベントの案内などを定期的に発信し続けましょう。学生の就職活動に関する相談に乗ったり、個別の質問に丁寧に回答したりすることも、信頼関係の構築に繋がります。
こうした継続的なコミュニケーションを通じて、学生の自社への関心を維持し、本選考の時期が来た際に第一想起してもらえるような存在になることを目指します。一貫した情報提供と丁寧な対応が、最終的に内定への道を確実なものにします。
近年、場所を選ばずに開催できるオンライン形式の1dayインターンシップが主流となりつつあります。しかし、対面とは異なる難しさがあるのも事実です。学生の集中力をいかに維持し、企業の魅力をweb上で効果的に伝えるかが成功の鍵となります。
ここでは、オンラインという環境の特性を踏まえ、参加者の満足度を高め、成果に繋げるための2つの重要な成功ポイントについて解説します。
オンラインでの開催は、学生が受け身になりやすく、集中力が途切れやすいという課題があります。一方的な講義形式が続くと、学生は画面を見ているだけで内容が頭に入ってきません。
これを防ぐためには、意図的に双方向のコミュニケーションを盛り込むことが不可欠です。チャット機能でリアルタイムに質問を受け付けたり、投票機能を使って意見を求めたり、少人数に分かれるブレイクアウトルームでディスカッションの機会を設けたりと、学生が能動的に参加できる仕掛けをプログラム全体に散りばめましょう。学生が自ら考え、発言する場面を増やすことで、オンラインでありながらも一体感と高い満足度を生み出すことができます。
当日の機材トラブルや通信障害は、オンラインインターンシップの満足度を著しく低下させる大きな要因です。映像が途切れたり、音声が聞こえなかったりすると、学生の集中力は削がれ、プログラムの内容が十分に伝わりません。
こうした事態を避けるため、主催者側は安定した高速インターネット回線と、性能の良いPC・マイク・カメラを準備することが必須です。また、使用するweb会議ツールの基本的な操作方法については、事前に参加者へマニュアルを送付し、使い方を周知しておくとスムーズです。可能であれば、開催前に接続テストの機会を設け、参加者側の環境に問題がないかを確認することも有効な対策となります。
1dayインターンシップは、企業が多くの学生と早期に接点を持ち、自社の認知度向上やブランディング強化を図る上で非常に有効な採用手法です。短期間の開催であるため、企画から運営までのコストを抑えつつ、効率的に母集団を形成できるメリットがあります。しかし、プログラム内容が表面的になりやすく、学生との関係性が希薄になる可能性も秘めているため、入念な準備が不可欠です。
成功の鍵は、明確な目的設定とターゲット学生像に基づいた魅力的なコンテンツ企画にあります。例えば、実践的なワークショップや社員との座談会、ビジネスケーススタディ、オフィス見学などを取り入れることで、学生の満足度を高め、企業理解を深めることができます。また、オンラインでの開催においては、双方向のコミュニケーションを意識したプログラム設計や、安定した通信環境の確保が重要です。
開催後には、参加者への個別フィードバックや、インターン参加者限定の選考ルート、イベントの案内、定期的なコミュニケーションを通じて、学生の志望度をさらに高め、本選考への応募に繋げることが重要となります。これらの施策を適切に実施することで、1dayインターンシップは単なる短期イベントではなく、採用成果に直結する強力なツールとなるでしょう。


記事公開日 : 2026/01/29
最終更新日 : 2026/01/15
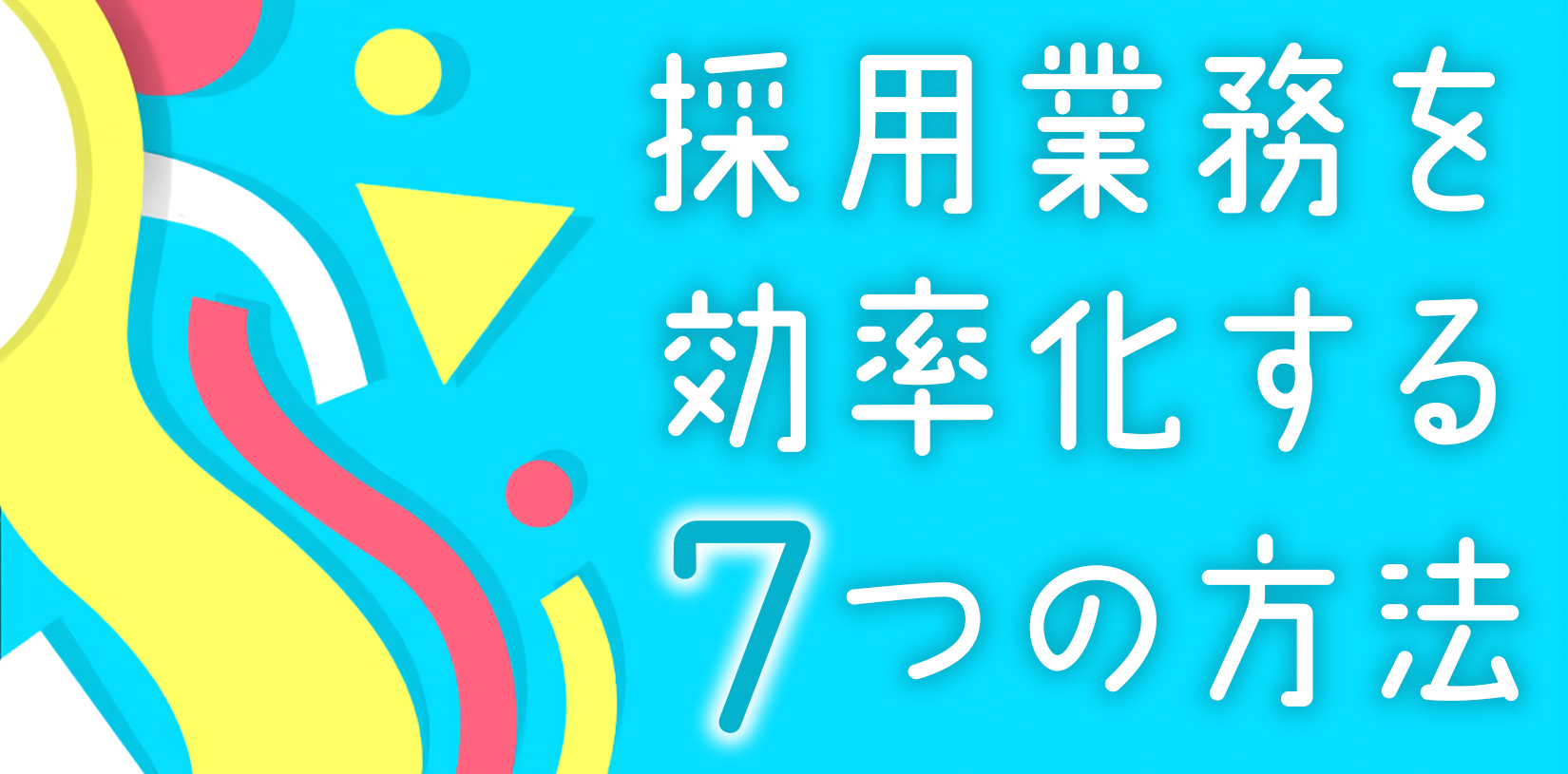
記事公開日 : 2026/01/27
最終更新日 : 2026/01/15
CONTACT