
タイパ抜群!?録画選考の活用法|Z世代に響かせるための動画面接
記事公開日 : 2026/01/29
最終更新日 : 2026/01/15
記事公開日 : 2025/10/23
最終更新日 : 2026/01/15

学生団体とは、学生が主体となって特定の目的を掲げ活動する組織のことです。企業にとって学生団体との連携は、優秀な人材への早期アプローチや効果的なブランディングなど多くのメリットをもたらします。
本記事では、学生団体の基本的な定義から、企業が連携することで得られる具体的な利点、さらにはビジネスコンテストの共同運営といった連携事例まで、採用や学生向けブランディングを検討する担当者向けに網羅的に解説します。

学生団体とは、学生が共通の目的や関心のもとに自主的に設立し、運営する任意の集まりを指します。サークルや部活動と異なり、大学非公認の団体も多く存在するのが特徴です。
活動目的は社会貢献、ビジネス、国際交流など多岐にわたります。法律上の明確な定義はなく、法人格を持たないケースがほとんどですが、中にはNPOやNGOといった法人格を取得して大規模に活動する団体も見られます。非営利目的で設立されるのが一般的で、利益を追求しないスタイルが基本です。
学生団体の活動は、イベント企画、メディア運営、マーケティングリサーチなど多岐にわたります。特定のテーマを掲げ、交流会や勉強会を通じて知見を深める団体も少なくありません。例えば、経営、教育、薬学といった学術的な分野から、政治、宇宙開発、理系研究など専門性の高いテーマまで様々です。
また、国際交流を目的とした英語でのディスカッションや、ファッションショーの開催、スポーツ大会の企画、長期休暇を利用した旅行の実施など、メンバーの興味関心に基づいた多様な経験を積んでいます。活動後には打ち上げなどを通じて、メンバー間の親睦を深めることもあります。
学生団体とサークルや部活動との間には、活動目的や組織運営において明確な違いが見られます。一般的にサークルは、共通の趣味を持つ仲間との交流や楽しみを主な目的とする内向きな活動が中心です。部活動は、大学の公認組織としてスポーツや文化活動における技術向上や大会での勝利を目指す傾向があります。
これに対し学生団体は、社会問題の解決やビジネススキルの向上など、より明確な目的意識や社会との関わりを持つ点が特徴です。サークルと比較して、外部の企業や団体と連携したり、社会に向けた情報発信を積極的に行ったりするケースが多く見受けられます。
応募から面接に至るまでの過程で、企業の対応に不満を抱いたことがドタキャンの引き金になる場合があります。
例えば、書類選考の結果連絡が遅い、メールの文面が不親切、面接日程の調整が一方的であるなど、応募者への配慮に欠ける対応は志望度を著しく下げてしまいます。
応募者は選考を通じて、その企業で働く自身の姿を想像するため、ぞんざいに扱われたと感じると「入社後も同じような対応をされるのではないか」と不安になります。結果として、その企業で働く意欲を失い、面接を辞退することを選択するのです。
企業が学生団体と連携することには、採用活動やブランディングにおいて大きなメリットがあります。学生団体への支援やスポンサーという形で関わることで、学生との間に良好な関係を築くことが可能です。これは、従来の採用手法とは異なる、能動的で意欲の高い学生層へのアプローチを実現します。
また、学生コミュニティ内での企業の認知度向上や、学生のリアルな視点を取り入れたマーケティング活動にもつながります。単なる営業活動ではなく、長期的な視点での関係構築が期待できます。
学生団体には、主体的に行動できる意欲の高い学生が数多く所属しています。特に有名な学生団体のリーダーや幹部クラスは、組織をまとめる統率力や課題解決能力に長けている傾向があります。通常の採用面接だけでは見極めにくいこれらの能力を、団体活動への関与を通じて深く理解することが可能です。
早稲田大学や慶應義塾大学、東大、立教大学、南山大学といった難関大学の学生が中心となって活動している団体も少なくなく、学業レベルと活動意欲を兼ね備えた優秀な層へ直接アプローチできる点は大きな魅力です。企業説明会やナビサイトだけでは出会えない、ポテンシャルの高い学生と早期に接点を持てます。
学生団体での活動を通して、学生は実践的なスキルを身につけています。例えば、イベント運営団体では企画力や渉外力、マーケティング団体ではWebマーケティングやSNS運用のスキルが磨かれます。特にIT系の団体では、プログラミングスキルを持つエンジニア志望の学生が、サービス開発やアプリ制作といった実務に近い経験を積んでいることもあります。
これらのスキルは、入社後すぐに業務で活かせるため、企業は即戦力として期待できる人材を発掘できます。座学だけでは得られない、実体験に裏打ちされたスキルを持つ学生との出会いは、採用活動において非常に価値が高いものです。
学生団体は、独自の強力なネットワークを保有しています。一つの団体が数百人規模のメンバーを抱えているケースや、複数の大学の団体で構成される連盟組織も存在します。有名団体や影響力の大きい団体と連携することで、そのネットワークを通じて自社の認知度を効率的に高めることが可能です。
例えば、イベントに協賛すれば、参加する多くの学生に企業の名前や事業内容を直接伝えられます。学生間の口コミは拡散力が高く、SNSなどを通じて一気に情報が広がることも期待できます。マス広告ではリーチしにくい学生層に対して、信頼性の高い情報源からアプローチできる有効な手段となります。
学生団体の活動は多岐にわたり、一言で説明するのは困難です。その活動ジャンルは、社会貢献からビジネス、国際交流、学術研究まで様々です。企業が自社の事業内容や採用したい人物像と親和性の高い団体を見つけるためには、まずどのような種類の団体が存在するのかを把握することが重要です。
ここでは、代表的な活動ジャンルの例を一覧で紹介し、それぞれの特徴について解説します。自社に合った連携先を探す際の参考にしてください。
学生団体の中には、大規模なイベントの企画や運営を専門に行う団体が数多く存在します。その活動内容は、新入生向けの交流イベントや大学の学園祭、地域の祭りのサポート、さらには音楽フェスやファッションショーといった商業的なイベントまで多岐にわたります。
これらの団体に所属する学生は、企画立案から会場設営、広報活動、当日の運営まで、イベント成功に向けた一連のプロセスを経験します。そのため、プロジェクトマネジメント能力やチームワーク、コミュニケーション能力が高い傾向にあります。企業はこうしたイベントへの協賛やブース出展などを通じて、多くの学生と接点を持つことが可能です。
ビジネスコンテストの企画・運営や、将来的な起業を目指して活動する学生団体も活発です。これらの団体は、社会課題を解決するための新しいビジネスモデルを考案し、事業計画の策定やプレゼンテーション能力を磨くことに注力しています。
メンバーは、マーケティング、ファイナンス、戦略立案といったビジネスの基礎知識を実践的に学び、企業との共同プロジェクトや現役起業家からのメンタリングを通じてスキルを高めています。企業にとっては、こうしたビジネスコンテストの審査員やスポンサーとして参加することで、次世代のビジネスリーダー候補となるような、高い問題解決能力と挑戦意欲を持つ学生との出会いが期待できるでしょう。最終戦まで残るような学生は特に優秀な傾向があります。
社会貢献意識の高い学生が集まり、ボランティア活動を主軸とする団体も多く存在します。活動テーマは、環境問題への取り組みとして地域の清掃活動やリサイクル推進、子ども食堂の運営支援、過疎化が進む地域での地域活性化イベントの企画など、国内の課題に焦点を当てるものがあります。また、海外に目を向け、ラオスなどの発展途上国での教育支援やインフラ整備支援を行う団体も少なくありません。
これらの活動を通じて、学生は社会課題への深い洞察力や行動力を養います。地方創生やSDGsに積極的に取り組む企業にとって、こうした団体との連携は、親和性の高い人材へのアプローチやCSR活動の一環として有効です。
グローバルな視野を持つ学生が集まるのが、国際交流や留学支援を目的とする団体です。主な活動として、キャンパス内の留学生と日本人学生の交流イベントを企画したり、海外の大学とのオンライン交流会を実施したりします。また、留学経験者が自身の体験を基に、これから留学を目指す学生へ情報提供や相談会を行うなど、支援活動にも力を入れています。
こうした国際系の団体に所属する学生は、語学力はもちろん、異文化への理解力やコミュニケーション能力が高いことが特徴です。グローバル展開を進める企業や、多様なバックグラウンドを持つ人材を求める企業にとって、魅力的な学生と出会える貴重な場となり、国際的な感覚を持つ人材の採用につながります。
特定の学問分野への深い探求心を持つ学生が集まり、研究や議論を行う学術系の団体も全国に存在します。法律分野でのディベート大会、経済学に関する論文発表会、マーケティング戦略の共同研究など、活動内容は専門的です。
関東や関西といった地域単位で活動する団体もあれば、東京、大阪、京都、福岡、広島、熊本、横浜、神奈川、愛知など都市部の大学を中心に、複数の大学の学生が参加するインカレ形式の団体も多く見られます。所属学生は論理的思考力や専門知識に長けているため、専門職や研究職の採用を考えている企業にとっては、非常に親和性の高い学生と出会える機会となります。
優秀な学生が多く所属する学生団体と連携したいと考えても、どのように接点を持てばよいか分からない企業担当者もいるかもしれません。学生団体とコンタクトを取る方法はいくつか存在し、自社の状況や目的に合わせて適切な手段を選ぶことが重要です。
ポータルサイトでの検索から、採用サービス、社内人脈の活用まで、具体的なアプローチ方法を解説します。これらの方法を組み合わせることで、より効果的に目的の団体とつながることが可能です。
学生団体との接点を持つための有効な手段として、学生団体の情報が集約されたポータルサイトの活用が挙げられます。これらのサイトでは、全国の多様な学生団体が活動内容や連絡先を登録しており、企業は自社のニーズに合った団体を効率的に検索できます。
多くのポータルサイトは無料で閲覧可能で、団体のホームページやSNSへのリンクも掲載されているため、より詳細な情報を得ることが容易です。まずはキーワード検索で関心のある分野の団体を探し、活動内容を確認した上でコンタクトを取るのが一般的な流れです。団体側も企業からの連絡を待っているケースが多いため、積極的にアプローチすることが連携の第一歩となります。
学生団体の経験者を効率的に探す方法として、新卒採用向けのスカウトサービスの利用も有効です。多くのサービスでは、学生がプロフィールに所属団体や活動内容を登録しており、企業はそれらの情報をもとにターゲットとなる学生を検索し、直接スカウトメッセージを送ることができます。
特に「OfferBox」や「dodaキャンパス」のような大手サービスに加えて、「en-courage(エンカレッジ)」や学生団体の活動を支援する「TSUNAGU」など、特定のコミュニティに強いサービスも存在します。また、「actry」や「CANS」のように、学生団体の協賛に特化したプラットフォームも登場しており、自社の目的に合わせてサービスを選択することが可能です。
自社の社員や内定者の人脈を頼ることも、学生団体と接点を持つための有効な手段です。特に若手社員や内定者の中には、学生時代に何らかの団体に所属していた経験を持つ者がいる可能性があります。彼らに後輩を紹介してもらったり、所属していた団体の幹部へコンタクトを取ってもらったりすることで、スムーズに関係を構築できる場合があります。
例えば、JR東日本企画が学生団体と連携したイベントを実施した事例のように、社内のリソースを活かしたアプローチは、外部のサービスを利用するよりも信頼関係を築きやすいというメリットがあります。まずは社内でヒアリングを行い、学生団体とのつながりを持つ人材がいないか確認することから始めるとよいでしょう。
企業が学生団体と連携することで、単なる採用活動にとどまらない多様な取り組みが実現可能です。学生の持つ斬新なアイデアや行動力、そしてコミュニティへの影響力を活用し、企業のブランディングやマーケティング、商品開発などに活かすことができます。
ここでは、実際に企業と学生団体が連携して成功を収めた活用事例をいくつか紹介します。これらの事例から、自社でどのような連携が可能か、具体的なイメージを膨らませてみてください。
学生団体が主催する大規模イベントへの協賛は、多くの学生に対して自社の認知度を高め、ブランディングを強化する有効な手段です。例えば、日本最大級の学生イベントである「AGESTOCK」や、ビジネスコンテストの「KING」などは、毎年多くの企業がスポンサーとして参加しています。企業は資金や物品を提供するだけでなく、イベントの企画段階から関わることで、学生とより深い関係を築くことが可能です。
また、学生団体と共同で独自のイベントを企画・開催するケースも見られます。「NEO」や「E4」のようなイベント企画団体と組むことで、学生のリアルなニーズを捉えた魅力的なコンテンツを提供し、企業のファンを増やすことにも繋がります。
学生団体と企業が共同でビジネスコンテストやアイデアコンテストを企画・運営する事例も増えています。例えば、学生団体「夢人」や「MIS」などが主催するイベントに企業がテーマや課題を提供し、学生がその解決策を競い合います。企業は、学生の持つ斬新な視点や柔軟な発想から、自社の事業に役立つアイデアを得られる可能性があります。
また、コンテストの運営プロセスに深く関わることで、参加学生の能力や人柄をじっくりと見極めることができ、優秀な人材の採用にも直結します。学生団体「Sone」や「おりがみ」のように、特定のテーマに特化した団体と連携することで、より専門性の高いコンテストを実施することも可能です。
特定の学生団体と強固な関係を築き、所属学生を対象としたインターンシップや採用選考の特別ルートを設けることも有効な連携方法です。これは、企業が求める能力や資質を持つ学生が多く所属する団体を見極め、的を絞ってアプローチする戦略です。
例えば、特定のスキルを持つ学生が集まる団体や、リーダーシップ経験を積んだ学生が多い団体と連携し、一般公募とは別の選考フローを用意します。これにより、企業は効率的に自社とマッチング度の高い優秀な学生を獲得できます。学生にとっても、自身の活動実績が評価され、キャリアの機会が広がるというメリットがあります。相互にとって有益な関係を築くことで、長期的な人材獲得戦略の柱となり得ます。
本記事では、学生団体が持つ多様な活動内容や、企業が学生団体と連携することで得られる多岐にわたるメリットについて詳しく解説しました。学生団体との連携は、単に学生への認知度を高めるだけでなく、意欲と能力の高い優秀な人材への早期アプローチ、即戦力となるスキルのある学生との出会い、そして団体のネットワークを通じた幅広い層へのブランディングなど、企業の採用活動やマーケティング戦略において非常に有効な手段となり得ます。具体的な接点としては、ポータルサイトでの検索や新卒採用向けスカウトサービスの活用、さらには自社社員の人脈を頼るなど、複数のアプローチ方法が存在します。
また、学生団体との協賛や共同イベントの開催、ビジネスコンテストの企画運営、インターンシップや採用選考における特別ルートの設置など、様々な活用事例を通して、企業が学生団体と連携することで実現できることの幅広さもご理解いただけたのではないでしょうか。貴社が抱える採用課題やブランディングの目標に応じて、学生団体との連携を戦略的に検討し、これからの採用活動や企業成長に繋げていくことをお勧めいたします。


記事公開日 : 2026/01/29
最終更新日 : 2026/01/15
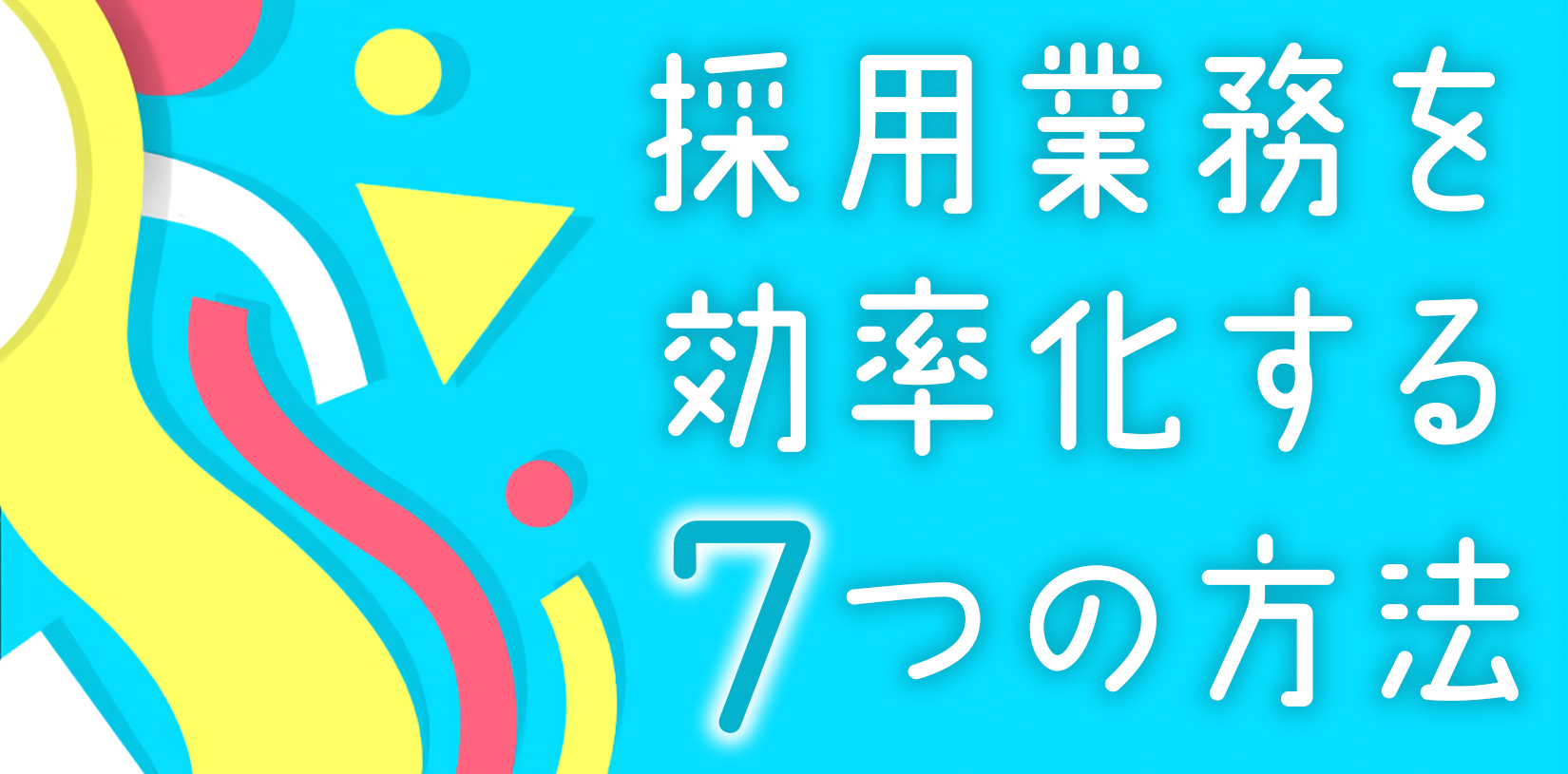
記事公開日 : 2026/01/27
最終更新日 : 2026/01/15
CONTACT