
タイパ抜群!?録画選考の活用法|Z世代に響かせるための動画面接
記事公開日 : 2026/01/29
最終更新日 : 2026/01/15
記事公開日 : 2025/10/20
最終更新日 : 2026/01/15
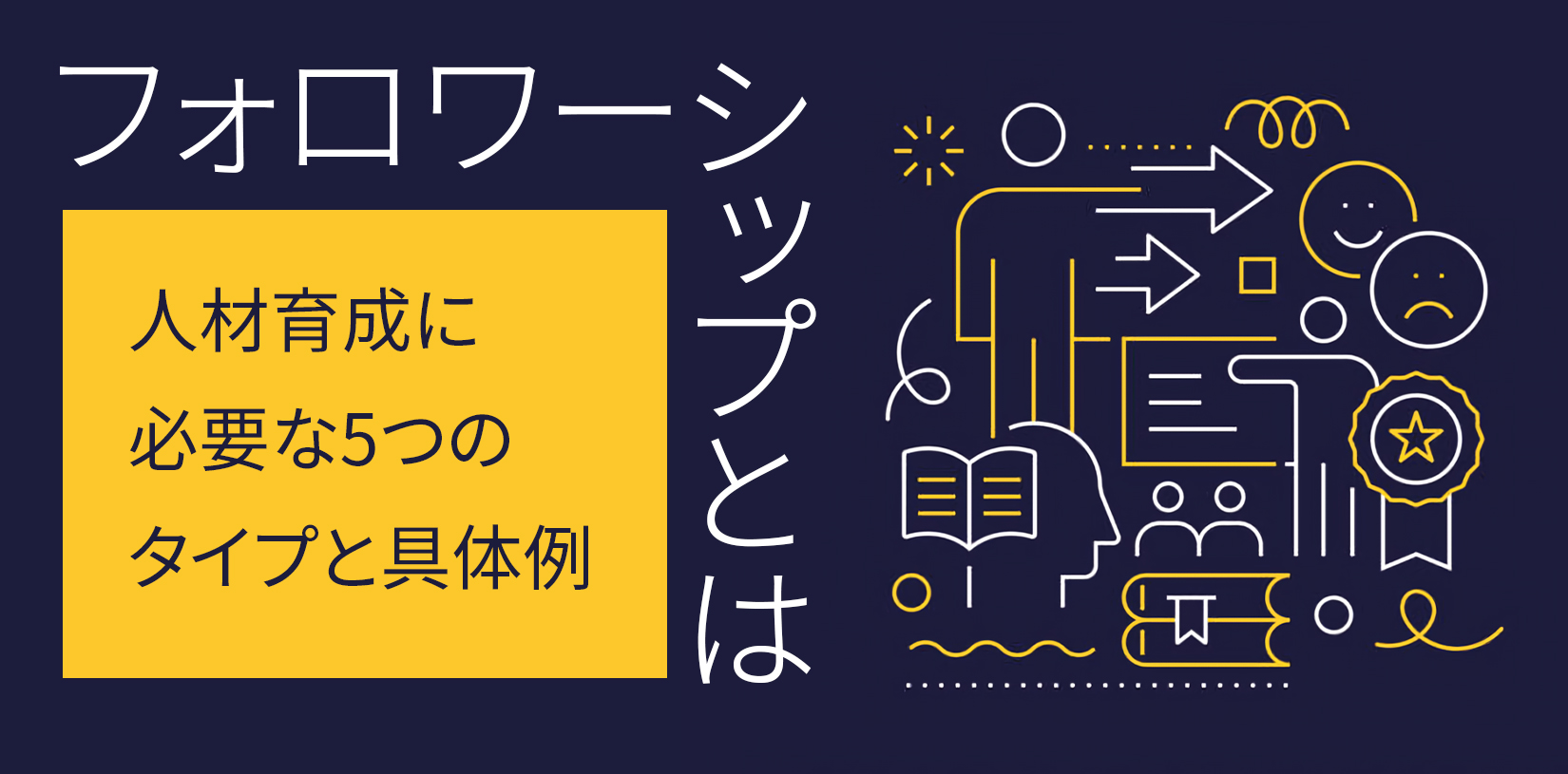
フォロワーシップとは、組織の目標達成に向けてリーダーを主体的に支援する能力を指します。優れたリーダーシップだけでは組織は機能せず、部下の自律的な貢献が不可欠です。
この記事では、フォロワーシップの基本的な考え方から、人材育成における重要性、そして具体的な5つのタイプについて解説します。部下の能力を引き出し、強い組織を作るための育成のヒントを提示します。

フォロワーシップとは、「組織の目標達成に向けてリーダーを主体的に支援する能力」を指します。これは、単にリーダーの指示に従うだけの受動的な行動ではなく、自らが積極的にチームや組織に貢献しようとする能動的な姿勢を意味します。
例えば、リーダーが設定した目標に対し、より良い達成方法を提案したり、他のメンバーが困っている際に自ら助けに入ったりする行動がこれに該当します。この能力は、組織全体のパフォーマンスを向上させるだけでなく、チームメンバー一人ひとりの成長を促す上で非常に重要です。
リーダーシップが組織を牽引する力であるならば、フォロワーシップはそのリーダーを支え、組織の基盤を強化する力と言えるでしょう。この両者が互いに補完し合うことで、組織は最大限の力を発揮できるのです。
現代のビジネス環境において、フォロワーシップの重要性は急速に高まっています。変化の激しい市場で企業が成果を上げ続けるためには、一部のリーダーに依存する組織体制には限界があるからです。特に、多様な価値観が共存する現在の日本企業では、社員一人ひとりの主体的な貢献を引き出す必要性があり、その鍵となるのがフォロワーシップです。この能力の人材育成への導入は、組織全体の力を底上げするために不可欠と言えます。
現代のリーダー、特に部長や上司といった管理職は、複雑化するマネジメントの課題に直面しています。フォロワーが主体的に行動し、リーダーの業務を補佐することで、リーダーは本来注力すべき戦略的な意思決定や重要な課題解決に時間を割けるようになります。さらに、部下からの的確な報告や建設的な提案は、リーダーが状況を多角的に把握するのを助け、意思決定の質そのものを高める効果を持ちます。
ある調査では、マネジメント層の約7割がリーダーシップの発揮に課題を感じているとされており、その背景には業務量の多さや意思決定の重圧があると指摘されています。フォロワーシップは、リーダー個人の能力への過度な依存から組織を脱却させる鍵となり、組織全体の生産性向上にも寄与するでしょう。
フォロワーシップが組織に浸透すると、社員一人ひとりが主体性を持ち、チーム全体の生産性が向上します。リーダーの指示を待つだけでなく、自ら課題を発見して解決策を提案したり、他のメンバーを積極的に支援したりする行動が増えることで、問題解決のスピードが格段に上がり、より質の高い意思決定が可能になります。例えば、予期せぬトラブルが発生した際に、リーダーの指示を待たずに現場のメンバーが自律的に対応し、迅速な解決に貢献するといった効果が期待できます。
また、フォロワーシップはチームワークの向上にも貢献します。 メンバー全員がチームの成功に貢献しようとする意識を持つことで、互いを尊重し協力し合う文化が生まれ、コミュニケーションが活発になります。 このような環境では従業員同士が互いの意見に耳を傾け、協力して業務を進めるため、個々の能力が最大限に発揮されてチーム全体のパフォーマンスが最大化されます。 さらに、自分の意見や行動が組織に貢献しているという実感は、社員のモチベーションを大きく高め、エンゲージメントの向上にも繋がります。 これにより、組織全体の活性化が促進され、生産性も飛躍的に向上します。
フォロワーシップを意識して業務に取り組む経験は、新人や新入社員が優れたリーダーになるための準備期間となります。リーダーを支援する過程で、若手社員は上司の視点や意思決定の背景を学ぶことができるためです。これにより、自らがリーダーの立場になった際に、どのようにチームを導き、後輩を指導すればよいかを具体的にイメージする訓練にもなります。
フォロワーとして優れた人材は、組織の状況を的確に把握し、周囲を巻き込む能力を自然と身につけるため、将来のリーダー候補として育成する上で理想的な土壌が形成されます。多くの企業が次世代のリーダー育成に課題を抱える中で、フォロワーシップの醸成は、組織全体の持続的な成長を支える重要な施策と言えるでしょう。
フォロワーシップはリーダーシップと対極にある概念ではなく、組織の目標達成のために相互に補完しあう関係です。リーダーシップが組織を「導く力」であるのに対し、フォロワーシップはリーダーを「支え、貢献する力」と定義されます。
また、全従業員が持つべき基本的な姿勢を指すメンバーシップという考え方もありますが、フォロワーシップはより能動的・主体的な関与を意味します。優れた組織では、リーダーとフォロワーがそれぞれの役割を最大限に発揮し、協働することで大きな成果を生み出します。
フォロワーシップの概念を提唱したアメリカのカーネギーメロン大学のロバート・ケリー教授は、フォロワーを5つのタイプに分類しました。この5類型は「組織への貢献・批判的思考」と「主体的・積極的関与」の2つの軸で分けられ、それぞれのフォロワーが持つ行動スタイルや特徴を示しています。自身のチームメンバーがどのタイプに当てはまるかを理解することは、個々の強みを活かし、適切な育成を行う上で非常に有効です。
模範型フォロワーは、組織への貢献意欲と主体性を共に高く持ち合わせる、最も理想的なスタイルです。リーダーの方針を理解し、積極的に支援するだけでなく、必要であれば建設的な批判や提言も行います。
このタイプの強みは、自律的に行動し、周囲に良い影響力を与える点にあります。彼らはリーダーの最も頼れる右腕となり、チーム全体のパフォーマンスを牽引する存在です。組織としては、この模範型の人材をいかに育成し、増やしていくかが重要な課題となります。
孤立型フォロワーは、批判的な思考が強い一方で、組織への積極的な関与が低いタイプです。現状に対して冷笑的であったり、方針に反対の立場を取ったりすることが多く、組織内では協調性に欠ける存在と見なされがちです。
しかし、彼らが持つ独自の視点や鋭い批判は、組織が陥りがちな思考停止の状態に警鐘を鳴らし、潜在的なリスクや問題点を浮き彫りにするきっかけを与えることもあります。彼らの意見に真摯に耳を傾け、組織の改善に活かす視点が求められます。
順応型フォロワーは、リーダーの指示に対して忠実に従い、積極的に業務を遂行するタイプです。協調性が高く、組織への貢献意欲もありますが、自らの意見を表明したり、リーダーに異を唱えたりすることはほとんどありません。いわゆる「イエスマン」になりやすく、思考停止に陥る危険性もはらんでいます。
あるレポートによると、組織に属するフォロワーの約8割が、この順応型か後述の消極型に分類されるとされています。主体性を引き出す働きかけが重要です。
消極型フォロワーは、組織への貢献意欲も主体性も低いタイプを指します。与えられた仕事は最低限こなしますが、それ以上の行動を起こすことはありません。指示がなければ動けず、常に受け身の姿勢で業務に臨むため、周囲のメンバーの負担を増やす原因にもなり得ます。
このタイプの従業員に対しては、まず仕事へのエンゲージメントを高め、自らの役割や貢献の意義を理解させるためのアプローチが必要です。小さな成功体験を積ませることが、主体性を引き出す第一歩となります。
実務型フォロワーは、現実的で着実に業務をこなす一方で、現状維持を好む傾向があるタイプです。彼らは組織にとって信頼できる働き手であり、与えられた職務を堅実に遂行します。しかし、新しい取り組みや変革に対しては懐疑的、あるいは消極的な態度を示すことが少なくありません。
この実務型フォロワーの能力を認めつつ、変化への適応を促し、より高いレベルでの貢献を引き出すためのマネジメントが求められます。彼らの経験や知識は、変革を現実的なものにする上で貴重な資源となります。
フォロワーシップの理論を理解するだけでなく、それを日々の業務でどのように発揮するかが重要です。ここでは、フォロワーシップを実践するための具体的な行動の例を3つ紹介します。
これらの実践例は、特別なスキルを必要とするものではなく、意識を変えることで誰でも取り組むことが可能です。部下にフォロワーシップの重要性を伝える際には、こうした具体的な行動レベルに落とし込んで指導することが効果的です。
組織やチームの目標達成という共通の目的に立ち、リーダーの決定や方針に対して、より良い代替案や改善点を提言する行動は、フォロワーシップの核となる要素です。
これは単なる批判や反対ではなく、あくまで組織を良くするための前向きな意見であることが重要です。提言を行う際には、なぜそう考えるのかという根拠を明確にし、相手に配慮した伝え方を工夫するコミュニケーションスキルが求められます。リーダーとフォロワーの間に信頼関係があってこそ、こうした建設的な対話が生まれます。
フォロワーシップを発揮する人材は、単に与えられた役割をこなすだけではありません。組織全体の目標を自分事として捉え、その達成のために今自分に何ができるかを常に考えて行動します。指示を待つのではなく、自ら課題を発見し、解決策を考え、周囲を巻き込みながら実行に移していく姿勢が求められます。 このような主体的な行動は、個人の成長を促すだけでなく、効果的なチームビルディングにも繋がり、組織全体の活力を高める原動力となります。
優れたフォロワーは、リーダーの得意なこと、不得意なことを把握し、その弱みを補うように行動します。自分の業務範囲に固執せず、チーム内で困っているメンバーがいれば積極的に手を差し伸べ、サポートします。
これは、スポーツのチームプレーや介護の現場における連携のように、全体のパフォーマンスを最大化するために不可欠な行動です。互いに補佐し合う文化が根付くことで、チームの一体感と結束力は格段に高まります。
部下のフォロワーシップを高めるためには、個人の意識改革だけでなく、組織としての仕組み作りが不可欠です。具体的には、評価制度の見直しや心理的安全性の確保、そして対話の機会創出などが挙げられます。研修などを通じてフォロワーシップの重要性を伝えると共に、それを実践できる環境を整えることが、育成の鍵となります。
ここでは、フォロワーシップという能力を構成する要素を伸ばすための具体的なポイントを解説します。
多くの企業ではリーダーとしての成果が評価の中心になりがちですが、部下のフォロワーシップを高めるためには、フォロワーとしての貢献を正当に評価する仕組みが必要です。例えば、リーダーへの建設的な提言や他メンバーへのサポートといった行動を評価項目に加えることが考えられます。
このような評価制度は、組織としてフォロワーシップを重視しているという明確なメッセージになります。マッキンゼーの7Sにおける「Shared Value(共通の価値観)」としてフォロワーシップを位置づけ、制度に反映させることが有効です。
部下がリーダーに対して建設的な提言を行うためには、どんな意見を言っても不利な扱いを受けないという安心感、すなわち心理的安全性が確保された職場環境が不可欠です。上司が部下の意見に真摯に耳を傾け、たとえ反対意見であっても一度受け止める姿勢を示すことが重要になります。また、失敗を過度に責めるのではなく、挑戦を推奨する文化を醸成する取り組みも心理的安全性を高めます。
このような職場環境が、主体的なフォロワーシップの発揮を促す土台となります。
定期的な1on1ミーティングは、部下が自身の役割や組織への貢献について深く考える内省の機会となります。上司は対話を通じて、部下の考えや価値観、キャリアプランへの理解を深めることが可能です。このような相互理解は、信頼関係の構築に繋がり、部下がフォロワーシップを発揮しやすい環境を整えます。
ミーティングでは、業務の進捗確認だけでなく、部下の強みや課題について話し合う時間を設けることが有効です。時にはグループワークを取り入れ、多角的な視点から自己理解を深める機会を作るのも良いでしょう。
フォロワーシップが企業文化として根付くと、個人やチームのレベルを超えて、組織全体に多くの好影響がもたらされます。従業員一人ひとりが主体的に組織の目標達成に関与することで、企業の競争力は格段に向上します。
具体的には、チームのパフォーマンス向上、変化への対応力強化、そして従業員エンゲージメントの向上といったメリットが期待できます。これらは持続的な企業成長の基盤となる重要な要素です。
メンバー全員がフォロワーシップを意識し、リーダーを支援し、互いに協力し合う文化が醸成されると、チーム全体のパフォーマンスは飛躍的に向上します。個々の能力が足し算でなく掛け算のように作用し、1+1が2以上になる相乗効果が生まれるからです。課題に対して多角的な視点からアプローチできるようになり、意思決定の質とスピードも高まります。結果として、チームはより高いレベルの目標を達成することが可能になります。
さらに、フォロワーシップが浸透すると、メンバー一人ひとりが生き生きと仕事に取り組むようになり、コミュニケーションが活性化し、生産性向上につながる好循環が生まれます。また、リーダーシップとフォロワーシップは相互に補完し合う関係にあり、どちらか一方だけでは効果が低く、両者が協働することで組織は最大限の成果を発揮できます。このように、フォロワーシップは個人レベルに留まらず、チーム全体のパフォーマンスを最大化するために不可欠な要素と言えます。
現代のビジネス環境は予測困難な変化に満ちており、このような状況において、トップダウンの指示系統だけに依存する組織は、変化への対応が遅れがちです。フォロワーシップが浸透した組織では、現場のメンバーが自律的に課題を発見し、改善提案を行うことが常態化します。これにより、環境変化の兆候をいち早く察知し、迅速かつ柔軟に対応できる組織風土が醸成されます。
例えば、市場のトレンドが変化した際、顧客と直接接する営業担当者がいち早くその変化を察知し、新商品開発チームに具体的な改善案を提案するといった動きが活発になります。こうしたボトムアップの力が、組織のレジリエンス(回復力・適応力)を高めるのです。変化を恐れず、むしろ変化を成長の機会と捉えるような前向きな組織文化は、競争優位性を確立する上で非常に重要です。個々の従業員が主体的に考え、行動することで、組織全体が俊敏性を持ち、持続的な成長を遂げられるようになります。
自分の意見や行動が組織に貢献しているという実感は、従業員の仕事に対するモチベーションを大きく高めます。フォロワーシップの発揮は、このような貢献実感を得る絶好の機会です。結果として、従業員のエンゲージメントが向上し、組織への帰属意識も強まります。
エンゲージメントの高い従業員は、自らの成長と組織の成長を重ね合わせて考える傾向があり、優秀な人材の定着、すなわち離職率の低下に直接的に貢献します。個々の従業員が主体的に組織に関わることで、組織全体が活性化され、それがさらなるエンゲージメント向上と離職率低下に繋がる好循環が生まれるのです。
フォロワーシップは、リーダーを主体的に支援し、組織の目標達成に貢献する能力であり、現代の組織運営において不可欠な要素です。リーダーシップとフォロワーシップは、車輪の両輪のように相互に補完し合う関係にあり、どちらか一方だけでは組織は十分に機能しません。従業員一人ひとりが自身のフォロワーシップのタイプを理解し、最も理想的な「模範型」を目指して行動することで、チーム全体の生産性は向上し、予期せぬ変化にも柔軟に対応できる強い組織が形成されます。
例えば、リーダーが設定した目標に対して、フォロワーが建設的な意見を提案したり、他のメンバーが困っている際に自ら助けに入ったりする行動が、組織全体のパフォーマンスを押し上げる原動力となります。フォロワーシップの育成は、単なるスキル研修にとどまらず、フォロワーとしての貢献を正当に評価する制度の導入や、誰もが意見を言いやすい心理的安全性の高い職場環境の整備を含めた全社的な取り組みとして推進することが求められます。このような取り組みを通じて、従業員は仕事への主体性を高め、エンゲージメントの向上にも繋がり、結果として組織全体の持続的な成長に貢献することが期待できます。


記事公開日 : 2026/01/29
最終更新日 : 2026/01/15
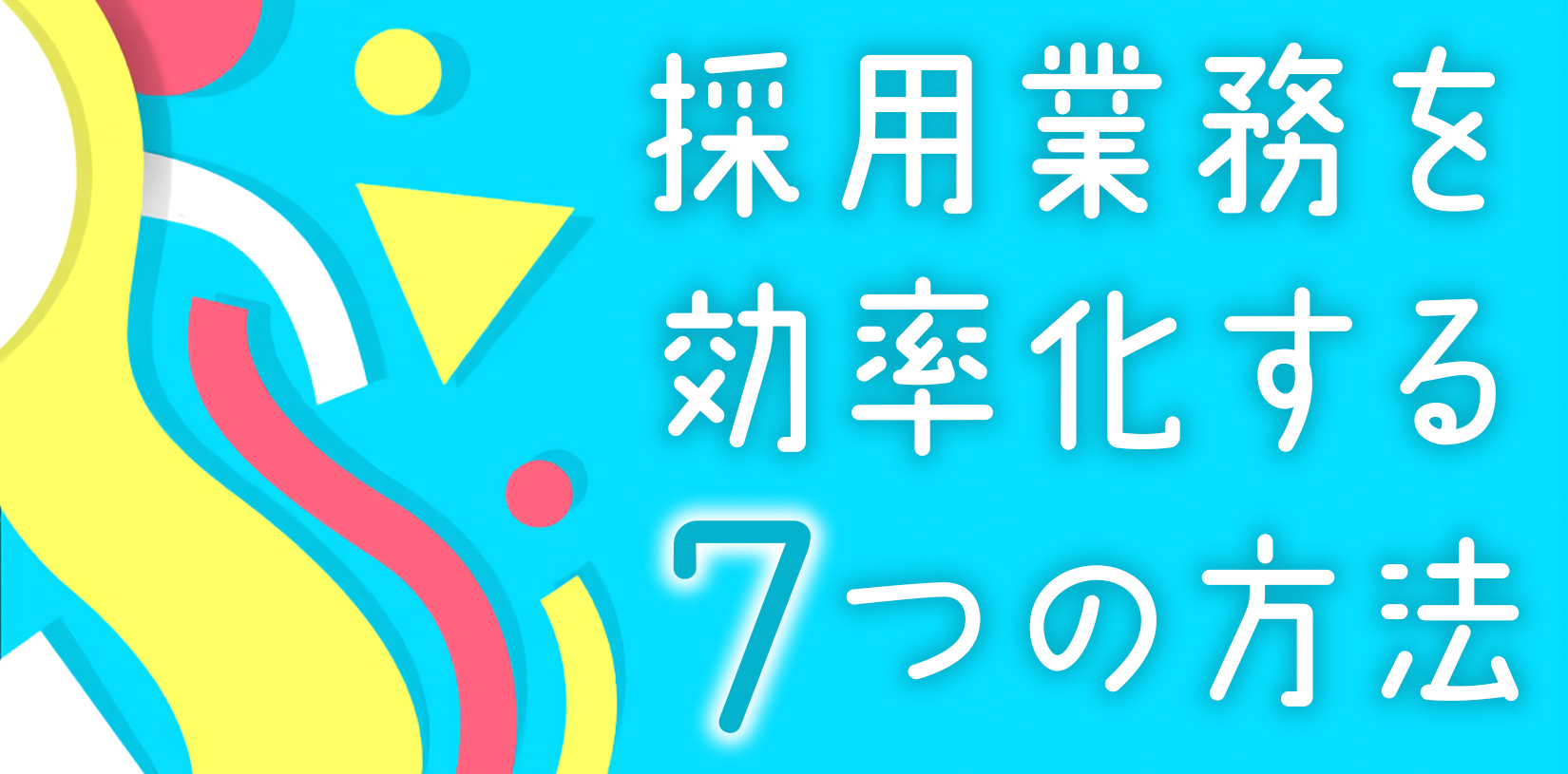
記事公開日 : 2026/01/27
最終更新日 : 2026/01/15
CONTACT