
タイパ抜群!?録画選考の活用法|Z世代に響かせるための動画面接
記事公開日 : 2026/01/29
最終更新日 : 2026/01/15
記事公開日 : 2025/10/17
最終更新日 : 2026/01/15

面接をドタキャンされた場合、企業側は冷静な対応が求められます。
突然のキャンセルに戸惑うかもしれませんが、まずはその理由を把握し、然るべき手順で処理を進めることが重要です。
この記事では、応募者が面接をドタキャンする理由から、企業側が取るべき具体的な対応、そしてドタキャンを未然に防ぐための対策までを詳しく解説します。
状況に応じたメール例文も紹介するため、採用活動の参考にしてください。

応募者が面接をドタキャンする背景には、様々な理由が存在します。
他社の選考が進んだといった応募者側の事情が多い一方で、企業側の対応が原因でドタキャンしてしまったというケースも少なくありません。無断キャンセルはマナー違反ですが、その背景を理解することで、自社の採用活動を見直すきっかけにもなります。
ここでは、ドタキャンに至る主な理由を5つの観点から解説します。
就職活動や転職活動では、複数の企業へ同時に応募することが一般的です。
そのため、自社よりも志望度が高い他社から先に内定が出た場合、応募者はそちらへの就職を決め、以降に予定されていた他社の選考を辞退することがあります。
特に優秀な人材であるほど多くの企業から内定を得る傾向があるため、選考の途中で辞退者が出ることは避けられません。辞退の連絡を入れずにドタキャンしてしまうのは、申し訳なさから連絡しづらいと感じたり、単純に連絡を忘れてしまったりすることが原因として考えられます。
indeedやマイナビといった求人サイトに掲載されていた情報と、応募後のやり取りや面接で提示された条件に乖離がある場合、応募者は企業に対して不信感を抱き、選考を辞退する可能性があります。
特に、給与や休日、勤務地、業務内容といった重要な項目で食い違いがあると、志望度は大きく低下します。求人情報で魅力的な条件を提示しておきながら、実際には異なる内容を伝えるようなことがあれば、企業の信頼を損なうことになります。
応募者が不誠実だと感じた場合、連絡をせずにドタキャンという形で意思を示すケースもあります。
応募から面接に至るまでの過程で、企業の対応に不満を抱いたことがドタキャンの引き金になる場合があります。
例えば、書類選考の結果連絡が遅い、メールの文面が不親切、面接日程の調整が一方的であるなど、応募者への配慮に欠ける対応は志望度を著しく下げてしまいます。
応募者は選考を通じて、その企業で働く自身の姿を想像するため、ぞんざいに扱われたと感じると「入社後も同じような対応をされるのではないか」と不安になります。結果として、その企業で働く意欲を失い、面接を辞退することを選択するのです。
応募した時点では魅力を感じていた会社でも、その後に口コミサイトやSNSなどでネガティブな評判を目にして志望度が下がるケースがあります。
現職の社員や元社員による働きがい、労働環境、人間関係などに関する書き込みは、応募者の意思決定に大きな影響を与えます。特に、面接を控えた段階で悪い評判を知ると、面接を受けること自体をためらうようになることも少なくありません。
「この会社で働くのは避けたい」と判断した場合、連絡をせずに面接を欠席するという行動につながる可能性があります。
応募者本人に悪意はなく、やむを得ない事情で結果的にドタキャンとなってしまうケースも存在します。
例えば、面接当日の朝に急な体調不良に見舞われたり、事故や悪天候による交通機関の大幅な遅延に巻き込まれたりする場合です。
このような緊急事態では、落ち着いて企業に連絡を入れる余裕がないことも考えられます。また、身内の不幸といった予期せぬトラブルも同様です。後日、応募者から謝罪と事情説明の連絡が来る可能性もあるため、連絡がないからといって一方的に不誠実だと決めつけるのは早計です。
面接の予定時刻を過ぎても応募者が現れない場合、企業側は冷静かつ適切な対応をすることが求められます。まずは状況を確認するための連絡から始め、応募者の事情に応じて次のアクションを判断していく必要があります。
無断でのキャンセルであっても感情的にならず、あらかじめ決められた手順に沿って事務的に処理を進める姿勢が重要です。
面接の予定時刻を過ぎても応募者が来ない場合、まずは電話をかけて状況を確認します。道に迷っている、交通機関の遅延に巻き込まれているといったトラブルの可能性も考えられるためです。
電話に出ない場合は、メールでも連絡を入れておくとよいでしょう。メールには、面接に来られていない旨と、もし何か事情があれば返信してほしいという内容を記載します。高圧的な文面は避け、あくまで安否や状況を気遣う姿勢を示すことで、やむを得ない事情があった応募者も連絡しやすくなります。
応募者から連絡があり、体調不良や交通機関の遅延といった、やむを得ない事情によるキャンセルであったことが判明した場合、面接日程の再調整を検討します。応募者の入社意欲が高いと判断できるのであれば、再度面接の機会を設けることで、優秀な人材を確保できる可能性が残ります。
ただし、再調整を打診するかどうかの基準は、あらかじめ社内で統一しておくと判断に迷いません。例えば、「本人から明確な謝罪と再設定の希望があった場合のみ対応する」といったルールを設けておくと、対応に一貫性を持たせられます。
電話やメールで連絡を試みても応募者から一切返信がない場合は、選考辞退とみなし、不採用として処理を進めます。何度も連絡を試みる必要はなく、一定期間(例えば1〜2日)を過ぎても応答がなければ、次の採用活動に切り替えるのが合理的です。
この際、不採用通知を送るかどうかは企業の判断によりますが、応募書類の取り扱いなどを明記した通知を送付しておくと、後のトラブルを避けやすくなります。応募者からの連絡を待ち続けることは採用活動全体の遅延につながるため、見切りをつけることも必要です。
面接をドタキャンした応募者への連絡は、その後の状況に応じて文面を使い分ける必要があります。やむを得ない事情が確認でき、再度面接の機会を設ける場合と、連絡が取れず不採用として処理する場合とでは、伝えるべき内容が異なります。
ここでは、それぞれの状況に応じたメール例文を紹介しますので、自社の状況に合わせて調整し活用してください。
件名:【株式会社◯◯採用担当】面接日程の再調整のご案内
◯◯様
株式会社◯◯採用担当の△△です。
先日は、面接にお越しになれなかったとのこと、承知いたしました。
その後、お変わりございませんでしょうか。
もし、引き続き弊社の選考をご希望でしたら、再度面接日程を調整させていただきたいと考えております。
つきましては、ご都合のよろしい日時をいくつかお教えいただけますでしょうか。
◯◯様からのご連絡をお待ちしております。
件名:【株式会社◯◯採用担当】選考結果のご連絡
本文:
◯◯様
株式会社◯◯採用担当の△△です。
先日ご予約いただいておりました面接の件につきまして、ご連絡いたしました。
◯月◯日◯時より面接を実施予定でございましたが、当日お越しになられず、また、弊社からの連絡にご返信がなかったため、誠に勝手ながら今回はご辞退されたものと判断いたしました。
お預かりした応募書類につきましては、弊社規定に基づき責任をもって破棄いたします。
末筆ながら、◯◯様の今後のご活躍を心よりお祈り申し上げます。
この不採用通知メールのポイントは、辞退と判断した経緯を客観的に記載し、応募書類の取り扱いについても明記してトラブルを未然に防ぐ点にあります。
面接をドタキャンした応募者へメールを送る際には、いくつか注意すべき点があります。特に、連絡のタイミングと応募書類の取り扱いについては、明確に伝えることが重要です。
新卒・中途採用を問わず、これらの配慮を怠ると、企業のイメージダウンや後のトラブルにつながる可能性も考えられます。慎重な対応が求められます。
応募者への連絡は、適切なタイミングで行うことが肝心です。例えば、面接当日に連絡が取れなかった場合、すぐに不採用通知を送るのではなく、1日程度は応募者からの連絡を待つのが望ましいでしょう。応募者側にもやむを得ない事情で連絡が遅れている可能性を考慮する必要があります。
一方で、面接の前日などにリマインドメールを送る場合は、応募者が予定を再確認するのに十分な時間を確保できるタイミングが効果的です。連絡が早すぎても遅すぎても効果が薄れるため、状況に応じたタイミングを見計らうことが求められます。
不採用を通知する際には、提出された応募書類(履歴書や職務経歴書など)をどのように取り扱うかを明確に記載することが不可欠です。個人情報保護の観点からも、応募書類の扱いを明示する義務があります。
「弊社規定に基づき責任をもって破棄いたします」と記載するのが一般的ですが、返却を希望される可能性も考慮し、企業のポリシーをあらかじめ定めておくとよいでしょう。
採用活動において預かった個人情報を適切に管理している姿勢を示すことは、企業の信頼性を保つ上で非常に重要です。
一度面接をドタキャンした応募者から、後日になって再度応募が来るケースも考えられます。2回目以降の応募にどう対応するかは、企業の方針によって異なりますが、過去の経緯を踏まえつつも、一貫性のある採用基準で判断することが求められます。
ここでは、再応募があった際の具体的な対応方針について解説します。
再応募があった際は、まず過去の応募履歴を必ず確認します。以前の応募で面接を無断でキャンセルした事実があるのなら、その経緯を考慮して選考に進めるかどうかを慎重に判断する必要があるからです。
応募者管理システムなどを活用し、過去の選考記録を正確に把握できる体制を整えておくことが望ましいです。やむを得ない事情があったのか、あるいは誠実さに欠ける応募者なのかを見極めるためにも、記録の確認は不可欠なプロセスです。その上で、今回の応募を受け付けるかどうかの判断を下します。
過去にドタキャンした応募者への対応については、明確なルールを設けておくことが重要です。「いかなる理由であれ、一度でも無断キャンセルした応募者は選考対象外とする」という厳しい方針もあれば、「事情を考慮し、再応募の機会を与える」という柔軟な方針も考えられます。どちらが正しいというわけではなく、自社の採用基準として一貫性を保つことが求められます。
特に転職市場では、様々な背景を持つ候補者が応募してくるため、場当たり的な判断は不公平感を生む可能性があります。一貫した基準を持つことで、採用活動の公平性と信頼性を担保できます。
面接のドタキャンは、採用担当者にとって大きな負担となりますが、企業側の工夫次第で発生率を低減させることが可能です。応募者の志望度を高め、辞退の連絡をしやすい関係性を築くことがドタキャンを防ぐ鍵といえます。
ここでは、ドタキャンを未然に防ぐための具体的な6つの対策を紹介します。
応募者からの問い合わせへの返信や、書類選考結果の連絡は、可能な限り迅速かつ丁寧に行うことが基本です。連絡が遅れると、応募者は「自分は重要視されていないのではないか」と感じ、志望度が低下する原因になりかねません。
また、メールの文面も重要であり、定型文をそのまま送るのではなく、応募者の名前を個別に入れるなど配慮した内容にすることで好印象を与えられます。
迅速で誠実なコミュニケーションを重ねることで応募者との信頼関係が構築され、ドタキャンされるリスクを減らせます。
面接日程を調整する際は、企業側の一方的な都合で日時を指定するのではなく、複数の候補日を提示して応募者に選んでもらう形式が望ましいです。特に、在職中の応募者や、アルバイトを掛け持ちしている学生などは、平日の日中に時間を確保するのが難しい場合があります。
候補者の都合に配慮した柔軟な対応を示すことで、「応募者に寄り添ってくれる企業だ」という印象を与えられ、志望度を高める効果が期待できます。日程調整の段階から良好なコミュニケーションを心がけることが、ドタキャン防止に役立ちます。
面接の前日に、確認のためのリマインド連絡を入れることは、ドタキャン防止に非常に効果的です。メールやSMSなどを利用して、面接日時、場所(Web面接の場合はURL)、持ち物、担当者名などを改めて伝えることで、応募者のうっかり忘れを防ぎます。
また、このリマインド連絡は、応募者にとって辞退の連絡をする最後のきっかけにもなり得ます。
もし辞退の意思があれば、このタイミングで連絡をもらえることで、企業側も無駄な準備をせずに済みます。自動送信ツールなどを活用すれば、採用担当者の負担を増やさずに実施可能です。
応募から面接までの期間が長引くと、その間に応募者の熱意が冷めたり、他社の選考が進んでしまったりするリスクが高まります。選考フロー全体を見直し、不要なステップを省略したり、オンラインツールを活用したりして、リードタイムを短縮することが重要です。
例えば、書類選考の結果連絡を早め、すぐに一次面接の日程を調整するなどの工夫が考えられます。スピーディーな選考は、応募者に「選考が早く進む魅力的な企業」という印象を与え、志望度を維持する上で効果的です。
遠方に住んでいる応募者や、在職中で時間の制約がある応募者にとって、指定された場所へ赴く対面面接は負担が大きい場合があります。Web面接(オンライン面接)を導入すると、応募者は場所を選ばずに面接に参加できるようになり、参加のハードルが大きく下がります。移動時間や交通費がかからないことは、応募者にとって大きなメリットです。
面接形式の選択肢を増やすことは応募者の負担を軽減し、結果的にドタキャン率の低下に結びつきます。一次面接はWeb、最終面接は対面といったように、選考フェーズに応じて使い分けるのも有効な手段です。
応募者が「この企業で働きたい」と強く思うようになれば、安易にドタキャンする可能性は低くなります。そのためには、採用サイトやSNS、説明会などを通じて、企業の魅力を積極的に発信し、応募者の志望度を高める努力が不可欠です。
仕事内容や待遇といった条件面だけでなく、企業文化や働く社員の様子、社会への貢献度など、共感を呼ぶ情報を伝えることが重要になります。応募者が企業のファンになるような情報発信を心がけることで他社との差別化を図り、選考プロセスにおけるエンゲージメントを高められます。
面接のドタキャンは、採用担当者にとって避けたい事態ですが、万が一発生した際には冷静かつ適切な対応が求められます。ドタキャンされた場合は、まず応募者の状況を確認し、事情に応じて日程の再調整や不採用処理を行います。
しかし、より重要なのは、ドタキャンを未然に防ぐための対策を講じることです。
企業側が応募者への迅速で丁寧な連絡を心がけ、選考フローを見直し、企業の魅力を積極的に発信することで応募者の志望度を高め、ドタキャン率を低下させることが可能です。これらの対策を通じて、採用活動を円滑に進めることができます。


記事公開日 : 2026/01/29
最終更新日 : 2026/01/15
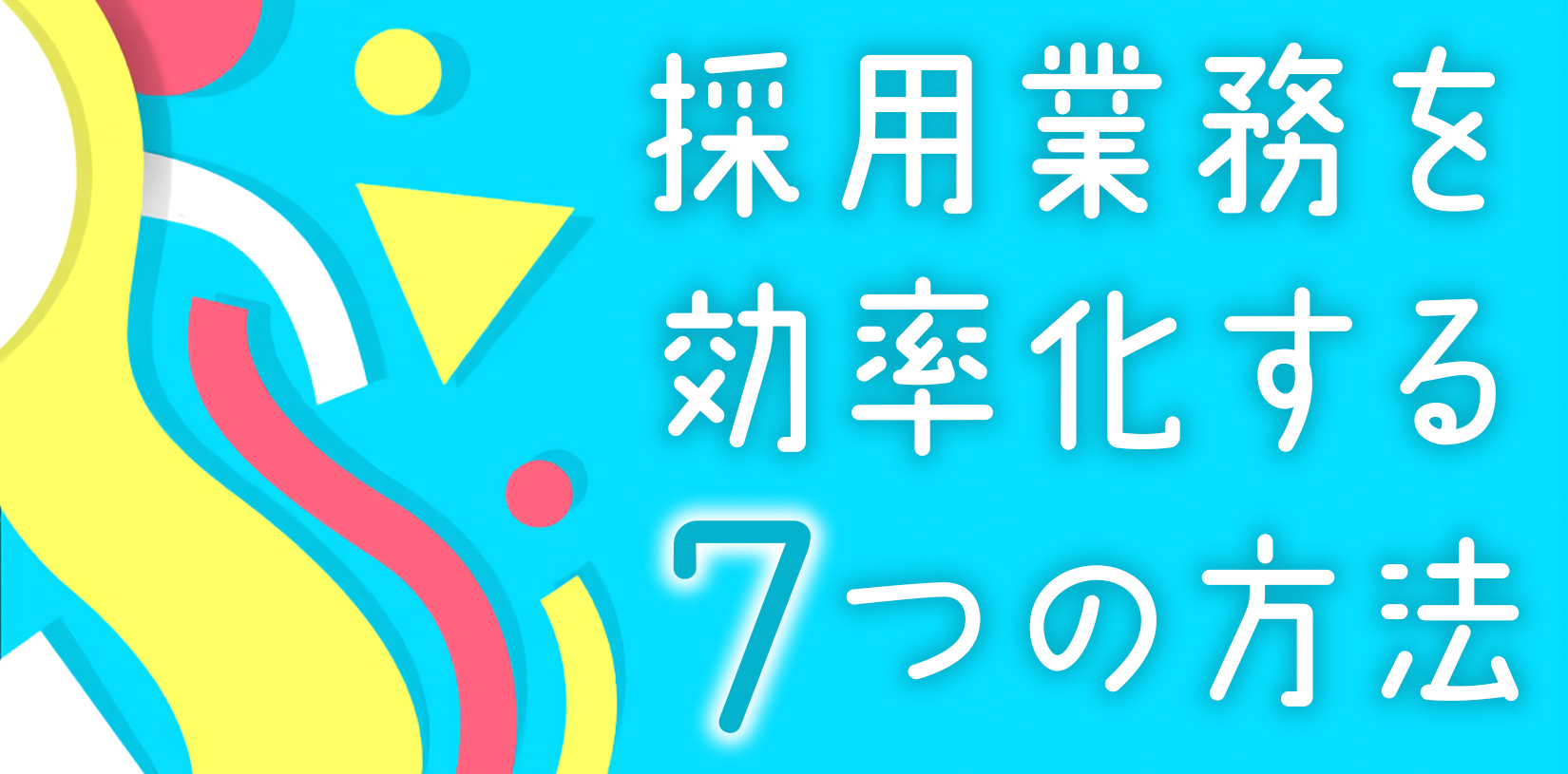
記事公開日 : 2026/01/27
最終更新日 : 2026/01/15
CONTACT