
【福利厚生としても注目!】近年話題のキャリアブレイクとは?
記事公開日 : 2026/01/16
最終更新日 : 2026/01/15
記事公開日 : 2025/10/24
最終更新日 : 2026/01/15
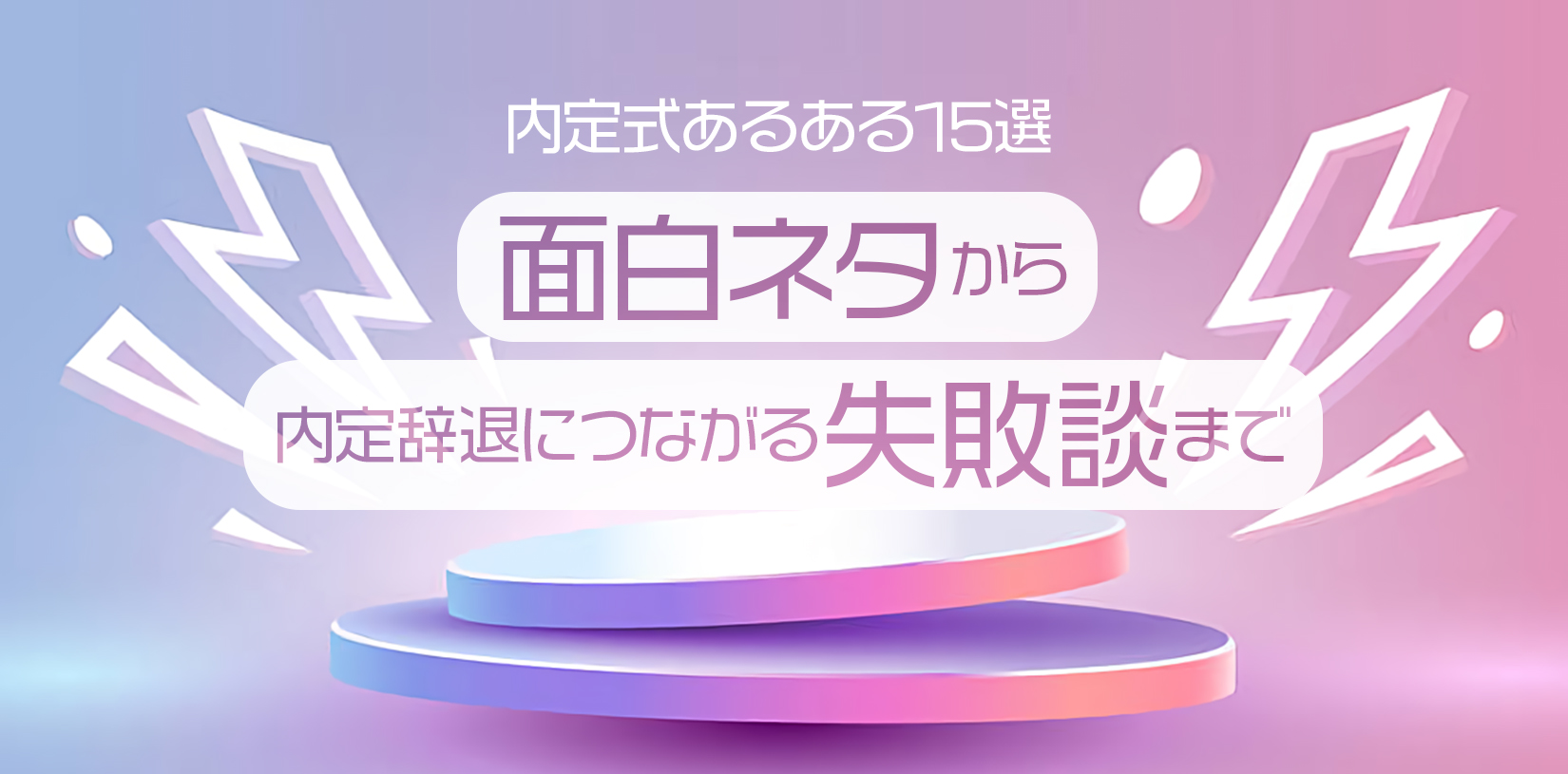
内定式は、社会人になる前の大きなイベントの一つです。多くの内定者が集まるこの式典では、期待と不安が入り混じる独特の雰囲気の中、思わず共感してしまうような出来事が起こりがちです。
この記事では、学生が体験する「面白あるある」から、企業側が注意すべき「NGあるある」まで、合計15の事例を紹介します。

内定式は緊張する場面も多いですが、後から振り返ると笑えるような「あるある」な出来事もたくさん起こります。初めて会う同期との交流や、普段は接することのない役員との対面など、独特の環境だからこそ生まれる共感必至のシチュエーションを紹介します。多くの内定者が同じような経験をしていると知ることで、少し肩の力が抜けるかもしれません。
ここでは、そんな内定式の微笑ましい一面を覗いてみましょう。
内定式では、会社のトップである社長や役員から直接話を聞ける貴重な機会が設けられています。企業の理念や歴史、内定者への期待などが語られますが、その話が予想以上に長くなることは珍しくありません。午前中から始まる式典の緊張感や慣れないスーツの窮屈さも相まって、徐々に強烈な眠気に襲われます。
特に、会場の照明が少し暗かったり、暖房が効きすぎたりしていると、眠気との戦いはさらに過酷になります。必死に目を開けようとしたり、姿勢を正してみたりと、意識を保つための静かな格闘が繰り広げられる光景は、内定式の定番です。
内定者同士が初めて顔を合わせる自己紹介の時間は、内定式の定番プログラムです。ほとんどの人が当たり障りのない内容で終える中、時折、非常に個性的でインパクトの強い同期が現れます。
例えば、マイナーなスポーツの全国大会出場経験者や、驚くような特技を持つ人、あるいはユニークな経歴の持ち主など、その自己紹介に会場全体が引き込まれることがあります。そうした人物の登場によって、場の空気が和む一方で、自分の自己紹介が平凡に感じてしまうことも。これから一緒に働く仲間たちの多様な一面を知る、面白い瞬間です。
内定者同士の交流を深める目的で、グループワークが実施されることがあります。短い時間で成果を出すことが求められる中、必ずと言っていいほど積極的に議論をリードしようとする人が登場します。タイムキーパーや書記、発表者などの役割を率先して決め、意見をまとめようと働きかけるその姿は非常に頼もしく見えます。
一方で、その進行が強引すぎると、他のメンバーが発言しづらい雰囲気になってしまうことも。こうした仕切りたがる人の存在は、チームで何かを進める上での人間模様を垣間見せる、グループワークならではのあるあるです。
式典が終わった後の懇親会は、社員や同期と自由に話せる貴重な機会です。しかし、立食形式の場合、すでに出来上がっている会話の輪にうまく入れず、どのテーブルに行けば良いか分からなくなり、会場内をうろうろしてしまうことがあります。
料理が置いてあるテーブルとドリンクコーナーを何度も往復したり、スマホを触るふりをして時間を潰したりと、手持ち無沙汰な時間を経験する内定者は少なくありません。まずは近くにいる一人でいる人に声をかけたり、人事担当者に話しかけたりするのが、気まずい状況を打開するきっかけになります。
選考中は評価する側とされる側という関係性だった人事担当者が、内定式では非常にフレンドリーに接してくれるようになります。「これからは仲間だから、何でも気軽に聞いてね!」と気さくに話しかけてくれるため、緊張がほぐれて安心感を覚える学生は多いです。
しかし、その言葉を真に受けて、給与や残業時間といった踏み込んだ質問をしても良いものか、一瞬ためらってしまうことも。ですがこの声掛けは学生の不安を取り除き、会社に馴染んでもらおうという企業側の配慮の表れであり、素直に質問することで会社の雰囲気を知る良い機会となります。
内定式のメインイベントである内定証書授与。大勢の役員や同期が見守る中、一人ずつ名前を呼ばれて登壇し、証書を受け取るという一連の流れは、独特の緊張感に包まれています。
普段行わないような丁寧なお辞儀の角度や、証書の両手での受け取り方などを意識しすぎるあまり、まるでロボットのようにカクカクとした不自然な動きになってしまうことがあります。歩き方からお辞儀、着席までの一挙手一投足がぎこちなくなり、後から写真や動画で見返して自分の硬さに苦笑いするのも、よくある話です。
内定式の最後には、役員や社員、同期全員での記念撮影が行われるのが一般的です。しかし、長時間の式典による疲れと、大勢の人の前で写真を撮られるという緊張から、自然な笑顔を作ることができず、顔が引きつってしまうことがよくあります。
「はい、笑ってー!」というカメラマンの声に応えようとしても、口角は上がっているのに目が笑っていなかったり、頬が痙攣したりすることも。後日、出来上がった写真を見て、自分の不自然な表情にがっかりするまでが内定式のセットです。
内定式では、思わぬハプニングや準備不足から「やってしまった」と感じる失敗も起こりがちです。多くの内定者が経験するこれらの失敗談を事前に知っておくことで、当日の焦りを減らし、落ち着いて対応できるようになります。
服装の選択ミスから、自己紹介での失態、懇親会での振る舞いまで、よくある失敗例を反面教師として、万全の態勢で内定式に臨むための準備をしましょう。
大勢の同期や社員の前で行う自己紹介は、想像以上に緊張するものです。事前に話す内容をしっかりと準備していても、いざ自分の番になると頭が真っ白になり、何を話すつもりだったか完全に忘れてしまうケースは少なくありません。しどろもどろになったり、言葉に詰まって気まずい沈黙が流れたりすると、余計に焦りが募ります。
こうした事態を避けるためには、伝えたい要点をまとめたメモを用意しておくと安心です。万が一内容が飛んでしまっても、慌てずに名前と意気込みだけでも伝えられれば問題ありません。
企業からの案内に「服装自由」や「私服でお越しください」と書かれていた場合、その解釈に頭を悩ませる内定者は多いです。言葉通りにカジュアルな服装で参加したところ、周囲は皆スーツやオフィスカジュアルで、自分だけが明らかに場違いな雰囲気になってしまうという失敗は頻繁に起こります。逆に、リクルートスーツで参加したら、自分以外は全員ラフな私服だったというパターンも。
企業のカルチャーによって適切な服装は異なるため、迷った場合は人事担当者に事前に確認するか、ジャケットを羽織るなど、どちらの状況にも対応できる服装を選ぶのが賢明です。
内定式の緊張感から解放される懇親会では、お酒も手伝って気分が高揚しがちです。社員や同期と打ち解ける良い機会ですが、自分の許容量を超えてお酒を飲んでしまうと、思わぬ失態につながる危険性があります。リラックスしすぎた結果、社会人として不適切な発言をしてしまったり、社員に対して馴れ馴れしい態度をとってしまったりするケースも。
楽しい雰囲気であっても、あくまで会社の公式なイベントであることを忘れず、節度を持った行動を心がけることが、社会人としての第一歩となります。
内定式の中で設けられる社員との質疑応答の時間や懇親会は、入社意欲を示す絶好のチャンスです。そのため、事前に会社の事業内容や働き方について質問を用意していく内定者は多いですが、いざ質問しようとしたら、他の同期に同じ内容を先に質問されてしまうことがあります。特に、誰もが気になりそうな質問は被りやすく、自分の番が来た時にはもう聞くことがなくなっていた、という状況も。
こうした事態に備え、質問は複数パターン用意しておくか、他の人の質問内容を発展させた、より深い質問を投げかけるといった工夫が求められます。
内定式は学生生活の集大成ともいえる記念すべき日であり、その様子を写真に収めてSNSで報告したいと考えるのは自然なことです。しかし、写真撮影に夢中になるあまり、周囲への配慮が欠けてしまうのは問題です。
式の最中にスマートフォンのカメラを構えたり、同期との交流よりも写真映えを優先したりする態度は、他の参加者に不快感を与える可能性があります。また、会社のロゴや資料、他の内定者が写り込んだ写真を無断で公開することは、情報管理の観点からも避けるべきです。まずはその場の雰囲気を楽しみ、交流することを最優先に考えましょう。
企業にとって内定式は、内定者の入社意欲を高め、内定辞退を防ぐための重要なイベントです。しかし、その運営方法によっては、学生をがっかりさせ、逆に入社への不安を煽ってしまう結果になりかねません。
学生は内定式の様子から、その企業の文化や体質を敏感に感じ取っています。ここでは、学生の視点から見て「この会社で大丈夫だろうか」と不安に思わせてしまう、企業側のNGな「あるある」を3つ紹介し、内定者フォローの改善点を探ります。
内定式の運営がスムーズでないと、学生は会社の仕事の進め方そのものに不安を感じます。例えば、受付が混乱していて開始時間が大幅に遅れたり、プログラムの進行が滞って待ち時間が頻繁に発生したり、音響や映像の機材トラブルが続いたりする状況は、準備不足の印象を与えます。社員同士の連携が取れておらず、誰に何を聞けば良いのか分からないといった状態も、学生の不信感を招きます。
当日の進行を円滑にするための入念なリハーサルや、役割分担の明確化は、学生に歓迎の意を示す上で不可欠な要素です。
内定者にとって、内定式で会う社員や役員は、入社後の会社の雰囲気を判断する重要な指標となります。その社員たちの態度が横柄であったり、学生に対して上から目線の言動が見られたりすると、学生は入社後の人間関係に強い不安を覚えます。
特に、懇親会の場で社員が内輪だけで盛り上がり、孤立している学生を放置するような態度は、学生に「歓迎されていない」と感じさせてしまいます。役員からの話も、一方的な訓示に終始するのではなく、学生の目線に立った温かいメッセージを伝えることが、エンゲージメントの向上につながります。
社長や役員からのメッセージは、学生にとって企業のビジョンを知る貴重な機会です。しかし、その内容が「気合」「根性」「成長意欲」といった抽象的な精神論に偏り、具体的な事業戦略や今後の展望が語られない場合、学生は会社の将来性に疑問を抱きます。
入社後にどのようなキャリアを築けるのか、会社がどのような方向に進んでいくのかを具体的にイメージできなければ、入社へのモチベーションは低下します。データや事実に基づいた事業説明や、若手社員の活躍事例などを交えながら、会社の未来を具体的に示すことが学生の不安を払拭します。
内定式で起こりがちな「あるある」を、学生向けと企業向けの両方の視点から紹介しました。学生にとっては、多くの人が同じような経験をすることを知ることで、過度な緊張を和らげることができます。事前の準備とマナーへの配慮を忘れずに、同期や社員との交流を楽しむ心構えで臨むことが望ましいです。
一方、企業にとっては、内定式が学生の入社意欲を左右する重要な機会であることを認識し、運営の細部にまで配慮することが求められます。学生の不安を取り除き、歓迎の気持ちが伝わるような丁寧な企画と運営が、双方にとって有意義な内定式を実現します。


記事公開日 : 2026/01/16
最終更新日 : 2026/01/15
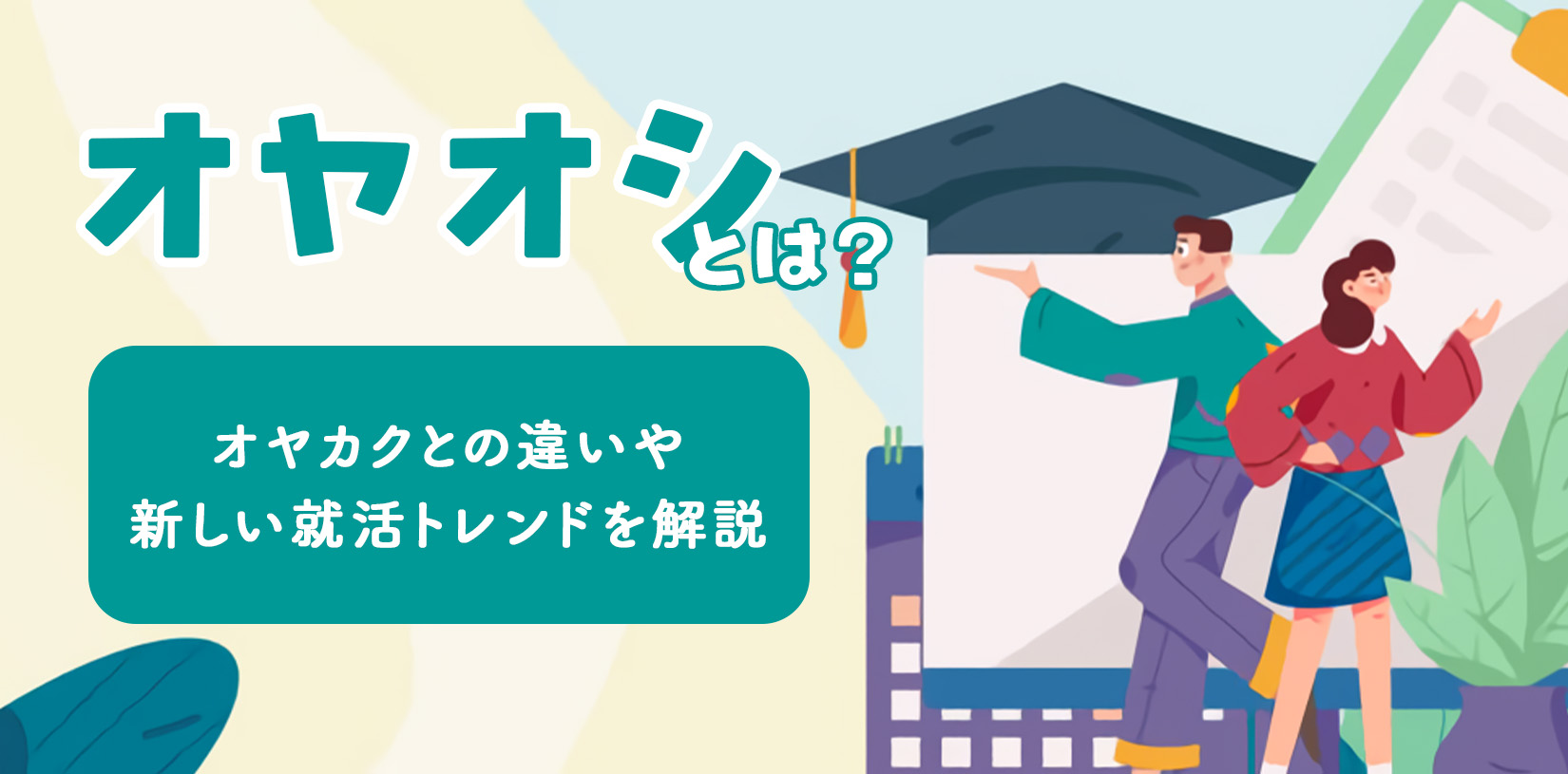
記事公開日 : 2026/01/13
最終更新日 : 2026/01/15
CONTACT