
【福利厚生としても注目!】近年話題のキャリアブレイクとは?
記事公開日 : 2026/01/16
最終更新日 : 2026/01/15
記事公開日 : 2025/08/22
最終更新日 : 2026/01/15
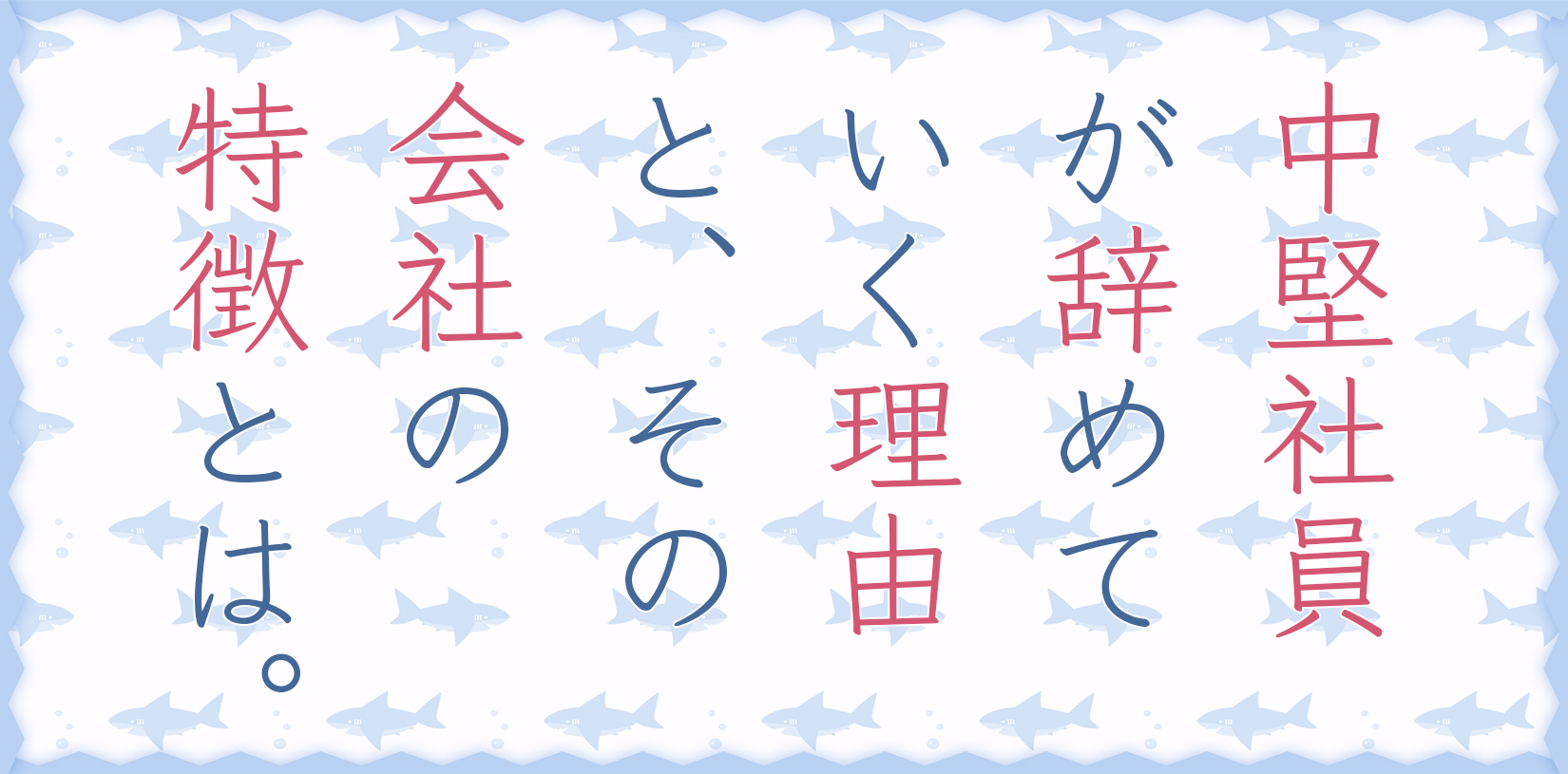
中堅社員の退職は、企業にとって深刻な問題であり、その理由と企業が抱える特性には密接な関係があります。中堅社員は、一般的に入社3年目から15年目程度の社員を指し、現場での中心的な役割を担い、新人や若手の育成にも欠かせない存在です。彼らが退職を選ぶ理由は多岐にわたり、単なる個人的な事情だけでなく、企業の組織文化や制度、マネジメント体制といった要因が大きく影響しています。
本記事では、中堅社員が退職に至る主な理由と、離職が多い企業に共通する特徴を深掘りし、その影響と対策について具体的に解説します。

中堅社員が辞めていくことは、企業に多大な損失をもたらします。彼らは業務の中心を担うだけでなく、若手の指導や育成にも関わる重要な存在であり、その離職は組織全体の機能不全を引き起こす可能性があります。
中堅社員の退職は、残された社員の士気を低下させ、職場の雰囲気を悪化させる要因となります。特に、信頼されていた中堅社員が退職すると、「この会社に残り続けても良いのか」といった疑問や不安が他の社員に広がる可能性があります。結果として、職場全体のモチベーションが低下し、ネガティブな空気が蔓延することで、生産性の低下にもつながることが考えられます。
中堅社員は、実務経験が豊富で業務を円滑に進める上で中心的な役割を担っているため、彼らが退職すると、残された社員への業務負担が増大し、業務遂行が困難になります。特に、退職した中堅社員が多くの業務を抱えていた場合、残された社員がその業務を引き継ぐことで、業務量と難易度が高まり、不満やストレスが溜まりやすくなります。これにより、業務がスムーズに回らなくなり、生産性の一時的な低下は避けられないでしょう。
優秀な中堅社員の退職は、他の社員にも影響を及ぼし、退職が連鎖する可能性があります。特に、「この人がいるから続けられる」と周囲から信頼されていた中堅社員が退職した場合、若手社員や周囲の中堅社員にも離職が波及することが考えられます。転職が珍しくない現代において、会社への不満やキャリアへの不安、人間関係が原因で退職した場合、周囲に悪影響を及ぼし、さらなる退職者を生む悪循環に陥る危険性があります。
中堅社員の離職は、新たな人材の採用と再教育に多大な費用をもたらします。中堅社員は、新入社員から自走できるまでに育成するのに大きなコストがかかっており、彼らが抜けることで、その教育コストが無駄になります。さらに、同等のスキルと経験を持つ人材を見つけることは容易ではなく、採用活動にかかる費用はもちろんのこと、採用した人材を中堅社員レベルにまで育成するための教育コストも莫大になります。ノウハウの喪失により、業務の引き継ぎにも時間がかかり、結果的に企業の経済的な負担が増大するのです。
中堅社員が退職を選ぶ理由には、個人のキャリア観やライフスタイルの変化に加え、企業内部の課題が深く関係しています。彼らが抱える不満や不安は、時に表面化しにくく、経営層が見過ごしがちな本質的な問題に起因していることもあります。
中堅社員は、プレイングマネージャーとして最前線で活躍しつつ、後輩の育成業務も担うことが多く、結果的に過度な業務負担が集中しやすい傾向にあります。ルーティンワークをこなすスピードが上がると、上司からさらに仕事が振り分けられやすくなり、日常業務が減らないまま育成業務が加わるケースも少なくありません。心身ともに負担が大きくなり、ストレスが蓄積すると、前向きに業務に取り組めなくなり、ストレスなく働ける職場への退職を考えるきっかけとなります。
中堅社員は仕事に慣れることで成長実感が薄れ、仕事への意欲を喪失してしまうことがあります。若手時代には目の前の仕事をこなすことで成長を実感できましたが、ある程度業務に慣れると同じ業務の繰り返しになり、やりがいを見失うケースが少なくありません。仕事の背景や意義を理解する機会が不足したり、新たな挑戦の機会がなかったりすると、モチベーションが低下し退職を検討する大きな理由となります。
中堅社員が退職を検討する理由として、将来的な昇進や成長の見込みが立たないことが挙げられます。評価制度や人間関係に満足していても、自身のキャリアプランに不安があると、退職の大きな理由となり得ます。
特に、管理職への昇進が経済的安定や社会的ステータスの象徴とされていた時代とは異なり、現代では管理職の負担に焦点が当てられ、「管理職になりたくない」と考える中堅・若手社員が増加していることも背景にあります。年功序列的な昇進が期待できない企業や、明確なキャリアパスが示されない企業では、中堅社員は自身の成長やスキルアップの機会を見出せず、外部に新たな活躍の場を求めるようになります。
評価制度への不満も、中堅社員が退職を選ぶ主要な理由の一つです。特に、同期入社の社員との間で給与や待遇に差が開いている場合、「自分だけ正当に評価されていない」「相応しい報酬が受け取れていない」と感じ、不満を抱くことがあります。自己評価との乖離が大きいと、公正な評価がされていないと感じ、退職を考えるきっかけとなり得ます。正当な評価に加え、仕事内容に見合った報酬が設定されているかどうかも、中堅社員の満足度に大きく影響します。
職場内の人間関係の問題は、中堅社員が退職を決断する重要な理由の一つです。風通しの悪い組織や、上司とのコミュニケーションが円滑でない場合、社員はストレスを感じやすくなります。中堅社員は、上司と後輩の間で板挟みになりやすく、気を使いすぎて疲弊してしまうことも少なくありません。世代間の価値観の違いや、オンラインコミュニケーションの普及による意思疎通の難しさも、人間関係の悩みを複雑化させる要因となります。
中堅社員は、結婚や育児、介護といったライフステージの変化に直面しやすく、仕事中心だった生活に疑問を抱き、個人の生活様式と会社の働き方が合わないと感じることで退職を検討する場合があります。長時間労働やストレスの多い職場環境は、中堅社員の退職を促進する要因となります。リモートワークやフレックス勤務など、柔軟な働き方を求める声が増えている中で、多様な働き方に対応できない企業は、優秀な中堅社員の流出リスクが高まります。
中堅社員の離職が多い企業には、いくつかの共通する特徴が見られます。これらの特徴は、社員のエンゲージメント低下やキャリア形成への不安に直結し、結果として離職を招く要因となっています。経営層や人事担当者は、これらの特徴を認識し、改善に取り組むことが重要です。
中堅社員の離職が多い企業では、将来のキャリアパスが不明瞭であることが特徴の一つです。企業内での昇進やキャリアアップの具体的な道筋が見えないと、中堅社員は「このまま今の会社にいて良いのか」「転職すべきか」といった漠然とした将来への不安や焦りを抱えることになります。
特に、ジョブ型雇用が進展しつつある中で、依然として職能資格制度が主流の日本では、評価基準が曖昧で、昇進・昇格に必要な要件や能力開発が分かりにくい状況に陥りがちです。自己申告制度やジョブポスティング制度があっても、それが形骸化し、企業都合による異動が通例になっている場合、「結局キャリアは会社が決めるもの」という諦めが生まれ、社員が自らキャリアを考えることを止めてしまうことにつながります。
中堅社員の離職が多い企業では、トップダウン型の組織運営が根強く、社員の意見が反映されにくい傾向があります。このような企業では、経営層が決定した方針が一方的に現場に伝えられ、中堅社員が持つ現場の視点や改善提案が十分に聞き入れられないことが多いです。
その結果、中堅社員は自身の仕事への貢献度や影響力を感じにくくなり、組織へのエンゲージメントが低下します。風通しの悪い組織文化は、社員がストレスを感じやすく、特に若手・中堅社員にとっては、自身の成長や発言の機会が限られていると感じ、退職を検討する要因となることがあります。
人事評価や待遇への不満は、中堅社員の離職が多い企業に見られる顕著な特徴です。特に、昇給が停滞している、あるいは業界水準と比較して給与が低いと感じる場合、中堅社員は自身の価値が正当に評価されていないと感じるようになります。長く勤めるほど業務負担や責任が増すにもかかわらず、その重さに見合う報酬がなければ、不満が蓄積されやすくなります。
また、評価制度の透明性や公正さが欠けている場合も、社員は不信感を抱き、モチベーションの低下につながります。自己評価と会社からの評価に大きな隔たりがある場合、より適切な評価と待遇を求めて退職を選ぶ可能性が高まります。
中堅社員の離職が多い企業の特徴として、社内のコミュニケーション不足が挙げられます。コミュニケーション不足は、社員のエンゲージメント低下に直結するだけでなく、上司と部下の信頼関係構築を阻害します。中堅社員は、上司と後輩の間に立つことが多く、双方の意見を調整する役割を担いますが、十分なコミュニケーションがなければ、この役割を円滑に果たすことが困難になります。
また、世代間の価値観のずれから生じるコミュニケーションギャップも、問題を複雑にしています。これにより、中堅社員は孤立感を感じたり、自身の悩みを相談できる相手がいないと感じたりすることで、退職を検討する原因となり得ます。社員の定着には、日頃からの密なコミュニケーションを通じて、会社へのエンゲージメントを高め、「今後も働き続けたい」と感じられる職場環境を築くことが不可欠です。
中堅社員の離職は、単なる表面的な問題ではなく、経営層が見落としがちな組織の本質的な問題が潜んでいる可能性があります。特に、やばいと感じるような離職が続く場合、以下の点に注意が必要です。
経営者と社員の価値観のずれは、企業にとって悪い状況を招きかねない本質的な問題です。それぞれが育った環境や経験によって形成される価値観は、人間関係だけでなく、組織マネジメントにおいても重要な要素となります。経営層が売上や利益を最優先する一方で、社員がワークライフバランスややりがいを重視するといった価値観のずれは、コミュニケーションギャップを生み、社員のエンゲージメント低下につながります。
特に中堅社員は、管理職と現場の橋渡し役を担うことが多く、経営層の意向と現場の状況との板挟みになることで、ストレスを感じやすくなります。企業が持つビジョンや戦略を社員と共有し、相互理解を深める努力を怠ると、社員は企業への貢献意欲を失い、結果として離職へとつながる可能性が高まります。
組織開発や人材育成への投資不足は、中堅社員の離職を加速させる問題であり、経営層が見落としがちな本質的な課題です。多くの企業、特に中堅・中小企業は、限られたリソースの中で人材育成の重要性を認識しつつも、具体的な施策が体系的・包括的ではない、あるいは部門横断的な戦略に欠けている可能性があります。
中堅社員は、実務の中心を担う存在であるにもかかわらず、新人や若手社員に比べて教育の機会が少ないのが実情であり、スキルアップが後手に回ってしまうケースが少なくありません。これにより、中堅社員は十分なスキルアップができていないと感じ、自身の成長に不安を抱きます。人的資本への投資不足は、短期的な利益は確保できても、長期的な人材確保に綻びを生じさせ、結果的に状況に陥る典型例と言えます。特に、次世代の管理職を育成するためには、3年から5年といった中長期的な視点での投資が不可欠です。
管理職の意識と能力不足は、中堅社員の離職に直結する問題であり、組織全体の生産性にも悪影響を及ぼします。現代の管理職は、マネジメントの難易度が格段に高まっており、負担が大きいと感じる中堅・若手社員が増加傾向にあります。これにより、管理職への昇進候補者の能力やスキルが不足していると感じる企業も多く、実際に昇進しても活躍できないケースが見られます。
中堅社員に求められる役割は、単にプレイヤーとしての実務遂行だけでなく、部下や後輩の育成、マネジメント層と現場の橋渡しなど多岐にわたりますが、管理職の意識や能力が不足していると、これらの役割が十分に果たされません。特に、OJTが現場任せになり、指導担当者のスキルに依存している場合、育成の質にばらつきが生じ、中堅社員の成長を阻害する可能性があります。管理職自身が自身の役割を十分に認識できていない、あるいは必要なスキルを習得できていない状況は、中堅社員のモチベーション低下につながり、結果的に離職を招くことになるのです。
中堅社員の離職を防ぎ、彼らが企業にとって不可欠な存在として長く活躍し続けるためには、多角的なアプローチが必要です。企業は、彼らが抱える不安や不満に寄り添い、具体的な対策を講じることで、エンゲージメントを高めることができるでしょう。
中堅社員の離職防止には、企業の明確なビジョンと戦略を共有することが不可欠です。中堅社員は、単に目の前の業務をこなすだけでなく、組織全体の中での自身の役割や貢献度を意識する層です。そのため、会社や事業部、チームのビジョンや戦略を正しく理解することで、自身の業務が組織全体の目標達成にどう繋がるのかを認識し、より広い視野で問題解決に貢献できるようになります。
経営層と管理職が共通認識を持ち、ビジョンを具体的に伝えることで、中堅社員は仕事へのモチベーションを高め、企業への帰属意識を深めることができます。これにより、「この会社で仕事を続ける理由」を見出すことができ、退職の防止につながります。
中堅社員の離職防止には、個々のライフスタイルに合わせた柔軟な人員配置が有効なアプローチです。中堅社員は、結婚や育児、介護など、自身のライフステージが変化しやすい時期に差し掛かります。仕事中心の生活から、ワークライフバランスを重視するようになる社員も少なくありません。このような背景を考慮し、テレワークやフレックス勤務などの多様な働き方を導入したり、業務負担を軽減するための役割分担を見直したりすることで、社員は仕事と私生活の調和を図りやすくなります。
個人の状況に合わせた働き方を支援することは、社員のエンゲージメントを高め、長期的な就業意欲を維持するために非常に重要です。
中堅社員の離職を防ぐためには、キャリア形成を支援する制度の構築が不可欠です。中堅社員は、業務に慣れ、自己成長の実感を得にくいと感じることがあります。そのため、企業は社員が主体的にキャリアを築く意欲を持ち、その実現に向けて必要な自己成長を描けるような環境を提供する必要があります。具体的な施策としては、キャリアプラン研修の実施や、1on1ミーティングを通じた上司との定期的なキャリア面談が挙げられます。これにより、中堅社員は自身のスキルや経験を棚卸し、将来のキャリアパスを明確にすることができます。
また、新しい事業領域への挑戦や、異なる部署とのプロジェクト協働の機会を提供することも、スキルアップとモチベーション向上につながります。さらに、リスキリングできる環境を整えたり、副業支援制度を導入したりすることで、会社に所属しながら新しいチャレンジができるため、退職という選択肢を減らす効果が期待できます。
中堅社員の離職防止には、公正で納得感のある評価・報酬制度の導入が不可欠です。中堅社員は、自身の働きが正当に評価され、それに見合った報酬が得られているかを重視します。昇給が停滞したり、業界水準と比較して給与が低いと感じると、モチベーションの低下や不満につながり、退職を検討する大きな理由となります。そのため、評価基準を明確にし、社員が自身の成果と評価の関連性を理解できるよう、透明性の高い評価制度を構築することが重要です。
また、報酬だけでなく、インセンティブ制度の適切さや、キャリアアップに繋がる評価の仕組みも、社員の満足度を高める上で重要な要素となります。自己評価と会社からの評価の乖離をなくし、社員が納得感を持って働ける環境を整備することが、中堅社員の定着に繋がるでしょう。
中堅社員の離職防止には、管理職のマネジメント力強化が不可欠です。管理職は、中堅社員の直属の上司として、彼らの日々の業務やキャリア、人間関係の悩みに深く関わります。しかし、現代の管理職は、マネジメントの難易度が高まっており、若手や中堅社員からは「罰ゲーム」とまで称されるほど負担が大きいと感じられていることもあります。そのため、管理職が効果的な1on1ミーティングを実施できるよう、コミュニケーションスキルやコーチングスキルを向上させる研修が有効です。
これにより、管理職は中堅社員のキャリアプランや目標について話し合い、日々の業務の不満や人間関係のストレスに気づき、適切なサポートを行うことができます。また、部下への指導・育成力や、業務マネジメント、コンプライアンス・リスクマネジメントといった、管理職に求められる多岐にわたるスキルを強化することも重要です。管理職の意識改革と能力向上は、中堅社員が安心して働ける職場環境を築き、離職を防ぐ上で欠かせない要素です。
中堅社員の離職防止には、コミュニケーションの質と量を向上させることが極めて重要です。特に、1on1ミーティングのような定期的な対話の機会を設けることは、中堅社員が抱える不安や不満を早期に察知し、適切なサポートを行う上で非常に有効です。これにより、上司と部下の間に信頼関係が構築され、中堅社員がキャリアプランや目標について自由に話し合える環境が生まれます。
また、日頃の業務における報連相の徹底や、カジュアルな会話の機会を増やすことも、職場の風通しを良くし、心理的安全性を高めることに繋がります。世代間の価値観のずれが存在することを認識し、異なる価値観を尊重し「置いておく」姿勢も、円滑なコミュニケーションには不可欠です。コミュニケーションの質と量を高めることで、中堅社員のエンゲージメントが向上し、「今後も働き続けたい」と感じられる職場環境が醸成されるでしょう。
中堅社員の離職防止には、企業文化の根本的な見直しが必要となる場合があります。特に、古い慣習や独自の企業文化が根強く残っている企業では、中堅社員が時代に合わないと感じ、不満を抱くことがあります。例えば、トップダウン型の組織運営が強く、社員の意見が反映されにくい環境や、年功序列に固執し、成果主義への移行が遅れている人事制度などは、中堅社員の成長意欲を削ぎ、離職を促進する要因となり得ます。
企業文化の見直しには、経営層が主体となり、社員の多様な価値観を尊重し、心理的安全性を確保できるような環境を整備することが重要です。社員が自身の意見を発信しやすく、新しい挑戦を奨励するような文化を醸成することで、中堅社員は企業への愛着を深め、長期的なキャリアを築くことを選択するでしょう。
中堅社員の離職は、企業にとって深刻な問題であり、その原因は過度な業務負担、仕事への意欲喪失、昇進・成長の見込みのなさ、評価制度への不満、人間関係の問題、そして個人の生活様式との不一致など多岐にわたります。これらの理由が積み重なることで、中堅社員は退職を決意し、結果として職場の雰囲気悪化、業務遂行の困難さ、退職の連鎖、そして新たな人材採用と再教育にかかる費用といった多大な影響を企業にもたらします。
中堅社員が辞めていく企業には、将来のキャリアパスが不明瞭であること、トップダウン型の組織運営、人事評価や待遇への不満、コミュニケーション不足といった特徴が見られます。また、経営層が見落としがちな本質的な問題として、経営者と社員の価値観のずれ、組織開発や人材育成への投資不足、管理職の意識と能力不足も挙げられます。
これらの課題に対処し、中堅社員の離職を防ぐためには、明確なビジョンと戦略の共有、個々のライフスタイルに合わせた人員配置、キャリア形成を支援する制度構築、公正で納得感のある評価・報酬制度、管理職のマネジメント力強化、コミュニケーションの質と量の向上、そして企業文化の根本的な見直しといった実践的なアプローチが不可欠です。企業はこれらの対策を講じることで、中堅社員が長く安心して活躍できる環境を整備し、組織全体の持続的な成長を実現することができるでしょう。


記事公開日 : 2026/01/16
最終更新日 : 2026/01/15
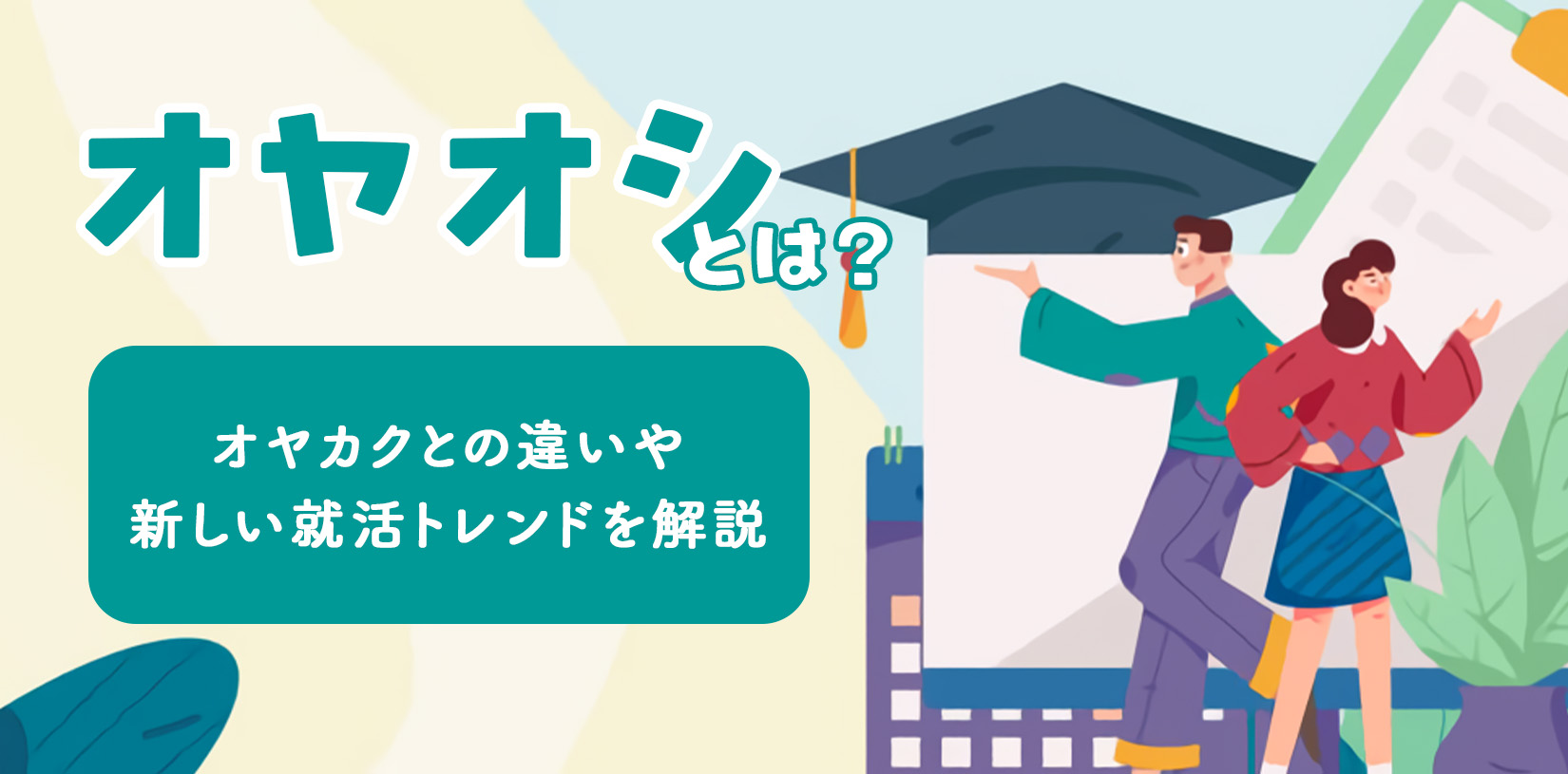
記事公開日 : 2026/01/13
最終更新日 : 2026/01/15
CONTACT