
【福利厚生としても注目!】近年話題のキャリアブレイクとは?
記事公開日 : 2026/01/16
最終更新日 : 2026/01/15
記事公開日 : 2025/08/27
最終更新日 : 2026/01/15
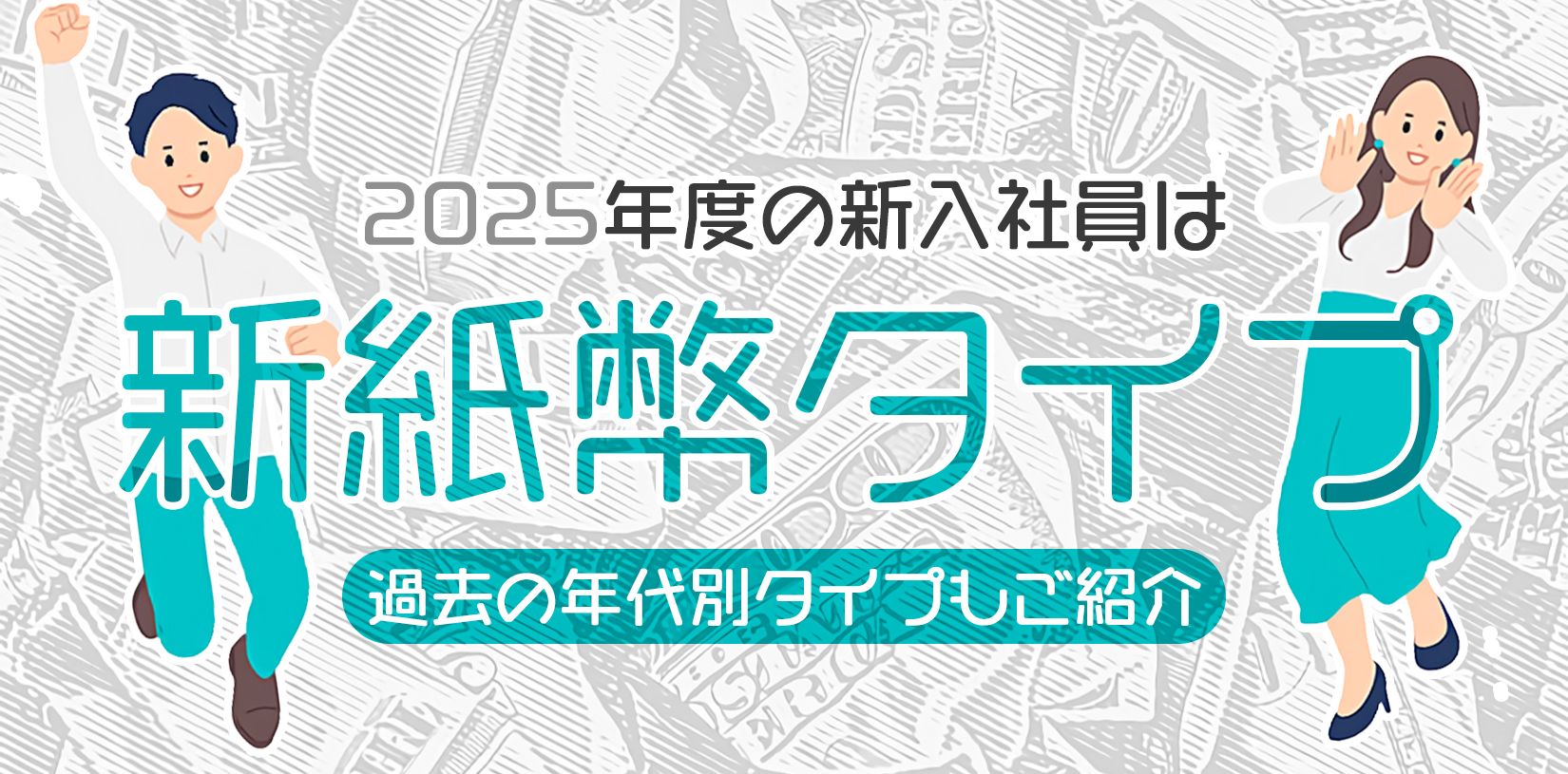
2025年度の新入社員は「変化を呼び込む!新紙幣タイプ」と称されており、その特徴は、最新技術と多様性を兼ね備えている点です。新入社員の特性を理解し、適切な育成を行うためには、過去の年代別タイプと比較し、世代ごとの傾向を把握することが不可欠です。本記事では、2025年度の新入社員の特徴から育成のポイント、さらには過去の新入社員タイプまで、人事担当者や管理職、育成担当者の皆様が新入社員の育成やマネジメントに役立つ情報をご紹介します。

2025年度の新入社員は、新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けながら学生生活や就職活動を送ってきた世代です。高校2年生の終わり頃からコロナ禍を経験し、大学生活の大半をオンラインと対面の併用で過ごしました。そのため、SNSやオンラインツールには慣れている一方で、対面での深い交流が不足し、コミュニケーション面に課題を感じる傾向があると言われています。
また、2025年卒採用からは「産学協議会基準」に準拠したインターンシップ評価が選考に活用され、早期に企業と接点を持った学生が多いという特徴もあります。彼らは「さとり世代」に該当し、過剰な物欲がなく、自宅を好み、興味のあることには妥協しないという傾向が見られます。さらに、情報収集が得意なデジタルネイティブであるため、ITに関する商品への興味関心が高い傾向にあります。
2025年度の新入社員は、産労総合研究所から「変化を呼び込む!新紙幣タイプ」と命名されました。この命名は、2024年7月に20年ぶりに発行された新紙幣が、偽造防止技術やユニバーサルデザインなど最新技術を盛り込んでいる点に由来しています。この新しい紙幣が多様性を受け入れ、最新のITリテラシーを身につけている新入社員の姿と重なる、という意味が込められています。
この世代の新入社員は、オンラインでの学習や就職活動を経験し、情報収集力や分析力を高めてきた背景があります。就職活動においては、早い段階から行動する人とそうでない人の二極化が進み、内定獲得のペースにも差が見られました。彼らは目的意識が強く、明確なゴールを持って企業を選ぶ傾向がありますが、過度な効率追求はチームワークや根気強い作業への理解をやや弱める可能性も持ち合わせています。
このように、2025年度の新入社員は常に最適解を求めようとする姿勢が強く、周囲からのフィードバックを素早く吸収する点が特徴的です。受け身のように見えても、自分発信のアイデアや自立心を持つ人材も多いため、明確な目標設定と柔軟なサポート体制をうまく組み合わせることで、大きな成長が期待できます。
2025年度の新入社員が「新紙幣タイプ」と称される理由は、多岐にわたる社会情勢と彼らの特性が合致しているためです。まず、彼らは高校2年生の終わり頃から新型コロナウイルスの影響を受け、大学生活の大部分をオンラインと対面のハイブリッド形式で過ごしてきました。そのため、オンラインツールやSNSを使いこなす高いITリテラシーを持ち合わせています。これは、偽造防止技術やユニバーサルデザインといった最新技術が盛り込まれた新紙幣の特性と共通する点です。
また、2025年卒の採用活動では、産学協議会基準に準拠したインターンシップ評価が選考に活用され、多くの学生が早期から企業と接点を持つ機会を得ました。この経験から、彼らは目的意識を明確に持ち、自分に必要な情報を効率的に収集・分析する能力が高い傾向にあります。しかし、オンラインでの交流が主だったために、対面での深いコミュニケーションに不安を感じる側面も持ち合わせています。
新紙幣の導入に際しては、設備投資や対応への変化が求められたように、この新入社員を受け入れる企業側も、彼らの特性に合わせたコミュニケーションや育成方法の変革が求められています。彼らの存在は、組織に新たな変化と活性化をもたらす可能性を秘めていることから、「変化を呼び込む!新紙幣タイプ」と名付けられました。
2025年度の新入社員の育成において、企業の人事担当者や管理職、育成担当者は、彼らの持つ独自の特性や価値観を深く理解することが不可欠です。
育成の具体的なポイントとしては、一方的に教え込むのではなく、個々の価値観を尊重し、適切な距離感で関わる姿勢が求められます。「なぜこの作業が必要なのか」「どのように役立つのか」といった目的や意義を論理的に示し、彼らが納得感を持って仕事に取り組めるような説明を心がけることが大切です。
2025年度の新入社員は、安定を求め、共感を大切にし、効率的に成長したいと願う「堅実で慎重、かつ自己成長意欲が高い共感型リアリスト」と称される世代です。
彼らは高校2年生の終わりから新型コロナウイルス感染症の影響を受け、大学生活の大半をオンラインと対面を併用した環境で過ごしました。この経験から、オンラインツールやSNSの利用に長けており、デジタルネイティブとしての特性を強く持っています。情報収集や分析能力が高く、常に最適解を求めようとする姿勢が見られますが、対面での深いコミュニケーションには課題を感じる傾向があります。
また、効率を重視する仕事観を持ち、時間対効果(タイパ)やデジタルコミュニケーション、成果重視を求めるキーワードとして挙げられています。しかし、従来の「根性論」や「まずはやってみる」というアプローチには理解を示しにくく、長期的な視点を必要とする業務にはモチベーションを見出しにくい側面もあります。
この世代は「さとり世代」に該当し、過剰な物欲がなく、自宅を好み、興味のあることには妥協しないという特徴もあります。また、バブル崩壊後の不況しか知らないため、熱くならず現実的な考え方をする堅実で慎重な世代とも言えます。
彼らは、職場での役割や目標が明確であることを好み、実務に入ってからも、成果を測定する指標が可視化されていることを求める声が多く、曖昧なプロセスや評価を苦手とします。これは、情報の断片を素早く集め、合理的に結論を導きたいというZ世代の特徴が反映されていると考えられます。ストレスへの耐性やモチベーションの保ち方についても、従来とは異なる感覚を持っています。失敗を恐れる傾向があるため、自ら考えて行動する自律型人材を育成するためには、失敗を許容し、主体的な行動を評価する企業の姿勢を明確にすることが重要です。
SNSでのつながりやリアルタイムなコミュニケーションに慣れているため、一人で抱え込まずに周囲と連携することが得意ですが、一方で批判や否定的な意見には敏感な一面もあります。肯定的なフィードバックをこまめに与えることが、仕事への意欲向上につながると言えるでしょう。また、彼らは社会全体の動向や企業の理念にも敏感に反応し、企業がSDGsやダイバーシティ推進など、社会的課題への取り組みを示すことで共感を得やすく、組織へのロイヤルティが高まる傾向があります。これらの価値観を理解した上で、研修や評価制度を設計することが、若手育成のカギとなります。
毎年、その時代の流行や社会情勢を反映して命名される新入社員のタイプは、企業の人事担当者や管理職が新入社員の特性を理解する上で重要な指標となります。過去の年度別タイプを振り返ることで、世代ごとの価値観や行動様式の変化を把握し、今後の育成やマネジメントに活かすことが可能です。
新入社員のタイプは単なる流行語ではなく、その世代が育った環境や社会情勢、教育の変化を色濃く反映しているため、それぞれの特性を理解し、柔軟な姿勢で受け入れることが、新入社員の活躍を促す鍵となります。
このタイプは、目標をはっきり見定め、自分に必要な情報を自らセレクトして集めるという特徴を持っています。新NISA(少額投資非課税制度)のように、自らの資産形成に積極的に関わる姿勢を、自己のキャリア形成にも投影していると見ることができます。
彼らは、デジタルネイティブ世代であるため、情報収集能力に長けており、インターネットやSNSを駆使して効率的に必要な情報を探し出すことができます。しかし、一方で、目標を明確にする傾向が強いゆえに、理想と現実とのギャップを感じやすく、悩む傾向もあると言われています。企業の人事担当者や管理職は、この世代の新入社員に対して、具体的な目標設定をサポートし、彼らが自ら選んだ道で成長を実感できるよう、明確なフィードバックと適切なサポートを提供することが重要です。また、彼らが抱える悩みや不安に寄り添い、現実的な視点を提供することで、早期離職の防止にも繋がるでしょう。
2023年度の新入社員は「可能性はAIチャットボットタイプ」と称されました。この名称は、チャットボットがユーザーの入力に対して自動的に回答する会話型システムであることに由来しています。
この世代は、新型コロナウイルス感染症の影響で学生生活の大半をオンラインで過ごしたため、対面でのコミュニケーションにストレスを感じやすい傾向がありました。しかし、知らないことをすぐに検索するデジタルスキルに長けており、オンラインでの情報収集やツール操作には慣れています。まさにAIチャットボットのように、適切な情報やアドバイスが与えられれば、想定を超える成果を発揮する可能性を秘めている、という特性がこのタイプには込められています。
彼らを育成する際には、デジタルネイティブとしてのスキルを活かしつつ、対面でのコミュニケーション不足を補うための配慮が求められました。具体的には、未熟な面や不安を汲み取った上でのコミュニケーション、そして適切なアドバイスを継続的に提供することで、彼らの持つ潜在能力を引き出すことが重要であると考えられます。
22年度の新入社員は「新感覚の二刀流タイプ」と命名されました。このタイプは、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を大きく受けた世代であり、大学の後半期に様々な活動制限を経験しました。インターンシップや就職活動を、対面とオンラインの二つのスタイルで器用にこなしてきたことから、「二刀流」と称されています。
しかし、就職活動中に職場の雰囲気や仕事に関する情報が得にくかったため、入社後に思い描いていたイメージと現実とのギャップにとまどう傾向が見られました。彼らはオンライン慣れしている反面、対面でのコミュニケーションには不慣れな面があると言われています。また、配属先や勤務地へのこだわり、SDGsへの興味、タイムパフォーマンス志向など、これまでの新入社員とは異なる「新感覚」の価値観を持っています。この世代を育成する際には、彼らの未熟な言動を受け止めた上で、一人ひとりに寄り添った温かい交流と育成支援が求められます。そうすることで、彼らの才能が開花し、環境変化にも適応できる「リアル二刀流」へと成長していくことが期待できます。
2021年度の新入社員は「仲間が恋しいソロキャンプタイプ」と名付けられました。この世代は、新型コロナウイルス感染症の拡大によって学生生活が一変し、オンラインでの孤独な就職活動を経験したことが背景にあります。初めてのソロキャンプのように、まごつくことも多かったものの、状況に適応し、工夫を凝らしてたくましく就職活動を乗り越えました。
オンライン面接など新しい就活スタイルに自由さや気楽さを感じた学生もいた一方で、対面での交流が減少したことで「孤立」や「孤独」を感じる人も多かったようです。そのため、仲間とのつながりや社会との関係性の重要性を強く感じているのがこの世代の特徴です。企業の人事担当者や管理職は、彼らが社会に出てから、自分の時間を楽しみつつも、様々な人々と出会い、仲間づくりができるよう、積極的にフォローすることが求められました。先輩社員が働く仲間として温かく受け入れ、サポートすることで、彼らの持つ潜在能力を引き出し、組織の一員として活躍を促すことが重要であると考えられます。
2020年度の新入社員は「結果が出せる厚底シューズタイプ」と命名されました。この名称は、衝撃吸収性に優れ、ランニングの記録更新に貢献している厚底シューズの登場が背景にあります。
この世代の新入社員は、ITの進展とともに育ち、先輩たちのノウハウをうまく活用して就職活動を乗り切った点が、厚底シューズが最新テクノロジーとノウハウの蓄積によって高いパフォーマンスを発揮する姿と重なると考えられています。彼らは、学生時代に「働き方改革」が社会的なテーマとなったことで、残業時間やワークライフバランス、福利厚生に関心を寄せる学生が増加し、自分を成長させてくれる場や居心地の良い職場環境を重視する傾向が見られました。
特に、この年度は新型コロナウイルスの影響により、従来の働き方の見直しが急務となった時期であり、彼らをどのように育成していくかが課題となりました。彼ら一人ひとりの価値観やキャリアプランを考慮した育成・指導・活用が、彼らの力を最大限に引き出す上で重要であるとされています。
2019年度の新入社員は「呼びかけ次第のAIスピーカータイプ」と名付けられました。この命名には、近年のAIブームと採用の売り手市場という時代背景が大きく影響しています。AIスピーカーが多くの人々から興味を持たれ、求められる存在であるように、この年の新入社員も売り手市場の中で企業から熱望される存在でした。
しかし、AIスピーカーは多彩な機能を備えているものの、その能力を最大限に発揮させるためには、細かい設定や手厚い教育、環境の構築が不可欠であるという点も共通しています。つまり、この世代の新入社員も多機能でポテンシャルを秘めている一方で、上司や先輩からの適切な「呼びかけ」(指示やサポート)がなければ、その能力を十分に引き出すことが難しい、という特性を示唆しています。彼らを育成する際には、個々の能力を見極め、それぞれの特性に合わせたきめ細やかな指導と、能力を活かせる環境を整えることが重要であると考えられます。
新入社員のタイプは年度ごとに変化しますが、どのタイプが活躍できるかは一概には言えません。それぞれのタイプが持つ特性を理解し、その強みを最大限に引き出すような育成やマネジメントを行うことが重要です。
例えば、2025年度の新紙幣タイプは高いITリテラシーと多様性を受け入れる柔軟性を持っていますが、対面コミュニケーションに課題を感じることもあります。この場合、デジタルツールを積極的に活用した業務指示や、オンラインでのきめ細やかなフィードバック、そして対面での交流機会を意識的に設けることが活躍の鍵となるでしょう。一方、2024年度の新NISAタイプは目標設定力と情報収集力に長けていますが、理想と現実のギャップに悩む傾向があります。彼らには具体的な目標設定のサポートと、現実的な視点を提供することで、モチベーションを維持し、着実に成果を出せるよう導くことが求められます。
重要なのは、画一的な育成方法ではなく、個々の新入社員の特性や価値観を理解し、彼らが安心して挑戦できる心理的安全性の高い環境を提供することです。そして、結果だけでなく、努力の過程や仕事への姿勢も積極的に承認し、適切なフィードバックを段階的に行うことで、新入社員は自身の強みを活かし、組織の中で成長し、最大限に貢献できるようになるでしょう。
新入社員のタイプは、その時代の社会情勢や教育環境を色濃く反映しており、毎年異なる特徴が見られます。2025年度の新入社員は「変化を呼び込む!新紙幣タイプ」と称され、高いITリテラシーと多様性を受け入れる柔軟性を持つ一方で、対面コミュニケーションに課題を感じる傾向があることが明らかになりました。
過去を振り返ると、2024年度の「セレクト上手な新NISAタイプ」や2023年度の「可能性はAIチャットボットタイプ」など、それぞれの世代が持つ強みと課題が見えてきます。企業の人事担当者、管理職、育成担当者は、これらの年度別タイプ論を参考に、新入社員一人ひとりの特性や価値観を深く理解することが重要です。画一的な育成ではなく、個性を尊重し、彼らが安心して能力を発揮できる心理的安全性の高い環境を提供することが求められます。例えば、デジタルネイティブ世代である新入社員には、オンラインツールを積極的に活用した業務指示や、効率を重視した明確な目標設定が有効です。また、キャリア自律への意識が高い傾向にあるため、早期に成長を実感できる機会を提供し、キャリア形成を支援することも重要となります。
新入社員の新しい視点や能力は、組織に新たな風を吹き込み、企業文化を変革するチャンスでもあります。彼らのポテンシャルを最大限に引き出し、共に成長していくための柔軟な育成体制を構築することが、これからの企業には不可欠と言えるでしょう。


記事公開日 : 2026/01/16
最終更新日 : 2026/01/15
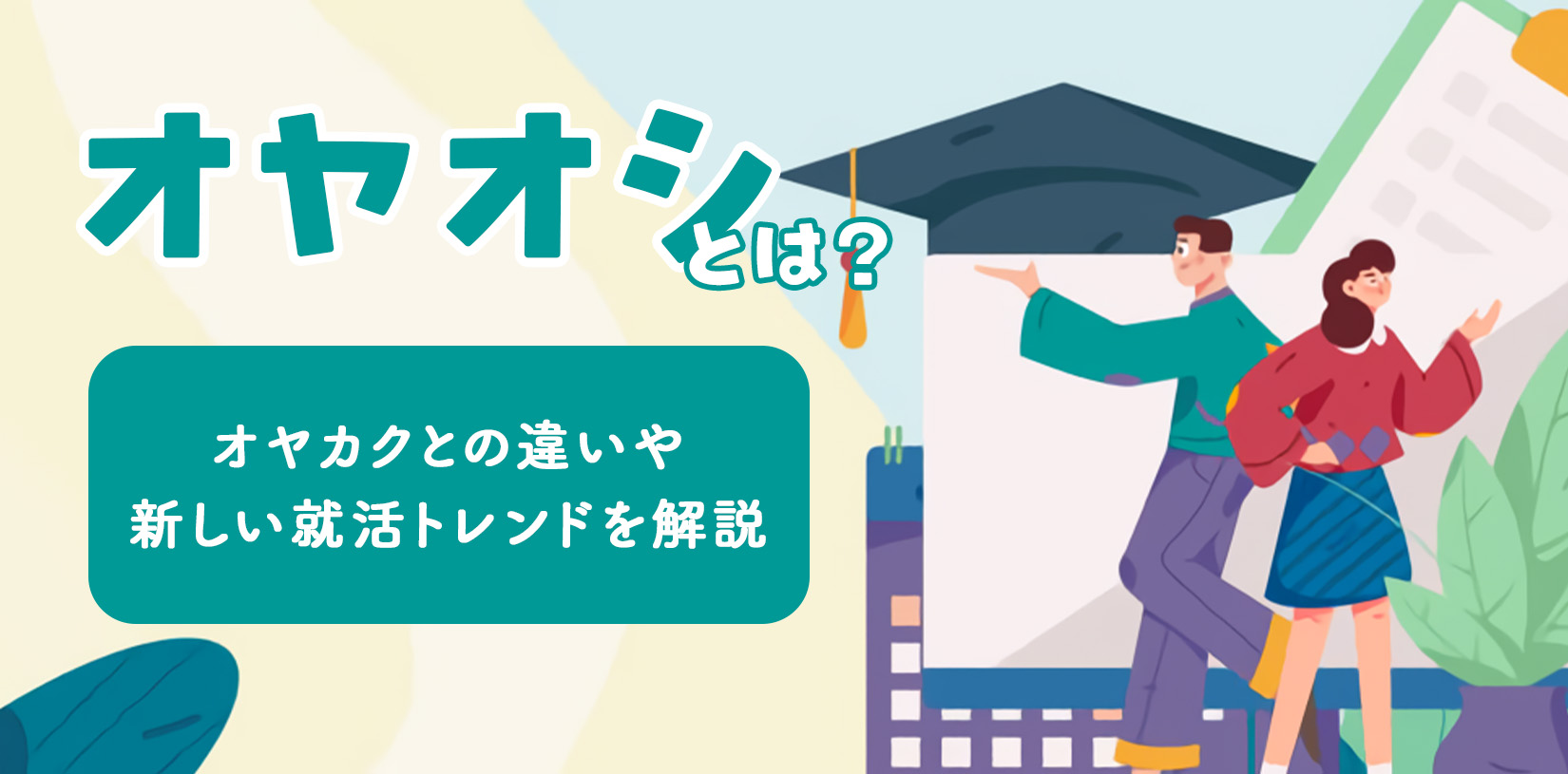
記事公開日 : 2026/01/13
最終更新日 : 2026/01/15
CONTACT