
STARフレームワークとは?面接での使い方を例文付きで解説
記事公開日 : 2025/11/10
最終更新日 : 2025/12/11
記事公開日 : 2025/01/15
最終更新日 : 2025/12/11
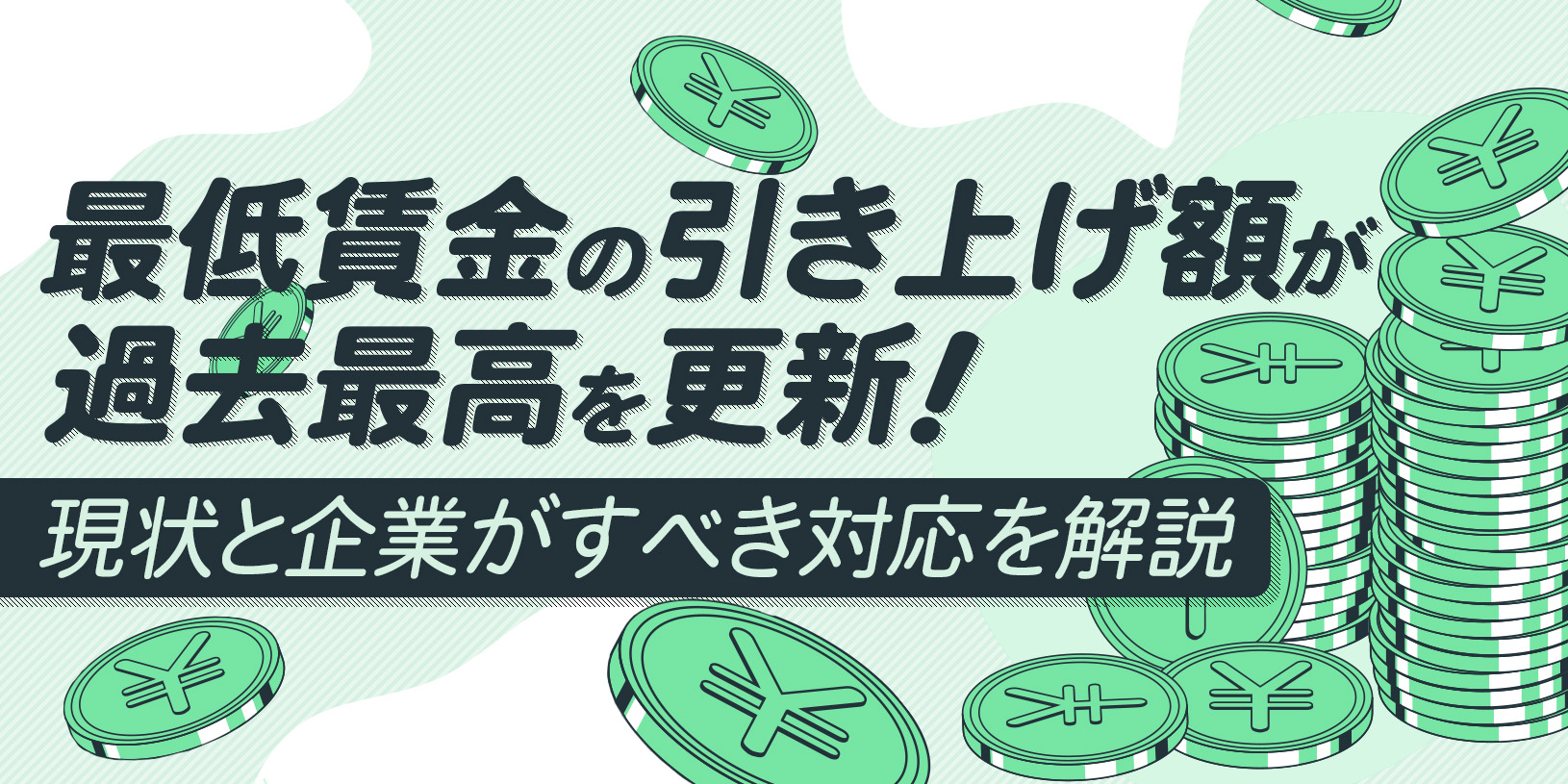
2024年8月29日、厚生労働省は最低賃金を1,055円に引き上げると発表しました。この額は2023年から51円増加しており、過去と比較しても急速な上昇が進んでいます。2002年からのデータによれば、最低賃金が50円上がるのに約7年を要していましたが、現在では1年でそれを超える増加が起こっています。
ここから最低賃金が下がる可能性は極めて低く、今後も継続的に50円以上の上昇が見込まれるでしょう。これは、多くの経営者がこれまで経験したことのない急激な賃金上昇であり、企業経営に大きな影響を及ぼしています。
最低賃金の引き上げに伴った労働者1人当たりの年間コスト増加額を試算すると、以下のようになります。
・月間労働時間(160時間)×51円(最低賃金増加額)= 8,160円
・年間(賞与2カ月分を含む14カ月)で換算すると、8,160円×14 = 114,240円
近年、新卒の給与引き上げ・ベースアップなどの賃上げに関する話題をよく耳にするようになったと思います。賃上げは採用手法の一種ではありますが、最低賃金が急上昇している状況では、最低賃金以上の水準で給与を引き上げないと競合他社との差は生まれません。採用市場で競争力を維持するため、毎年15,000円や20,000円といった大幅な賃上げが求められる状況です。
企業が賃上げを実施する主な理由には以下の2点があります。
・従業員の生活維持:インフレや物価上昇に対応し、従業員が安定した生活を送るため
・採用競争力の確保:人手不足が深刻化する中、競合他社に対抗するため
厚生労働省が発表した『労働者の過不足状況』によると、2024年2月のデータで全体の51%の企業が「人手不足を感じている」と回答しています。業種別では、建設業で65%、情報通信業で62%が不足を感じており、特に深刻な状況です。
このような売り手市場で、採用力を強化するためには給与水準を上げることが求められます。しかし物価上昇に伴い、エネルギー価格や原材料費が高騰しており、企業にとっての負担が重くなっている現状があります。
しかし、買い手市場であれば企業は賃上げを抑制しやすい傾向になるため、現在の売り手市場は労働環境の改善や賃金引き上げを促す点ではポジティブな側面も持ち合わせています。
賃上げを可能にするためには、企業が売上や利益を向上させることが不可欠です。そして高価格帯の商品やサービスが売れる市場を作ることが理想であり、その好例として海外の事例が挙げられます。例えば、アメリカではラーメン1杯が3,000円~5,000円という高価格で提供されていますが、それでも売れる価値が確立しており、従業員の待遇向上が実現しています。
日本でも同様に、企業が価値を提供し、それに対して顧客が適切な対価を支払う経済モデルを構築することが重要です。これを達成することで初めて賃上げが持続可能な形で実現できます。
採用手法もまた、時代の流れに合わせて変化しています。現在の若い世代は効率性を重視する傾向が強く、従来の転職サイトを介さず、より簡便に情報を得られる仕組みが求められています。
例えば、Indeedのような求人検索エンジンは、Web上の求人情報をまとめて検索できる仕組みを提供し、多くの求職者に利用されています。また、SNSを活用した採用活動も増加しており、企業と求職者が直接やり取りできる環境が整備されつつあります。
最低賃金の上昇は企業にとって大きな挑戦である一方、労働環境や経済モデルを改善する好機とも言えます。賃上げを避ける企業は魅力を失い、優秀な人材を確保できずに競争力を失う可能性が高まります。そのため、企業は売上や利益の向上を目指し、採用戦略を見直す必要があります。
現在の労働市場において競争力を維持するためには、賃上げを実施するだけでなく、根本的な経営戦略の見直しが欠かせません。こうした施策を実行することで、企業は成長を続け、将来の不確実性に備えることができるでしょう。


記事公開日 : 2025/11/10
最終更新日 : 2025/12/11

記事公開日 : 2025/10/28
最終更新日 : 2025/12/11
CONTACT