
【福利厚生としても注目!】近年話題のキャリアブレイクとは?
記事公開日 : 2026/01/16
最終更新日 : 2026/01/14
記事公開日 : 2025/03/10
最終更新日 : 2026/01/14
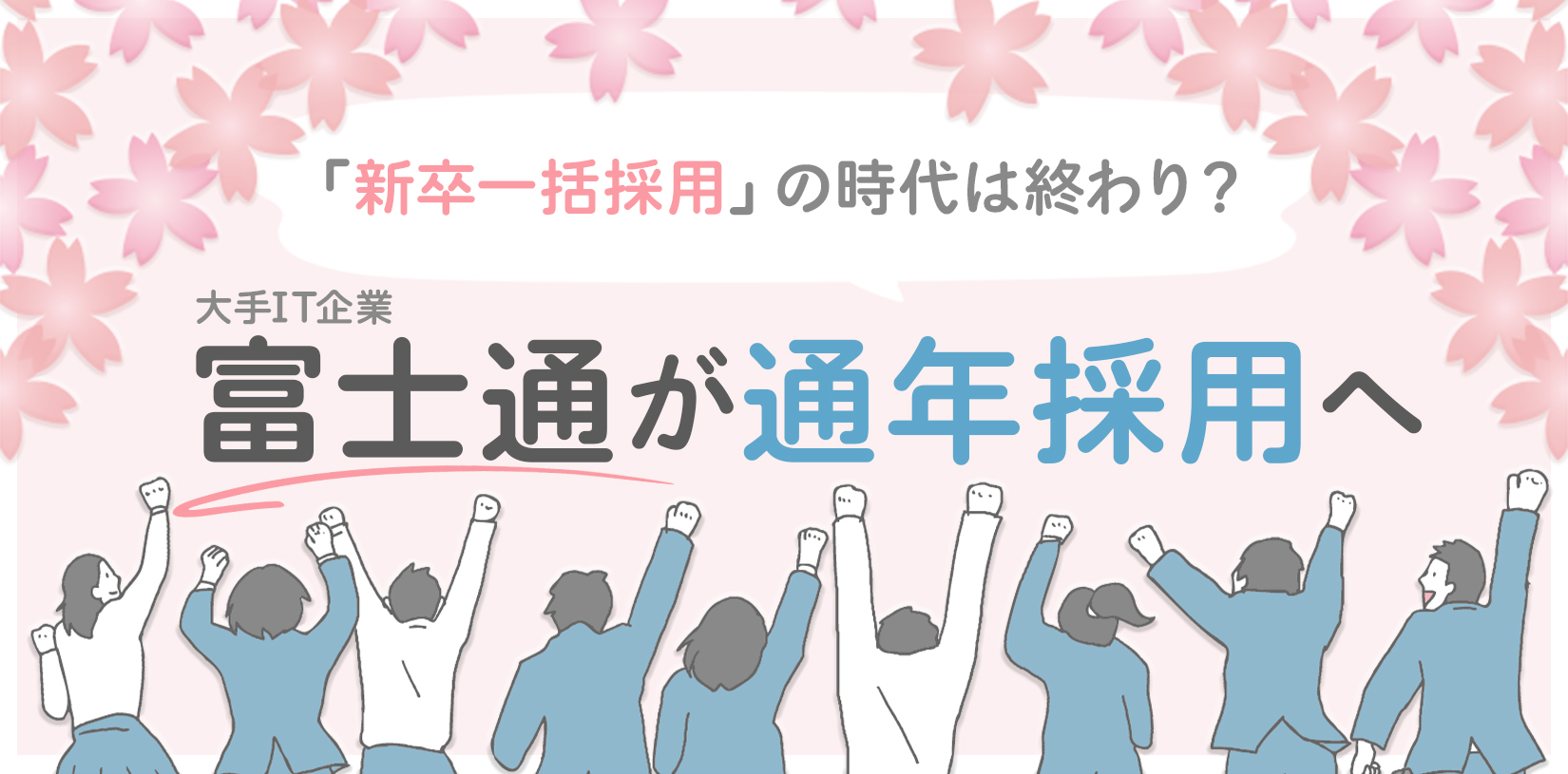
2024年3月7日、大手IT企業の富士通が「新卒一括採用」の廃止を発表しました。これまで日本企業で一般的だった採用方式を見直し、専門性に応じた「ジョブ型採用」を新卒・中途問わず適用する方針を打ち出しています。これは、日本の雇用市場にどのような影響を与えるのでしょうか?
本記事では、新卒一括採用の背景と、通年採用のメリット・デメリット、今後の採用市場の変化について解説します。

富士通はすでに、職務内容に応じて雇用契約や報酬を決定する「ジョブ型採用」を導入しています。これを新卒採用にも適用し、以下のような変更を行うことを発表しました。
・新卒一括採用を廃止し、通年採用へ移行
・採用計画の人数枠を撤廃
・一律の初任給を廃止し、専門性に応じた報酬体系に変更
・高度な専門性を持つ新卒人材には年収1000万円程度を支給
・入社前に最大6ヶ月の有償インターンシップを実施
富士通は、今回の決定の背景について次のように説明しています。
「入社後数年間で行っていた一部の定型業務はAI活用や業務プロセス改革で見直し、成長意欲が高い若手人材がより高いレベルの仕事に挑戦できるようにする」
「入社前の有償インターンシップの機会を増やし、学生と企業が互いに働くイメージを明確に持てるようにする」
つまり、採用時点で専門性の高い人材を確保し、入社後すぐに即戦力として活躍してもらうことを目的としているのです。
日本における「新卒一括採用」は、戦後の高度経済成長期に広まりました。企業は安定的に大卒人材を確保するため、毎年決まった時期に一括採用を行い、研修を経て社内で育成する方式を採用しました。
新卒一括採用は、日本の伝統的な「終身雇用」や「年功序列」とも相性が良く、新卒で入社した社員は定年まで勤め上げることが一般的でした。そのため、企業はじっくりと時間をかけて社員を育成する余裕がありました。
しかし、近年では社会の変化により、新卒一括採用のデメリットが浮き彫りになっています。例えば、
・採用スケジュールが固定されているため、海外の大学に通う学生が応募しにくい
・留学や病気などで就職活動のタイミングを逃すと、機会を得にくい
・転職が一般化し、長期的な育成を前提とする採用方式が合わなくなってきた
こうした状況の中で、富士通の「新卒一括採用廃止」は、時代に即した変革といえるでしょう。
学生は自分のペースで就職活動ができ、企業も必要なタイミングで採用できる。
採用時点で一定のスキルを持つ人材を確保できるため、育成コストを抑えられる。
外資系企業のように通年採用を行うことで、海外の学生や多様なバックグラウンドを持つ人材も獲得しやすくなる。
新卒一括採用では一定の時期に採用業務が集中するが、通年採用では常に携われる人材を確保しなければならない。また、掲載延長に比例して求人情報の掲載コストも増加する。
新卒一括採用では、同じ時期に就職活動を行う仲間が多く情報交換がしやすいが、通年採用ではその機会が減る。
通年採用では選考が長期間にわたるため、採用の手間が増える可能性がある。
富士通の決定を受け、今後は他の大手企業でも「新卒一括採用の見直し」が進む可能性が高いです。すでに、ユニクロ(ファーストリテイリング)や星野リゾートなどの企業は、新卒一括採用ではなく、通年採用を実施しています。大手企業の動きを見て、他企業が追随する可能性も高いでしょう。
通年採用が拡大することで、学生の就職活動の在り方も変わります。今後はこれまでよりも早い段階からキャリアプランを考え、在学中からインターンシップや職務経験を積んだりスキルを証明できる資格やポートフォリオを用意したりといった準備がより重要になってくるでしょう。
新卒一括採用の歴史を振り返ると、それが「終身雇用」や「年功序列」といった日本独自の雇用形態と深く結びついていたことがわかります。しかし、時代の変化とともにその制度疲労が顕在化し、より柔軟な採用方式が求められるようになりました。
富士通の「新卒一括採用廃止」は、日本の採用市場において大きな転換点となる可能性があります。今後、少なからず通年採用へシフトする企業が現れることで、学生側もこれまでのような「決まった時期の就職活動」ではなく、より長期的な視点でキャリアを考える必要が出てくるでしょう。
今後の採用市場は、企業と求職者の双方にとって、より「実力主義」な体制へと移行していくことが予想されます。


記事公開日 : 2026/01/16
最終更新日 : 2026/01/14
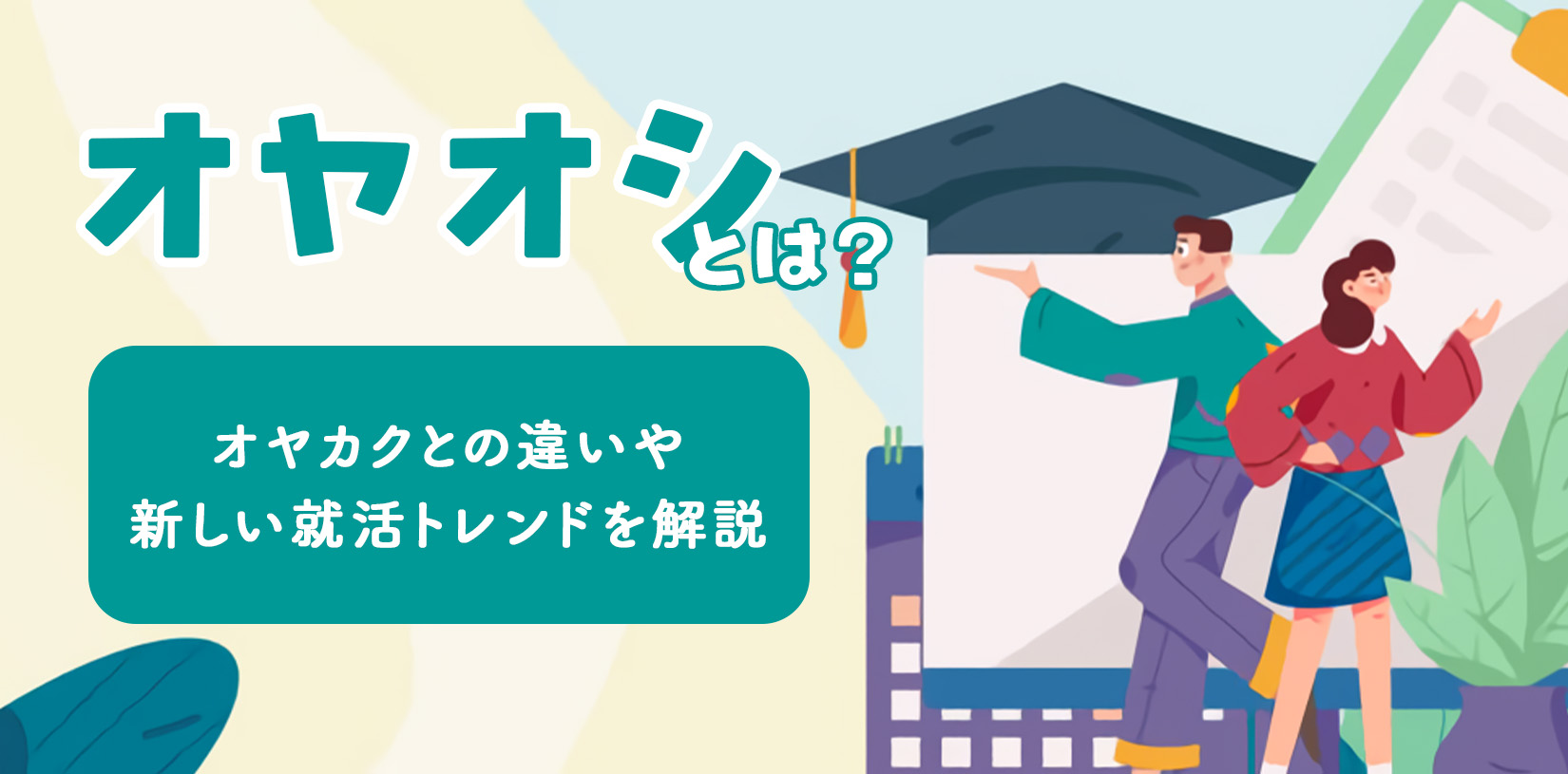
記事公開日 : 2026/01/13
最終更新日 : 2026/01/14
CONTACT