
タイパ抜群!?録画選考の活用法|Z世代に響かせるための動画面接
記事公開日 : 2026/01/29
最終更新日 : 2026/01/15
記事公開日 : 2025/08/18
最終更新日 : 2026/01/15
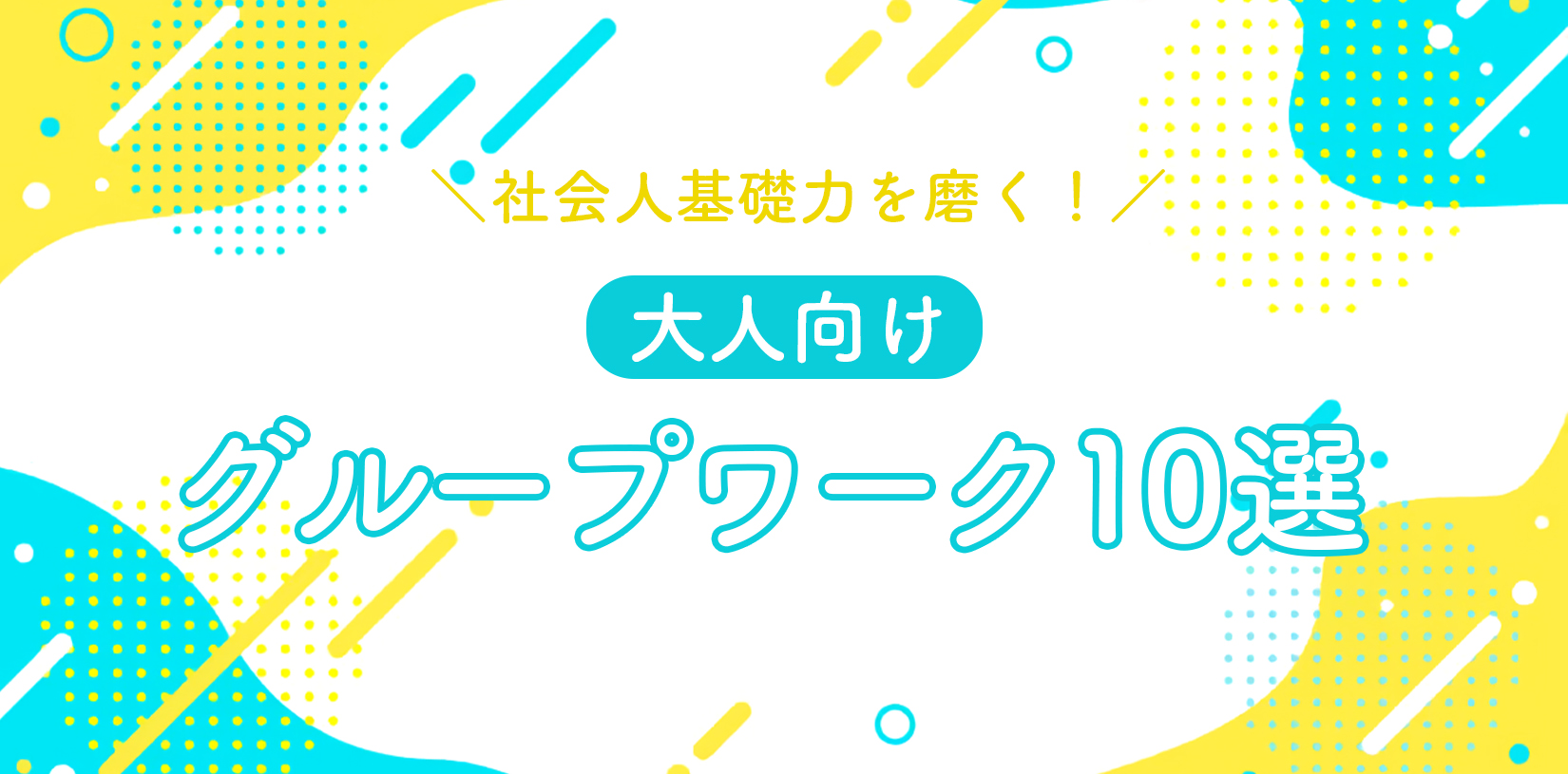
社会人として活躍し続けるためには、単に知識やスキルを習得するだけでなく、さまざまな人々と協調し、主体的に課題を解決していく「社会人基礎力」が不可欠です。企業の人材育成において、この社会人基礎力の向上は重要なテーマであり、効果的な手法としてグループワーク研修が注目されています。本記事では、社会人基礎力の構成要素から、グループワーク研修の具体的な利点、実施時の注意点、そしてすぐに活用できるおすすめのグループワークを10種類ご紹介します。

社会人基礎力とは、2006年に経済産業省が提唱した「職場や地域社会で多様な人々と仕事をしていくために必要な基礎的な力」を指します。これは、現代社会で活躍するために不可欠な能力として位置づけられています。社会人基礎力は、単なる業務スキルに留まらず、人間関係構築力や問題解決能力といった、より汎用的な能力の集合体です。特に、新入社員研修など、若手層の育成において重視されています。
社会人基礎力は、「前に踏み出す力(アクション)」「考え抜く力(シンキング)」「チームで働く力(チームワーク)」という3つの能力で構成されています。これらの3つの能力は、さらに細分化された12の能力要素から成り立っています。
まず、「前に踏み出す力」には、主体性、働きかけ力、実行力の3要素が含まれます。主体性とは、指示を待つのではなく自ら課題を見つけて行動する力、働きかけ力は他者に働きかけ巻き込む力、実行力は目標を設定し粘り強く取り組む力です。次に、「考え抜く力」は、課題発見力、計画力、創造力の3要素から構成されます。課題発見力は現状を分析して問題点を明らかにする力、計画力は課題解決に向けたプロセスを設計する力、創造力は新しいアイデアや価値を生み出す力を指します。
最後に、「チームで働く力」は、発信力、傾聴力、柔軟性、状況把握力、規律性、ストレスコントロール力の6要素で構成されます。発信力は自分の意見を分かりやすく伝える力、傾聴力は相手の意見を理解する力、柔軟性は異なる意見や立場を受け入れる力、状況把握力は周囲の状況を的確に理解する力、規律性は社会や組織のルールを守る力、ストレスコントロール力はストレスに対処する力です。
「人生100年時代」といわれる現代において、社会人基礎力の重要性は一層高まっています。経済産業省は2018年、「人生100年時代の社会人基礎力」として、これまでの社会人基礎力に加えて3つの新たな視点を追加しました。これは、長期化する職業生活において、個人が自らキャリアを切り拓き、変化に適応し続けるために必要な視点です。
具体的には、「何を学び続けるか」「どのように学ぶか」「学びをどう仕事や人生に活かすか」という3つの視点が重要とされています。これは、絶えず変化する社会や技術に対応し、個人の知識やスキルを継続的にアップデートしていく必要性を示しています。企業においては、既存の人材が長く活躍できる環境を整えるため、社員の学び続ける意識を高め、社会の変化に対応できる会社を目指すことが求められています。
グループワーク研修は、座学形式の研修とは異なり、参加者が主体的に学習に取り組める点が大きなメリットです。ここでは、グループワーク研修の具体的な利点について詳しく解説します。
グループワークは、参加者同士の相互理解を深め、チームの結束力を向上させる効果があります。日常業務では接点のない社員や、話す機会が少ない社員同士が共通の課題に取り組むことで、お互いの考え方や意見の背景を共有できます。これにより、一体感が生まれ、研修後も円滑なコミュニケーションにつながることが期待されます。特に、新入社員研修においては、同期とのつながりを築き、チームで働く力を養う上で非常に有効な手段といえるでしょう。
グループワークは、参加者が自ら考え、意見を発信し、課題解決に向けた実践的なアウトプットを行う貴重な機会を提供します。座学だけでは得られない、主体的な思考力や問題解決能力を養うことができます。例えば、課題解決型のグループワークでは、現実の業務上の問題を話し合いを通じて解決することを目指し、発信力や論理的思考力、チームとして結論を組み立てる力が重視されます。また、プレゼン型のグループワークでは、議論の結果をまとめ、発表するプロセスを通じて、プレゼンテーション能力やチーム内での調整力を鍛えることが可能です。
ゲーム性を取り入れることで、参加者の意欲や集中力を高める効果があります。特に、初対面の参加者が多い研修や、堅い雰囲気になりがちな新人研修などにおいて、ゲーム要素はアイスブレイクとしても機能し、和やかな雰囲気を作り出します。ゲームを通じて楽しみながら取り組むことで、参加者は自然とコミュニケーションを深め、チームワークや問題解決のプロセスを実践的に学ぶことができるでしょう。気軽に楽しめるゲーム型グループワークは、PDCAサイクルの学びにもつながる可能性があります。。
近年、リモートワークやオンラインでの業務が増加している社会において、グループワークもオンラインで実施する機会が増えています。オンラインツールを活用することで、物理的な距離に囚われずにグループワークを行うことが可能になり、多拠点間の交流や、より多くの参加者の参加を促進できます。オンラインでのグループワークは、集合研修とは異なる留意点がありますが、ビデオチャットツールを活用し、チームで協力しながら謎解きや課題解決に取り組むことで、社員間のコミュニケーションを促進し、チームビルディングに貢献できるでしょう。
グループワークを研修として効果的に実施するためには、いくつかの重要な留意点があります。これらの点に注意することで、より実りある学びの場を提供し、参加者の満足度を高めることができます。
グループワークを実施する際には、事前に目的を明確にすることが最も重要です。単にグループで話し合わせるだけでなく、「親交を深めるため」「業務に関する知識を身につけるため」「問題解決能力を向上させるため」など、具体的な目的を設定し、参加者全員に共有することが大切です。目的が明確であれば、それに沿った適切なグループワークの内容を選定でき、研修効果を最大化できます。目的と内容がずれていると、参加者にとって有意義な時間とならず、研修効果も薄れてしまう可能性があります。
グループワークの議論を円滑に進めるためには、いくつかの注意点があります。まず、参加者が意見を出しやすい雰囲気作りが重要です。発言しづらいと感じているメンバーには積極的に話を振り、全員が意見を表明できる機会を設ける配慮が必要です。また、議論中に論点がずれたり、話の方向性が変わったりしないよう、ファシリテーターはメンバーの発言に気を配り、適宜軌道修正を行う役割を担います。
意見が出揃った段階で、書記を中心に意見を整理し、類似した意見はまとめ、ジャンル別に分類するなどして、効率的に議論を進めることが求められます。意見を大きく括りすぎて集約しすぎないよう注意し、必要に応じて改めて議論の機会を設けることも重要です。コミュニケーションが苦手な人がいる場合は、個人で考える時間を設けたり、付箋やマインドマップなどのツールを活用して意見を可視化したりする工夫も有効です。
グループワークをスムーズに進めるためには、役割分担を事前に検討することが有効です。一般的な役割としては、議論の進行役であるファシリテーター、時間管理を行うタイムキーパー、議論の内容を記録する書記、最終的な発表を行う発表者などがあります。役割を決める際には、グループワークの目的やゴールをメンバー全員で共有し、それぞれの役割に応じた責任と期待を明確にすることが重要です。また、役割に固執せず、メンバー全員が柔軟に協力し合う姿勢も求められます。タイムキーパー任せにするのではなく、全員が時間配分を意識することで、時間内に議論をまとめ、成果物を完成させる精度が高まります。
ここでは、社会人基礎力の向上に役立つ、おすすめのグループワークを10種類ご紹介します。これらのネタは、研修やチームビルディング、新人研修など様々な場面で活用でき、楽しみながら学びを深めることができます。
マシュマロチャレンジは、乾燥パスタ、マシュマロ、紐、テープを使い、制限時間内に自立可能な最も高いタワーを作るゲームです。所要時間は30分から120分程度で、1チームあたり4人から6人、全体では2人から40名以上で参加できます。
このワークは、チーム内のコミュニケーション、リーダーシップ、コラボレーション、イノベーション、問題解決戦略といった要素を重視しています。試行錯誤を繰り返しより良い方法を見つけ出すPDCAサイクルを実践的に学ぶことができ、短時間で効果的なチームビルディングが期待できます。マシュマロの重さに耐えられずタワーが倒れるという失敗を繰り返す中で、成功への道筋を見出すプロセスが重要です。
コンセンサスゲームは、特定の状況下でグループ内で合意形成を目指すゲームです。例えば、無人島に漂着した際に、限られた物資の中から優先順位をつけて生き残る方法を議論するといったテーマがよく用いられます。
このゲームは、参加者のコミュニケーション能力、論理的思考力、交渉力、そしてチームとしての合意形成能力を養うことを目的としています。所要時間は比較的短時間で設定されることが多く、少人数(6人から8人程度)での実施に適しています。意見の対立を乗り越え、いかにしてチームとしての最適解を導き出すかがポイントとなります。
謎解き脱出ゲームは、チームで協力して物語に沿った謎を解き明かし、制限時間内に脱出を目指すゲームです。オンラインやリモートでの実施も可能であり、ビデオチャットツールを活用することで、離れた場所にいるメンバーともコミュニケーションを取りながら協力プレイが楽しめます。
想定プレイ時間は1時間から1時間半程度で、10名から500名程度の大人数でも参加可能です。コミュニケーション不足の解消や、チームビルディングに役立ちます。特にオンライン版では、情報共有の重要性や、非日常空間での協調性が試されます。
マーダーミステリーは、参加者が推理小説の登場人物となり、与えられたシナリオと役割に基づいて事件の真相を解き明かす体験型ゲームです。参加者はそれぞれ秘密の目的や背景を持ち、互いに情報を交換しながら容疑者を特定し、犯人を見つけ出すことを目指します。
オンラインやリモートでの実施も可能で、Discordなどの音声通話アプリやセッション用ツールを用いることで、密談のような駆け引きも楽しめます。少人数(6人から8人程度)で深く推理やコミュニケーションを楽しむことも、大人数で盛り上がりを重視してプレイすることも可能です。このゲームは、コミュニケーション能力、論理的思考力、情報整理能力、そして洞察力を高めるのに適しています。
人狼ゲームは、参加者が「村人」と「人狼」の2つの陣営に分かれ、議論を通じて人狼を探し出す、または人狼が村人を欺き生き残ることを目指す心理戦ゲームです。
このゲームは、相手の表情や発言から真実を見抜く洞察力、自分の立場を偽り説得する発信力、そして論理的に思考し議論を組み立てる力を養うのに非常に効果的です。短時間で手軽に実施でき、コミュニケーションを活発化させるアイスブレイクとしても人気があります。プレイ人数は2人から大人数まで幅広く対応できますが、少人数でも深く駆け引きを楽しめます。
ドミノ倒しは、チームで協力してドミノを並べ、見事な連鎖を完成させる共同作業型のグループワークです。目標を共有し、協力して一つの成果物を創り上げる過程で、チームワーク、計画性、細やかな作業への集中力、そして問題解決能力が培われます。途中でドミノが倒れてしまうなどの予期せぬアクシデントが発生することもあり、その際の対応力やチーム内での連携も試されます。比較的長い時間をかけて取り組むワークとして、6人から8人程度のグループで実施するのに適しています。
ペーパータワーは、数枚の紙とハサミ、のりやテープなどの道具のみを使い、制限時間内にできるだけ高いタワーを作る共同作業型のグループワークです。
このゲームは、チームで協力して最適な設計を考え、効率的に作業を進める能力を養います。材料の制約がある中で、いかに創造力を発揮し、安定した構造を構築できるかがポイントとなります。短時間(例えば10分から30分程度)で実施可能であり、グループで取り組むことで、コミュニケーションの活性化やPDCAサイクルを体験する良い機会となります。
ヘリウムリングは、チーム全員で人差し指の第一関節にフラフープを乗せ、指がフラフープから離れないようにしながら、地面まで下ろすゲームです。所要時間は5分程度の短時間で、少人数でも実施できます。
このゲームは、チーム内のコミュニケーション、協調性、そして非言語的な連携能力を養うのに非常に効果的です。フラフープが上に上がってしまう「ヘリウム現象」をいかに克服し、メンバー全員でタイミングを合わせてフラフープを降ろせるかがカギとなります。人数が多いほど難易度が上がり、チームビルディングに役立つでしょう。
ダイアログ・イン・ザ・ダークは、視覚を完全に遮断した「純度100%の暗闇」の中で、視覚以外の感覚を駆使して様々な体験をするワークショップです。視覚障害者のアテンドに導かれ、参加者は声や触覚、聴覚などを頼りにコミュニケーションを取りながら課題をクリアしていきます。
この体験は、普段意識しないコミュニケーションの重要性や、固定観念に囚われずに多様な価値観を受け入れることの重要性を気づかせます。性別や年齢、肩書きといった属性が意味を失うため、本質的なコミュニケーションが促され、チームビルディング、リーダーシップ、イノベーション能力向上、ダイバーシティ推進といったテーマに効果的です。1,000社以上の企業で導入されており、数名から最大24名程度まで参加可能です。
共通点探しゲームは、チーム内でメンバー同士の共通点をできるだけ多く見つけるゲームです。自己紹介を通じて互いの情報を共有し、ユニークな共通点を発見していく過程で、コミュニケーションが活性化し、相互理解が深まります。
短時間で手軽に実施でき、2人から6人程度の少人数グループでも楽しめます。特に、初対面のメンバー同士のアイスブレイクとして有効であり、チームの結束力を高めるきっかけにもなります。発見した共通点を発表することで、さらにグループ間の交流を促進することも可能です。
社会人基礎力は、現代社会で活躍するために不可欠な能力であり、グループワーク研修はその向上に大きく貢献します。チームの結束力向上、実践的なアウトプットの機会、ゲーム性による参加促進、そしてオンライン実施の可能性といった多くの利点があります。効果的なグループワークを実施するためには、目的の明確化、議論における適切な進行、そして役割分担の検討が重要です。
本記事で紹介した10種類のグループワークは、新人研修から既存社員のスキルアップまで、様々な研修の場で活用できるでしょう。これらのグループワークを通じて社会人基礎力を磨き、組織全体の成長につなげていきましょう。


記事公開日 : 2026/01/29
最終更新日 : 2026/01/15
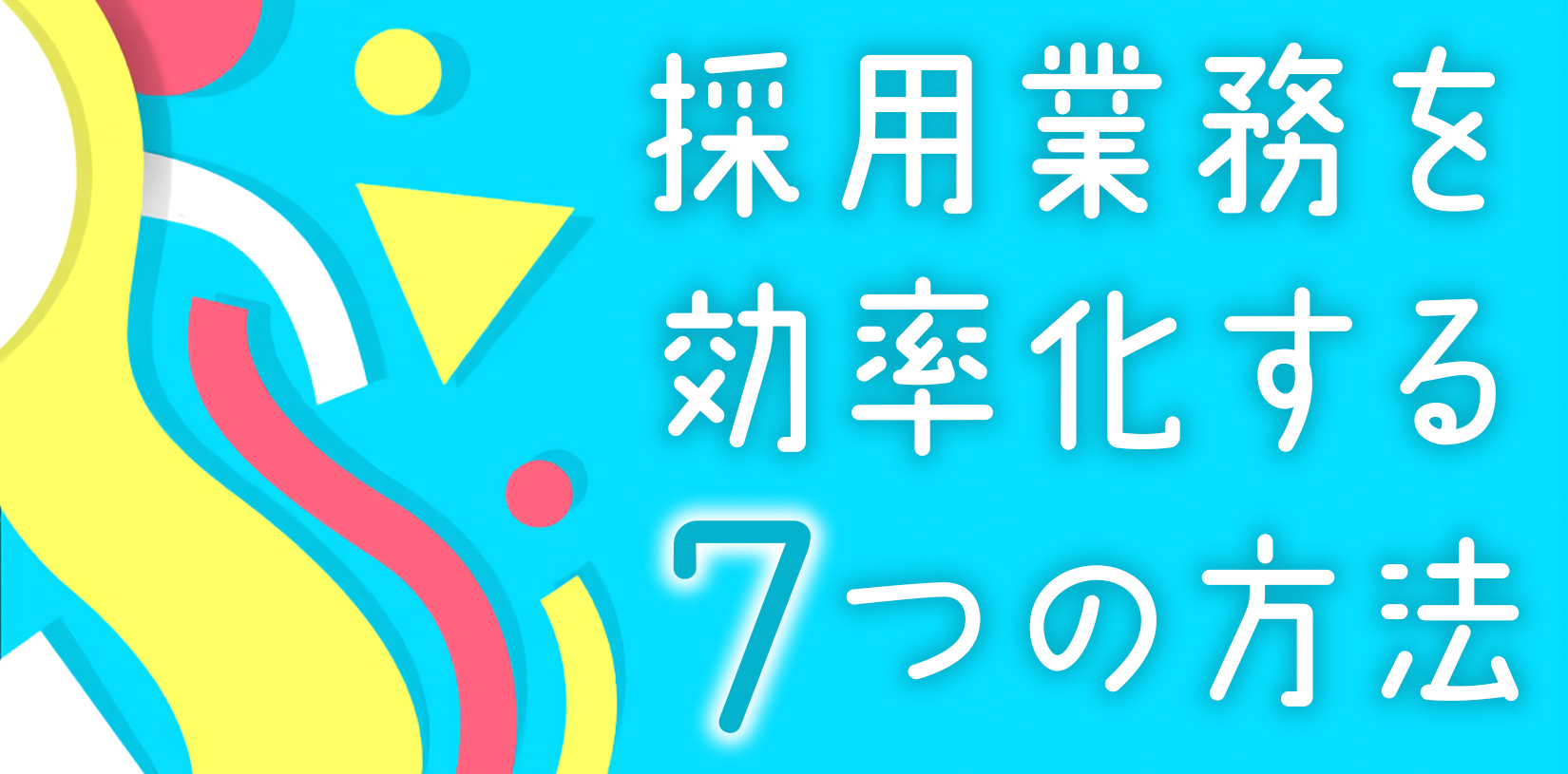
記事公開日 : 2026/01/27
最終更新日 : 2026/01/15
CONTACT