
タイパ抜群!?録画選考の活用法|Z世代に響かせるための動画面接
記事公開日 : 2026/01/29
最終更新日 : 2026/01/15
記事公開日 : 2025/09/10
最終更新日 : 2026/01/15
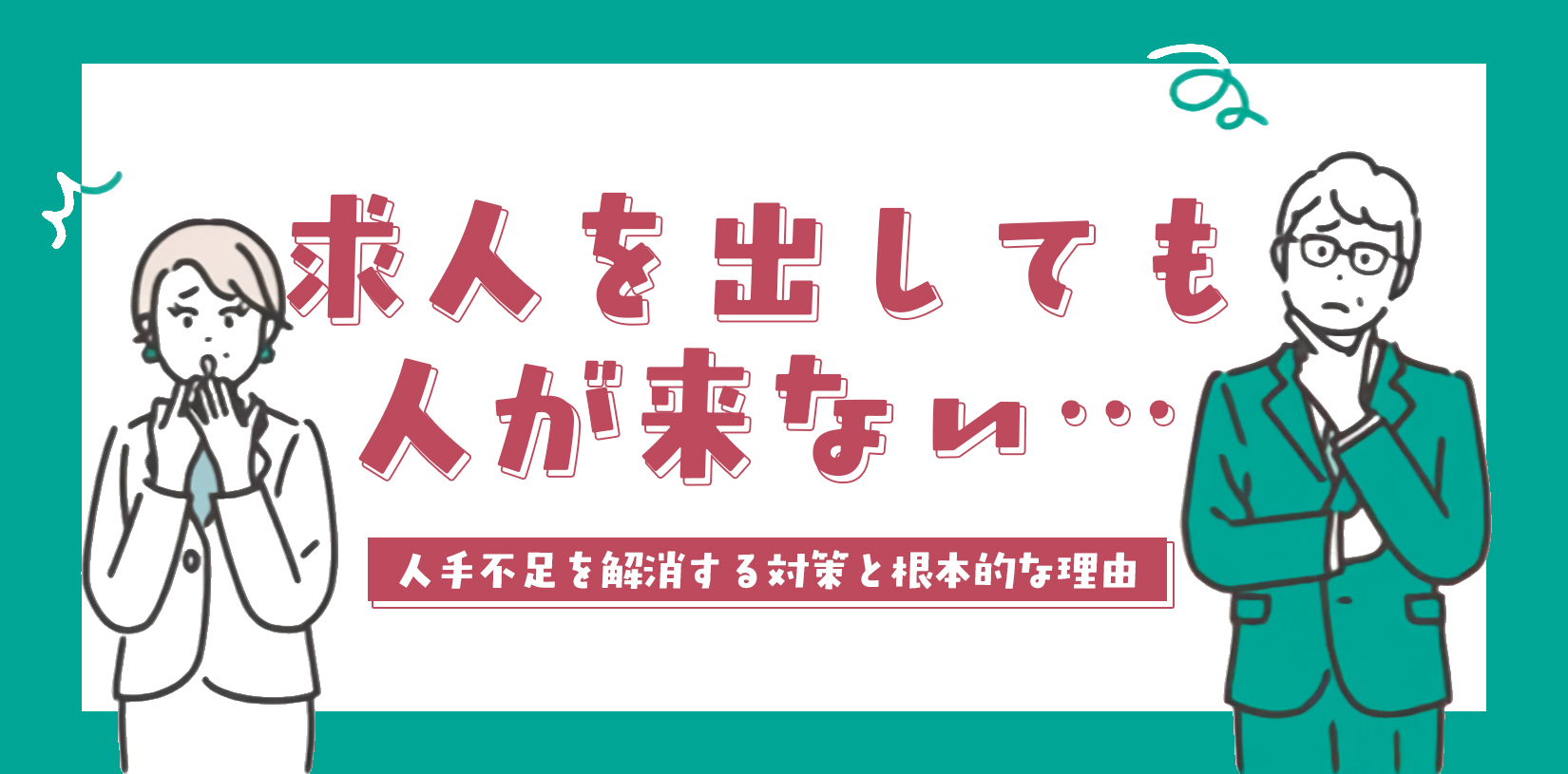
求人を出しても応募がなく、人が来ないという悩みは多くの企業が抱えています。この問題の背景には、少子高齢化による労働人口の減少だけでなく、求職者の価値観の変化や企業側の採用活動における課題が存在します。
本記事では、応募が集まらない根本的な理由を多角的に分析し、人手不足を解消するための具体的な対策を解説します。

少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少を背景に、多くの企業で求人を出しても応募がこない状況が続いています。実際、2023年に日本商工会議所が実施したアンケート調査では、中小企業の約70%が人手不足と回答しており、そのうち約60%以上が事業に影響が出ていると回答しました。特に、介護・看護業、建設業、宿泊・飲食業などでは8割近くの企業が人手不足を感じています。
高い有効求人倍率は、求職者にとって有利な売り手市場を意味し、企業側は人材獲得競争の激化に直面しています。2025年7月の全国の有効求人倍率は1.22倍で、求職者1人に対して1.22件の求人がある状況です。しかし、これはハローワークに登録された求人・求職を基にした数値であり、求人サイトなどの情報は含まれていない点に留意が必要です。
中小企業では特に、知名度や待遇面で大企業との差が生まれやすく、より深刻な人手不足に陥る傾向が見られます。これは、中小企業が求める人材と、求職者が求める労働条件の間にギャップがあることも一因と考えられます。このような課題に対し、企業は多角的な対策を講じる必要があります。
求人に応募が集まらない背景には、社会構造の変化だけでなく、企業側の採用活動に潜む複数の理由が考えられます。求人票の魅力不足、求人媒体のミスマッチ、応募条件の厳しさ、競合他社との比較、そして企業情報の発信不足など、見直すべき点は多岐にわたります。これらの根本的な原因を一つずつ特定し、改善していくことが応募者増加の第一歩となります。
求人票の内容が曖昧で、仕事の魅力ややりがいが具体的に伝わっていないことが、応募に至らない大きな理由となります。単に業務内容を羅列するだけでは、求職者は入社後の働き方をイメージできません。
どのようなスキルが身につき、将来的にどのようなキャリアを築けるのか、また、どのような人物が活躍しているのかといった具体的な情報が不足していると、他社の求人に埋もれてしまいます。求職者は自身の経験やスキルがその企業でどう活かせるかを知りたがっているため、ターゲットとなる人物像を明確にした上で、その人物にとって魅力的に映る言葉で仕事内容や企業の強みを表現する必要があるのです。
曖昧な表現は、求職者に不信感を与えたり、企業への関心を抱かせにくくしたりする要因となります。特に「応相談」や「経験に応じて」といった給与や待遇に関する表現は、具体的な情報不足から応募をためらわせる可能性があります。求人票は企業と求職者をつなぐ最初の接点であり、ここで自社の魅力を最大限に伝えきることが、採用成功の鍵を握る理由となるのです。
求人媒体は、Webメディア、紙媒体、人材紹介など多岐にわたり、それぞれに異なる特色と利用者の層が存在します。実際に、求人サイトは新卒向け、中途向け、アルバイト・パート向けといった雇用形態別のサイトや、エンジニア、主婦(夫)など特定のターゲットに特化したサイトに分かれています。たとえば、若手人材を求めているにもかかわらず、ミドル層以上の利用者が多い媒体を選んでいては、求める人材からの応募は期待できません。
自社が求める人材のペルソナ(年齢、経験、スキル、価値観など)を詳細に設定し、そのペルソナがどのような媒体で情報収集を行うかを分析した上で、最適な掲載先を選定することが重要です。例えば、20代の若手層にアプローチしたい場合はマイナビ転職やdoda、Re就活などが有効とされています。一方で、紙媒体である求人フリーペーパーや折込チラシは地域密着型であり、Webに不慣れなミドルシニア層に効果的という特徴があります。
このように、求人媒体ごとの特性を把握し、自社の採用ターゲット層と合致する媒体を選ぶことは、採用活動を効率的に進める上で不可欠な理由です。
求めるスキルや経験のレベルを高く設定しすぎていることも、応募者数が伸び悩む理由の一つです。即戦力を求めるあまり、「必須スキル」の項目を多く設けたり、実務経験年数を長く設定したりすると、多くの潜在的な候補者をふるい落としてしまう可能性があります。
特に、市場に少ないスキルを持つ人材を求めている場合は、応募のハードルがさらに高くなります。例えば、特定のプログラミング言語での開発経験が5年以上必須、といった条件を設定した場合、その言語の使用経験が3年の優秀な人材であっても応募をためらってしまうでしょう。
本当にそのスキルが必須なのか、入社後の研修で習得可能ではないかを見極め、「歓迎スキル」として記載するなどの柔軟な対応が求められます。条件を緩和することで、ポテンシャルを持った優秀な人材からの応募を促せます。例えば、未経験者歓迎の求人でも、入社後の教育体制や研修プログラムを明確にすることで、意欲のある人材の応募を増やすことができます。また、応募条件の緩和は、新たな視点や多様なバックグラウンドを持つ人材の獲得にもつながる理由となります。
給与や休日、福利厚生といった雇用条件が、同じ地域や業界の競合他社と比較して見劣りする場合、応募が集まらない決定的な理由になり得ます。求職者は複数の企業を比較検討するのが一般的であり、特に条件面は重要な判断基準となります。自社の提示する条件が地域の給与相場や業界水準から乖離していないか、客観的に分析しなくてはなりません。たとえば、東京都の最低賃金は2023年10月に1,113円に引き上げられましたが、これはあくまで最低限の基準であり、他社が提示する時給や月給はこれを上回ることがほとんどです。
もし自社の給与水準が競合他社よりも低い場合、優秀な人材はより高い報酬を提示する企業へ流れてしまう可能性が高いでしょう。給与水準をすぐに引き上げることが難しい場合でも、年間休日数を増やしたり、フレックスタイム制や時短勤務制度を導入したり、独自の福利厚生を導入したりするなど、他の要素で魅力を高める工夫が求められます。
例えば、育児中の社員向けに「短時間勤務制度」を充実させたり、社員の健康増進のために「フィットネスジムの利用補助」を設けたりすることも、差別化の理由になります。競合の動向を常に把握し、自社の条件を定期的に見直す視点が不可欠です。ハローワークインターネットサービスや民間の求人情報サイトで近隣の競合企業の求人情報を確認し、自社の条件との比較を行うことは、現状把握の第一歩となります。
求職者が企業選びで重視するのは、給与や仕事内容といった条件面だけではありません。企業のビジョンや価値観、職場の雰囲気、社員同士の関係性といった社風も重要な判断材料となりますが、この情報発信が不足していることが応募をためらわせる理由になります。
求人票だけでは伝わりにくいこれらの情報は、自社の採用サイトやSNS、社員インタビューなどを通じて積極的に発信していく必要があります。実際に働く社員の声や日常の様子を伝えることで、求職者は入社後の働き方を具体的にイメージしやすくなり、企業文化への共感を抱くきっかけにもなります。
具体的には、会社のブログで社員の1日のスケジュールやランチの様子を紹介したり、Instagramでオフィス環境や社内イベントの写真を投稿したりすることが考えられます。動画コンテンツとして、社長や部署のリーダーが企業の将来性や事業への想いを語るインタビューを公開することも効果的です。例えばIT企業であれば、開発チームがどのような技術を使ってどのような課題解決に取り組んでいるのかを具体的に紹介することで、技術力を重視するエンジニア層に強くアピールできます。また、福利厚生として「社員旅行」や「部活動」がある場合、その活動の様子を発信することで、職場の人間関係の良さや働きがいを視覚的に伝えられます。
これらの情報は、求職者が「この会社で働きたい」と感じるための重要な理由となり、応募を促進するだけでなく、入社後のミスマッチを防ぐ上でも非常に有効です。
応募を増やすためには、求職者が企業選びの際にどのような点を重視しているのかを正確に理解しておく必要があります。給与や休日といった基本的な条件はもちろんのこと、自身のキャリアプランやプライベートとの両立、長期的な安定性など、多角的な視点で企業を評価しています。
求職者が応募をためらう理由、あるいは応募を決断する理由を把握し、彼らが求める情報を提供することが、採用成功の鍵を握ります。
求職者が給与を確認する際、提示された金額だけでなく、その企業での将来的な昇給の可能性や評価制度の透明性も重視します。入社時の給与が相場通りであっても、昇給モデルが不明確であったり、キャリアアップの道筋が見えなかったりすると、長期的に働くイメージが持てず応募をためらう理由となります。
求人情報には、具体的な給与額に加えて、モデル年収例や評価制度、キャリアパスの事例などを記載することが望ましいです。どのような成果を上げれば評価され、給与に反映されるのかを明確に提示することで、求職者は自身の将来性を具体的に描くことができ、働く意欲を高めることにもつながります。
ワークライフバランスを重視する傾向が強まる中で、年間休日数や残業時間は企業選びの重要な指標となっています。休日が少なかったり、残業に関する情報が不明確だったりすると、プライベートの時間が確保できないのではないかと懸念され、応募を敬遠される理由になります。年間休日数(例:120日以上)や完全週休2日制といった具体的な情報を明記することは不可欠です。
また、平均残業時間や残業代の支給実績、有給休暇の取得率といったデータを公開することで、透明性の高い企業であるという印象を与えられます。実際に、リクルートの調査によると、転職活動で重視する項目として「休日・休暇」を挙げる人が約6割、「残業の少なさ」を挙げる人も約5割に上っています。働きやすい環境が整備されていることを客観的な数値で示すことが、求職者の安心感につながるのです。
福利厚生は、社員の生活を豊かにし、企業への帰属意識を高める重要な役割を担います。社会保険完備や交通費支給といった基本的な福利厚生はもちろんのこと、住宅手当や家族手当、退職金制度、財形貯蓄制度、社員食堂の有無など、独自の制度が充実している企業は、求職者にとって大きな魅力となる理由です。
特に、ライフステージの変化に対応できる育児・介護休業制度の取得実績や、時短勤務制度の活用状況を公開することは、長期的なキャリア形成を考える求職者にとって安心材料となります。例えば、育児中の社員が安心して働けるように企業主導型保育園と提携したり、介護休暇を柔軟に取得できる制度を設けたりする企業は、多様な働き方を尊重しているというメッセージを伝えられます。
また、健康経営に力を入れ、フィットネスジムの利用補助や健康診断のオプションを充実させることも、社員の健康維持をサポートする企業として好印象を与えます。これらの福利厚生は、単に待遇面を良くするだけでなく、企業が社員を大切にしている姿勢を示す重要な指標となり、安心して長く働ける環境であるという理由から、求職者の応募意欲を大きく左右するのです。
求職者は、自身の将来性や成長機会を重視しており、その企業で働くことでどのようなキャリアプランを描けるかを具体的に知りたいと考えています。単に業務内容を羅列するだけでは、入社後のイメージが湧きにくく、応募に至らない理由となります。
そこで、求人情報ではプロジェクトの具体例や使用する技術、チーム体制、入社後に期待される役割などを詳細に記述することが求められます。例えば、営業職であれば「入社後3年でリーダー、5年でマネージャー昇格を想定し、既存顧客への深耕営業から新規開拓まで幅広く経験できる」といった具体的なキャリアパスを示すことで、自身のキャリアをイメージしやすくなります。
また、研修制度や資格取得支援制度といった、スキルアップをサポートする企業の取り組みについても言及することで、成長意欲の高い求職者にアピールできます。自身のスキルやキャリアが、その企業でどのように向上していくのかが見えないと、成長意欲の高い求職者にとっては応募しない理由となるため、具体的な仕事内容を通じて、入社後の活躍イメージとキャリアプランを明確に提示することが、応募への意欲を引き出す上で重要なのです。
求人に応募が来ない原因を特定した後は、具体的な対策を講じていく段階に入ります。人手不足を解消するためには、単一の施策だけでなく、多角的なアプローチが求められます。求人情報の見直しから、適切な媒体選定、労働条件の改善、そして企業の魅力発信まで、複数の打ち手を組み合わせることが重要です。
ここでは、応募者数を増やすために有効な4つの具体的な対策について解説します。
応募を増やすための基本的な対策として、求人情報の書き方をターゲットに合わせて最適化することが挙げられます。まず、どのような人材に来てほしいのか(ペルソナ)を明確に定義します。その上で、そのペルソナが魅力に感じるであろう仕事のやりがい、得られるスキル、企業の将来性などを具体的な言葉で記述します。
例えば、単に「営業職」と記載するのではなく、「新規顧客開拓を通じて市場を拡大するやりがい」や「最新のAIツールを活用したデータ分析スキルが身につく」といったように、具体的なメリットを提示することで、求職者の興味を引きつけやすくなります。専門用語を多用せず、平易な言葉で業務内容を説明したり、1日の仕事の流れを例示したりすることで、求職者は働き方をイメージしやすくなります。
加えて、企業の文化や職場の雰囲気を伝える写真や動画を掲載することも、求職者の共感を呼ぶ対策として有効です。また、ネガティブに捉えられがちな情報も正直に伝えることで、誠実な企業であるという印象を与え、入社後のミスマッチを防ぐ効果も期待できます。
採用活動の効果を高めるには、自社のターゲット人材が最も多く利用している求人媒体を選定し直す対策が不可欠です。総合求人サイトだけでなく、特定の職種や業界に特化した専門サイト、若年層にリーチしやすいSNSを活用した採用活動、あるいは地域の人材にアプローチできるハローワークや地方の求人誌など、選択肢は多岐にわたります。各媒体の利用者層や特徴を調査し、自社の採用ペルソナと合致するかどうかを慎重に検討します。
たとえば、全国的に広く人材を募集したいのであれば、リクナビNEXTやマイナビ転職といった大手総合求人サイトが有効です。これらのサイトは幅広い職種と経験層に対応しており、多くの求職者の目に触れる機会があります。一方、特定の専門職、例えばエンジニアやデザイナーを求めている場合は、GreenやWantedlyのようなIT・Web業界に特化した媒体がより効果的です。これらの媒体は専門性の高い求職者が集まるため、ミスマッチが少なく、効率的な採用につながりやすくなります。
また、20代の若手層にアプローチしたい場合は、Re就活やdodaなどの若年層向けの媒体を活用すると良いでしょう。地域密着型で、Webに不慣れなミドルシニア層をターゲットとする場合は、ハローワークの求人掲載や、地域で発行されている求人フリーペーパー、折込チラシなどが有効です。
複数の媒体を組み合わせたり、ダイレクトリクルーティングのような能動的な手法を取り入れたりするなど、採用チャネルを多様化させることも有効な手段です。自社の採用ターゲットに合った媒体を選び直すことで、求める人材からの応募数を増やし、採用効率を向上させる対策となります。
人手不足の解消には、競合他社と比較して見劣りしない労働条件や給与体系を整備することが不可欠です。地域の給与相場や同業他社の水準を綿密に調査し、競争力のある給与体系に見直すことが最も効果的な対策の一つです。厚生労働省の資料によると、2017年以降、労働力供給が労働力需要を下回っており、人手不足が広範囲の産業・職業で生じていると示されています。このような「売り手市場」では、求職者にとって魅力的な待遇提示が重要です。
給与の引き上げが難しい場合でも、年間休日数の増加、フレックスタイム制や時短勤務制度の導入など、働き方の柔軟性を高めることで企業の魅力を向上させることが可能です。 さらに、住宅手当や資格取得支援制度といった福利厚生の充実も、求職者への強力なアピールポイントとなります。
このような労働環境の整備は、新たな人材の獲得だけでなく、既存社員の定着率向上にも寄与します。 従業員が安心して長く働ける環境を整備することは、企業全体の生産性向上にもつながります。 労働環境や給与体系の見直しは、企業の持続的な成長と従業員の働きがいを両立させるための重要な対策であり、定期的に市場の変化に応じて見直すことが肝要です。
求人媒体の情報だけでは伝えきれない企業の魅力を発信するために、自社の採用サイトやSNSを積極的に活用する対策が有効です。社員インタビューを通じて仕事のやりがいや職場の雰囲気を伝えたり、社内イベントの様子を写真や動画で紹介したりすることで、求職者は企業のリアルな姿を知ることができます。
実際に、求職者が転職先を選ぶ際に重視する点として、仕事内容や給与だけでなく、企業の文化や働きがいといった情報も挙げられています。企業のビジョンや事業の社会貢献性といった、働く意義に関わる情報を発信することも、価値観に共感する人材を引きつける上で重要です。
継続的な情報発信は、企業の認知度向上にもつながり、潜在的な候補者層へのアプローチを可能にします。これらの対策は、求職者が「この会社で働きたい」と感じるための重要な理由となり、応募を促進するだけでなく、入社後のミスマッチを防ぐ上でも非常に有効です。
応募者数を増やすことに成功しても、採用した人材が早期に離職してしまっては、人手不足の根本的な解決にはなりません。重要なのは、採用のミスマッチを防ぎ、入社した人材が定着・活躍してくれることです。そのためには、応募者数を増やす対策と並行して、選考プロセスにおいて自社にマッチする人材を的確に見極め、スムーズな採用活動を実現するための工夫が求められます。
採用のミスマッチを防ぐためには、面接における評価基準を明確にし、面接官の間で統一する対策が重要です。評価基準が曖昧であったり、面接官の主観に頼ったりすると、採用判断にばらつきが生じ、自社が本当に求める人物像とは異なる人材を採用してしまう可能性があります。この点に関して、パーソル総合研究所の調査では、採用選考における面接官の評価のばらつきが、採用の質に大きく影響することが示唆されています。
スキルや経験だけでなく、企業の価値観や文化への適合性を見極めるための質問項目を事前に準備し、構造化面接を取り入れることが有効です。例えば、「チームで意見が対立した際にどのように解決しましたか?」といった行動面接の質問は、候補者のコミュニケーション能力や問題解決能力を客観的に評価するのに役立ちます。
また、評価項目ごとに5段階評価や点数制を導入し、面接官全員が同じ基準で評価できるようにトレーニングを行うことも重要です。候補者の回答を多角的に評価し、客観的な基準に基づいて合否を判断する体制を整えることで、採用の精度を高められます。
優秀な人材ほど、複数の企業から内定を得ていることが多いため、選考プロセスが長引いたり、連絡が遅れたりすると、候補者の入社意欲が低下し、他社へ流れてしまうリスクが高まります。
そのため採用プロセス全体を見直し、非効率な部分を削減する対策が求められます。書類選考から面接、内定通知までの期間をできるだけ短縮し、各段階で候補者への連絡を迅速かつ丁寧に行うことが重要です。
Web面接の導入や採用管理システム(ATS)の活用も、プロセスの効率化に寄与します。候補者体験(CX)を向上させる視点を持ち、スムーズな選考フローを構築することが、最終的な採用成功につながります。
人材採用や労働条件の改善には費用がかかりますが、国が提供する補助金や助成金制度を活用することで、その負担を軽減できる場合があります。これらの制度は、特定の条件を満たす労働者の雇用や、従業員のキャリアアップ、待遇改善に取り組む企業を支援することを目的としています。
自社の状況に合った制度を見つけ、積極的に活用することも人手不足解消に向けた有効な対策の一つです。ここでは、採用コストの負担軽減に役立つ代表的な補助金・助成金制度について解説します。
トライアル雇用助成金は、職業経験の不足などにより就職が困難な求職者を、原則3ヶ月間の試行雇用として雇い入れた場合に受給できる制度です。この制度を活用する対策により、企業は採用対象者の適性や業務遂行能力を試用期間中に見極めた上で、本採用に移行するかどうかを判断できます。
具体的には、ハローワークまたは地方公共団体が運営する無料職業紹介事業者の紹介により、未経験者やブランクのある人材を雇い入れる場合に適用されます。例えば、新卒で就職できなかった若年層や、育児・介護などで長期ブランクのある主婦(夫)層などが対象となるケースが多いです。
助成金の額は、対象労働者1人あたり月額最大4万円(最長3ヶ月間)で、母子家庭の母や父子家庭の父、または就職氷河期世代の人は月額最大5万円に増額されます。この助成金によって採用コストの一部が補填されるため、これまで採用の視野に入れていなかった層へもアプローチしやすくなり、採用におけるミスマッチのリスクを低減させながら、多様な人材を積極的に採用するきっかけとなります。本制度は、特に人手不足に悩む中小企業にとって、新たな人材を確保し、企業の活性化を図る上で有効な対策の一つと言えるでしょう。
中途採用等支援助成金は、中途採用者の雇用管理制度を整備し、中途採用の拡大を図る事業主に対して助成を行う制度です。この助成金には複数のコースがあり、例えば、生産性の向上に資する中途採用を行った場合や、45歳以上の人材を初めて採用した場合などが対象となります。
具体的には、中途採用計画の作成や採用後の研修制度の導入といった取り組みが要件となっており、計画的な中途採用を促進する対策として活用できます。経験豊富な即戦力人材の獲得を目指す企業にとって、採用活動にかかる経費の負担を軽減する有効な手段となるでしょう。
さらに、この助成金は、中途採用者の職場への定着を支援するための制度も含まれており、採用後のミスマッチを防ぎ、長期的な人材確保にも貢献します。例えば、中途採用者向けの職場適応訓練やメンター制度の導入費用が助成対象となる場合もあります。
このように、中途採用等支援助成金は、単に採用時の費用を補填するだけでなく、中途採用者が安心して活躍できる環境を整備するための多角的な対策を企業が講じることを後押しする制度と言えます。
キャリアアップ助成金は、有期雇用労働者やパートタイム労働者といった非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化や処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。
この制度を利用する対策は、既存の非正規社員のモチベーション向上と定着率アップにつながるだけでなく、求職者に対しても「正社員登用の道がある」「待遇改善に積極的である」というポジティブなメッセージとなります。
魅力的な労働条件を整備することは、新たな人材を惹きつける上でも重要な要素であり、この助成金はそのための投資を後押しします。
求人に応募が来ない人手不足の問題は、労働市場の変化という外的要因だけでなく、企業の採用活動における様々な理由が複雑に絡み合って発生します。求人票の魅力不足、求人媒体の選定ミス、厳しい応募条件、競合に見劣りする待遇、そして企業情報の不足といった内的な理由を一つひとつ見直し、改善していくことが不可欠です。
本記事で紹介した、求職者の視点に立った情報発信や労働条件の見直し、適切な媒体選定といった具体的な対策を実践することで、応募状況の改善が期待できます。さらに、採用後のミスマッチ防止や助成金の活用も視野に入れ、今後はさらに総合的な対策を講じていきましょう。


記事公開日 : 2026/01/29
最終更新日 : 2026/01/15
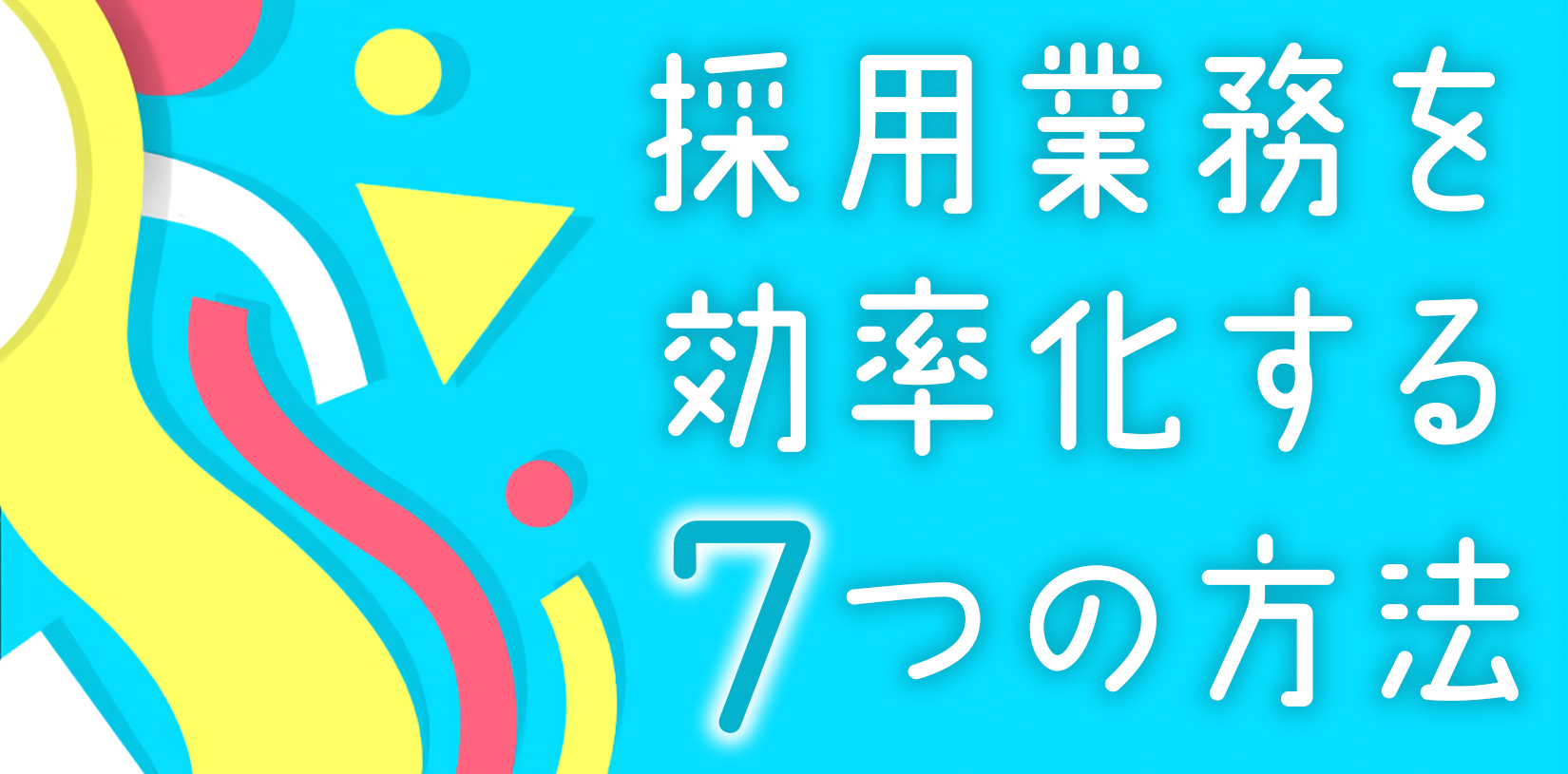
記事公開日 : 2026/01/27
最終更新日 : 2026/01/15
CONTACT